|
●報告
転倒予防教室による移動能力と心理的QOLへの効果
Evaluation of Fall Prevention Program on Physical Function
and Psychological QOL
| 征矢野 あや子a |
上岡 洋晴b |
岡田 真平b |
| Ayako SOYANOa |
Hiroharu KAMIOKAb |
Shinpei OKADAb |
| 高島 洋子c |
中尾 幸代c |
中村 恵子c |
| Yoko TAKASHIMAc |
Sachiyo NAKAOc |
Keiko NAKAMURAc |
| 坂本 育子c |
太田 美穂d |
武藤 芳照d |
| Ikuko SAKAMOTOc |
Miho OHTAd |
Yoshiteru MUTOHd |
a 東京大学大学院医学系研究科 地域看護学分野
b 身体教育医学研究所
c 東京厚生年金病院 看護部
d 東京大学大学院教育学研究科 身体教育学講座
a Department of Community Health Nursing, Graduate School of Medicine, the University of Tokyo
b Laboratory of Physical education and Medicine
c Department of Nursing, Tokyo Koseinenkin Hospital
d Department of Physical and health Education , Graduate School of Education, the University of Tokyo
Abstract
Experiencing a fall may lead to fear of falling and a decline in an elder's quality of life, including becoming housebound and/or depressed. The purpose of this study is to evaluate a fall prevention program on mood state, fear of falling and walking ability.
Subjects were participants in a fall prevention program at a general hospital. Persons who could not read, write or understand a questionnaire or who experienced an event that could influence their mood were excluded. They were assessed for psychological status (Profile of Mood States, POMS), Fall-related Self-Efficacy (F-SE) and walking ability at the beginning and at the end of the program. Assessment showed changes in the POMS at the end of the program. Scores decreased significantly for depression, fatigue, confusion, and total mood disturbance and improved significantly for vigor. No differences in the F-SE were found between the initial assessment and that at the end of the program. With regard to walking ability, there was improvement in 10 m walking time and Rt maximum length of step.
In summary, the fall prevention program improved psychological QOL as well as walking ability.
| ●代表者連絡先:〒113−0033 文京区本郷7−3−1 |
| |
東京大学大学院医学系研究科地域看護学分野 征矢野あや子 |
| |
TEL 03−5841−3597 FAX 03−5802−2043 E−mail ayakos-tky@umin.ac.jp |
| Key Words: Fall Prevention Program, Quality of Life(QOL) |
| 転倒予防、生活の質 |
1. はじめに
高齢期は心理的問題と身体的問題が密接に関わることが多い。このため、高齢者が転倒した場合、転倒によって骨折や寝たきり状態への移行を免れたとしても、転倒が自立生活を脅かす体験となり、自身の身体機能に対する自信を失うことがある。多くの先行研究が、転倒に関連した転倒恐怖や活動減少、抑うつ状態の存在を明らかにしている1)2)。転倒予防介入を行う場合、高齢期の心理的特徴を十分理解し、こころとからだの両面に同時に働きかけることが重要である。
身体機能の向上とともに転倒恐怖の軽減が認められた研究には、太極拳を用いた介入3)や理学療法士による訪問指導4)などがある。また、健康関連QOL(quality of life、生活の質)指標であるSF365)の変化をみた転倒予防介入研究6)もあるが、これは介入効果が認められたのは身体機能に関する下位領域のみであった。このように、恐怖や抑うつなど、1領域の陰性感情のみの変化を確認した研究はみられるが、運動習慣の維持に不可欠と言われている楽しみ7)に着目した介入研究はない。楽しみを含めた情動全体に働きかけ、効果を見ることが重要であろう。
東京厚生年金病院で開催している「転倒予防教室」では、運動の楽しさを重視した運動指導(表1、図1)や転倒予防自己効力感を高める要素を備えた運動指導(表2)を行っている8)9)。
そこで、本研究の目的は、転倒予防教室により気分・感情、身体機能が変化するかどうかを明らかにすることとした。
表1 「楽しさ」を引き出す転倒予防教室の指導方法と内容
1. 安全性の確保
十分なスタッフの配置
参加者の運動能力に応じたグループ分け
運動に適した環境整備(温度、広さなど) |
2. 参加者に応じた運動強度の調節
参加者の運動機能のアセスメント
(整形外科医・内科医による詳細な健康診断、歩行機能・バランス機能測定、運動中の心拍数測定) |
3. 運動の面白さ、ルール
親近感、コミュニケーション、偶然性やスリル、挑戦や達成感を考慮した運動プログラムバランス機能に応じた運動遊びの種目(図1) |
4. 指導者の態度
丁寧な言葉、尊敬を示した態度
肯定的な表現
ユーモア
スキンシップ |
楽しさを引き出す主な運動種目
ボディジャンケン
リズム体操
ボール運動(ハンドテニス、スポンジテニス) |
|
2. 方法
対象は、2000年1月から2001年3月までに転倒予防教室に参加した中高年者である。教室未修了者10名、自記式質問紙に回答できない程度の視力障害・低下を有する者8名(眼鏡を携帯していなかった者を含む)、質問の意味を理解できないと申告した2名、近親者の死亡など、調査時の気分・感情に著しく影響を及ぼす出来事があったと申告した2名等を除く、78名を分析対象とした。
表2 自己効力感に影響する4つの情報源と転倒予防自己効力感を高める転倒予防教室の機能
| 効力感に影響する情報源 |
介入案 |
| (1)制御体験:自分で実際に行い、失敗や成功をする |
生活動作を転ばずにやり遂げる体験を導く 安全な歩行方法・動作の訓練 簡単な動作から始める |
| (2)代理体験:他人の成功や失敗を観察する |
楽しく運動を続けているOB、OB会(再会教室)を紹介する |
| (3)社会的説得:やればできると他人から言葉や態度で説得される |
詳細な健康診断に基づき、運動できる機能を備えていることを説明する(太鼓判) |
| (4)生理的・感情的状態の自覚:生理的、感情的な変化を自覚する |
身体機能の向上や恐怖を克服しつつあることを自覚できるように言葉をかける できるようになった時に声をかけ、自らの変化に気付く機会を作る |
|
| (拡大画像:85KB) |
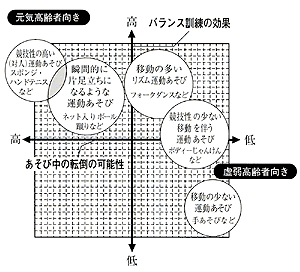 |
図1 バランス訓練の効果と運動あそび中の転倒
(上岡、岡田、武藤、2001)
ただし、転倒を回避するための外出の自粛や教室の感想についての面接は、2000年6月から2001年3月までの上記の条件に該当する60名を対象とした。
調査項目は、転倒予防教室開始時および終了時に、気分感情、転倒予防自己効力感を自記式質問紙にて収集し、移動・バランス機能として、健脚度(10m全力歩行時間、最大一歩幅、40cm踏台昇降)、30秒開眼単脚起立時間を測定した。また、開始時に既往歴、転倒歴(過去1年間に1回以上の転倒経験の有無、および転倒時の状況)を、終了時に、転倒を回避するために自粛している動作、転倒予防教室に関する感想や出来事などについて、半構造的質問により聴取した。
気分・感情の測定は、McNairら(1992)が開発したProfile of Mood States(POMS)10)を翻訳、開発した日本版POMS11)を用いた。POMSはそのときの個人の気分・感情状態を、緊張−不安、抑うつ−落ち込み、怒り−敵意、活気、疲労、混乱の6領域から測定する自記式質問票で、旧版は信頼性、妥当性が確認されている12)。それをもとに改訂された新版の質問票を用いた。各領域の標準化得点だけでなく、総合得点として、活気以外の項目を加算し、活気だけを減算するtotal mood disturbance(TMD)も採用した。
10m全力歩行時間は、前後2mを含めた14mを最大努力で速く歩いた時の時間を測定した。最大一歩幅は、両脚を揃えた状態から片方の脚を踏み出し、反対側の脚をその横に揃える時の最大距離を測定し、下肢長で割った補正値を用いた。40cm踏台昇降は、高さ40cmのステップ台を手すりなしで確実に昇り降りができるかどうかを、可能・困難(膝に手をあてたり、着地でふらつく)・不可能の3段階で判定した14)。バランス機能は開眼30秒開眼単脚起立時間を用い、起立が保てない場合は両脚接地までの時間を測定した。なお、これらの移動・バランス能力指標の信頼性は確認されている14、15)。
各変数の二時点の比較は対応のあるt検定を行った。
|