|
●報告
地域スポーツ行事の変遷と社会背景との関連について
―長野県北御牧村スポーツ行事を事例として―
Relationship between the Changes of Regional Sport Festivals
and the Social Background
―An Example of sport festivals in Kitamimaki Village in Nagano Prefecture―
| 小林 佳澄a |
上岡 洋晴a |
岡田 真平a |
武藤 芳照b |
| Kasumi KOBAYASHIa |
Hiroharu KAMIOKAa |
Shinpei OKADAa |
Yoshiteru MUTOHb |
a 身体教育医学研究所
b 東京大学大学院身体教育学講座
a Laboratory of Physical Education and Medicine
b Department of Physical and Health Education, Graduate School of Education, The University of Tokyo
Abstract
The connection of the changes of social background with sport festivals in Kitamimaki village, Nagano Prefecture was examined.
Kitamimaki village, Nagano Prefecture was selected for this study. Data were collected through literatures describing sport festivals in this village and then interviewing people who involved in planning and operation of these events. We asked sixteen middle-aged to aged men and women by phone or by interview how these sport festivals were carried out.
We found that the sport events in Kitamimaki village initially was started as Athletic Game of The Seinenkai. At that time these sport festivals played important roles in education of Japanese through athletics and in training them for the upcoming war. Afterward, these events had opened as one of measures for regional development. Since Japanese have wanted more variable choices in athletic games, people gradually have lost their interest in participating to the sport festival for regional development. The reasons may be; 1) people tend to have few children, 2) elderly population has increased, 3) young people have moved out the village and 4) people in the village have changed a sense of value, however, further analysis will be necessary. On the other hand, new sport festivals which people could learn about health and techniques have been created on the basis of Educational Ministry Guideline. Residents in the village have multiple choices of sport activity and populations who enjoy sport games are increased.
| ●代表著者連絡先: |
〒389−0402 長野県北佐久間郡北御牧村大字布下6−1 |
| |
身体教育医学研究所 小林佳澄 |
| |
TEL/FAX 0268−61−6148 E−mail kobayashiks@mimaki.jp |
| Key Words: |
regional society, social background, localsportactivity, OutdoorGames(Undoukai) |
| |
地域社会、社会背景、地域スポーツ、運動会 |
1. はじめに
都市化、産業化など様々な社会背景の変化に伴って国民のライフスタイルも多様化してきた。これを受け、地域社会も変容をとげている。この現象の1つとして、地域意識の希薄化が顕著となってきたことが挙げられ1)、地域社会は構造的安定性を失いつつあると考えられる(図1)。
また、学校教育現場においては、子どもをめぐる問題が深刻化している。今後は少子・高齢化が一層深刻化することが予想され、住民同士が連帯感を持ちながら、地域社会を再構築することが望まれる。
ところで、国民のスポーツに対するニーズも多様化し、地域社会が媒体となって展開される「地域スポーツ」にも、質・量ともに年々変化が見られる2)。
構造的安定性を失いつつある地域社会を再構築する手段にスポーツを活用するとすれば、地域スポーツ行事の内容の変遷に注目し、それらを明らかにすることが必要である。
図1 社会背景の変化と地域社会(概念図)
そこで本研究は、地域スポーツの中でも特にスポーツ行事に注目し、事例として長野県北御牧村で開催されてきた各種のスポーツ行事の変遷と社会背景との関連について考察することを目的とした。
2. 調査対象地域の特色
本研究は、長野県北御牧村を調査対象とした。当村は、明治22(1889)年4月、市町村制施行により、6つの村が合併して成立した。長野県の東部、小諸市の西に位置し、浅間山をはじめ信州を代表する山々を見渡せ、豊かな自然に恵まれた村である。
平成12年4月1日現在の人口は5,526人であり、高齢者比率は25.3%と高齢化が村にとって大きな問題の1つとなっている。
産業構造は、1965(昭和40)年には、農業従事者が労働人口の69.8%を占める典型的な農村であった。しかし、その比率は全国的には高いものの年々減少し1995(平成7)年には25.6%で、他産業の比率が高くなってきている(図2)。
3. 方法
調査時期は平成12年4月〜11月で、まず、北御牧村の地域スポーツについて、『図説 北御牧村の歴史』3)、『北御牧時報I』4)、『北御牧時報II』5)を資料として文献調査を行った。
次に、これまで北御牧村で行われてきた各種スポーツ行事に深く関わってきた中高年16名(平均年齢56.3歳、32−78歳)に対して、各種スポーツ行事の開催形態、目的、内容について、電話・面接による聞き取り調査を行った。
4. 調査結果
北御牧村における最初の地域スポーツ行事は1915(大正4)年に北御牧村青年会主催によって行われた「青年体育競技会」であった(図3)。この組織は1913(大正2)年11月に発足し、15歳から35歳の男子437名で構成されていた。この組織が結成された背景には、1906(明治39)年の日露戦争終戦後に、国威高揚を国是とした「国、県、郡」一貫の国家的な見地から、青年層を指導する必要性があった。
| (拡大画像:72KB) |
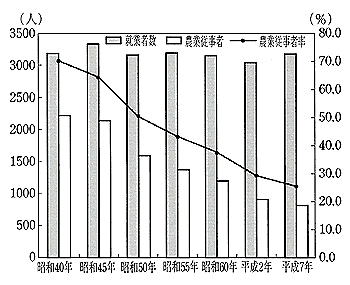 |
図2 北御牧村の産業構造の推移
この青年会の活動内容を見てみると、会員自身の自主的な修養としての活動、村の活性化を目的とした各種の講演会や視察旅行などを実施していた。
この青年会が開催した「青年体育競技会」の主旨は、戦時下、特に会員の体位*の向上であった。その内容は、百米競走、円盤投げなどの陸上競技種目のほか、銃剣術や剣道などの武道も行われていた。これらは、当時生活の基盤となっていた分館**を単位に対抗戦で競われた(表1)。この競技会はその後、戦争の影響を受け続け、1940(昭和15)年には「第1回村民大運動会」に移行された。
この青年会は、1927(昭和3)年には、各分館に置かれた各分団の進歩向上、青年相互の親睦・協調を図るとともに、村の活性化を目的に「北御牧村青年団」として新しく発足した。
1946(昭和21)年以降は、団員同士の親睦を図るため、団員を対象に、「球技大会(野球、排球)」、「籠球大会」、「卓球大会」などが開催された。これらをきっかけに、青年団自体の活動はより活発化した。この活動は分館にも影響を与え、分館内の親善を深めるための野球などのスポーツ行事も開催された。
| (拡大画像:43KB) |
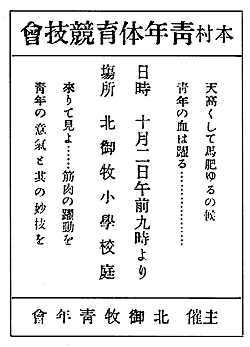 |
図3 『青年体育競技会』の広告
表1 『青年体育競技会』の形態
| 開始時期 |
1915(大正4)年開始 |
| 主催 |
北御牧村青年会 |
| 目的 |
会員の体位向上 |
| 参加対象 |
北御牧村青年会会員 |
| 種目 |
百米競走、円盤投げ |
| 銃剣術、剣道 |
| 競技形態 |
分館対抗※ (※公民館を核とする村内各地のこと) |
|
これ以降のスポーツ行事は、青年団と北御牧体育協会、公民館、北御牧村体育指導員会などの共催で開かれ、参加対象の幅も広げられた。このため、参加形態にも変化が見られるようになった。多世代に渡る選手によって構成された分館単位の参加に加え、1963(昭和38)年以降は、同じ職場で勤務する者同士のチームの参加も多くなってきた。
当村のスポーツ行事に多大な影響を与えてきた北御牧村青年団であったが、1991(平成3)年に、若者の村外流出により団員数の減少が主な原因となって解散されている。
一方、1962(昭和37)年以降の高度経済成長期後、国民の余暇時間の増大や生活水準の向上、また健康ブームが高まる中、国民のスポーツ活動に対するニーズが多様化してきた。
そこで国では、スポーツ振興のため「社会体育指導者派遣事業」を開始した。この事業は市町村教育委員会の社会体育指導体制の整備・充実を図ることを目的に展開された。主な内容としては、地方自治体が実施する各種スポーツ行事大会振興事業や、スポーツ施設の整備及び学校体育施設の開放に対する補助、またスポーツ指導者の養成などである。実際には、市町村教育委員会任用の社会教育主事(市町村スポーツ主事)が配置されていない市町村から、その派遣の要請があった場合、都道府県教育委員会から一定の期間に派遣される6)。
表2 北御牧村におけるスポーツ教室(1980年代)
| 対象 |
主な目的 |
教室の種目 |
| 初心者(清壮年) |
技術の習得 |
硬式テニス・軟式テニス・卓球・ゴルフ・ジャズダンス・バドミントン・社交ダンス・太極拳 |
| 高齢者 |
技術の習得 |
ゲートボール |
| 小学生 |
体力・健康増進 |
少年野球・少年少女軟式テニス・剣道・空手・ミニバレーボール・ミニバスケットボール |
| 清壮車 |
高度な技術の習得 |
ジョギング・体力づくり |
| 中・上級者(各年代) |
バレーボールリーダー・ゲートボール・ソフトボールリーダー |
|
この国家的事業を受け、1980(昭和55)年、長野県教育委員会より、北御牧村教育委員会に社会教育主事が派遣された。これをきっかけとして、当村では体育・スポーツ活動の日常化を目指し、自主的なスポーツ集団の育成、その指導者の養成、さらにスポーツ行事の企画・運営などの見直しがされた。当時は早起き野球リーグや男女バレーボールリーグなど、いくつかのスポーツ活動が一部で意欲的に行われていたが、今後はこれらに参加していない村民が身近にスポーツ活動が実施できる環境の整備についても力が注がれた。具体的にはテニスやゲートボールなどの初心者や高齢者向けの教室も実施され、各教室終了後には大会が開催された(表2)。
また、この中のひとつであるジョギング教室は、村民の生活の中にスポーツ活動を浸透させるという点で、他のスポーツ行事と性格を異にしている。この教室終了後に、村教育委員会は村内に11箇所のジョギングコースを設置した。コース内には、スタート地点からの距離、方向が記載された標識が100〜200メートル間隔で設置された。また同時に「世界一周走ろう運動」も行われた。これは、カードが配布され、1日2km以上ジョギングを実施したら印をし、規定された日数を達成できた者には記念メダルが贈られるというものであった。村民は、これらを利用しながら講師のアドバイスをもとに、自分のライフスタイルや体調に合わせて、健康づくりに取り組んだ。
この社会教育主事派遣事業をきっかけに、スポーツ人口の拡大が図られた。
* 体位:体格・健康の程度。(広辞苑、岩波書店、1988)
**分館:公民館を核とする村内各地区のこと。
※地域スポーツ:本研究では、地域社会が媒体となって展開されるスポーツ行事を地域スポーツとした。
5. 考察
調査の結果から、北御牧村において開催されてきたスポーツ行事は1945(昭和20)年のポツダム宣言受諾、そして1962(昭和37)年の高度経済成長期を境として大きく3つに区分することができると考えられる(表3)。
表3 北御牧村におけるスポーツ行事の変遷
| (拡大画像:115KB) |
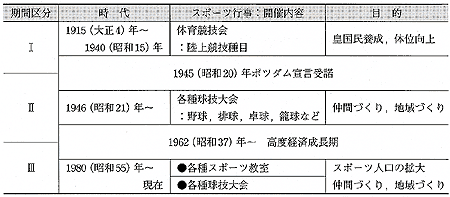 |
第I期に行われていたスポーツ行事は、戦時中により体位の向上を目的とし、皇国民養成のための重要な手段の1つとして開催されていたと考えられる。その内容も、個人的な種目が中心となっており、分館を単位に競われてはいるものの、個人の体力・運動能力が評価されるものであった。
これに対し、ポツダム宣言受諾後の第II期以降に開催されてきたスポーツ行事は、仲間づくり、地域づくりを目的に開催されたと考えられる。その内容にも変化が見られ、野球やバレーボールなど集団的スポーツ種目が取り入れられている。これらのスポーツ行事に参加する中で、集合意識、住民の地域意識は高まっていったと考えられる。
また、高度経済成長期後の第III期以降では、国民のスポーツ活動が多様化していく中で、従来の地域づくりを目的に開催されたものに加え、さらにスポーツ人口の拡大を目的にスポーツ行事が開催されるようになった。1983(昭和58)年以降、国民の生活の力点はレジャーおよび余暇生活がトップとなっている(図4)7)。国民の余暇生活に対する意識が変化し、余暇生活の利用の仕方も多様化してきたと考えられる。このような傾向が当村でも見られ、1940(昭和15)年から現在でも当村で開催されている伝統ある「村民大運動会」は、1986(昭和61)年以降各分館において人員不足の問題が深刻化した8)。この一方で、社会教育主事派遣事業をきっかけに、健康づくり、初心者や高齢者向けに開催されたスポーツ行事への関心度は高く、スポーツ人口は拡大したと考えられる。
6. まとめ
今回の研究により、北御牧村のスポーツ行事は、北御牧村青年会の「青年体育競技会」がその起源であったことが明らかになった。当初は戦争に備え皇国民養成のための重要な手段の1つとして始められたが、しだいに地域づくりの手段の1つとして開催されるようになった。その後、国民のスポーツ活動に対するニーズが多様化する中で、地域づくりを目的としたスポーツ行事への参加者は年々減少してきている。その主な要因として、少子・高齢化の進展、若者の村外流出、村民の価値観の変化などが考えられるが、こうした分析にはさらなる検討が必要である。この一方で、文部省の施策を受け、村民のニーズに対応した「健康づくり、技術習得」を目的としたスポーツ行事の開催により、村民のスポーツ活動の選択肢が増え、スポーツ人口の拡大が図られたと考えられる。
今後は、村民のスポーツ行事への参加状況、スポーツ習慣などを明らかにし、地域社会を再構築する手段としての地域スポーツのあり方について検討していくことが課題となった(図5)。
●附記
本研究は、次の事業助成の一部を受けて行われた。
(財)日本財団2000年度社会福祉事業助成「ケアポートを核とした元気むらづくり事業」、組織:(福)みまき福祉会 身体教育医学研究所
また、平成13(2001)年第52回日本体育学会(札幌)において「地域スポーツ行事の変遷と社会背景との関連について―長野県北御牧村スポーツ行事を事例として―」の演題で口頭発表を行った。
| (拡大画像:20KB) |
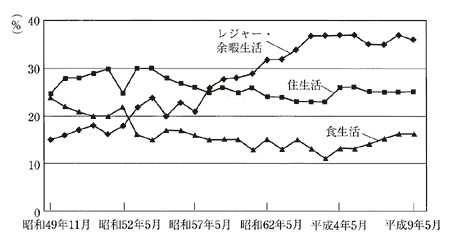 |
図4 国民の生活の力点
※少数回答である耐久消費財・衣生活については削除した。
出典:総理府広報室「国民生活に関する世論調査」平成9年5月
図5 三世代交流ゲートボール大会(平成12年)
●参考文献
1)長谷川昭彦:地域の社会学, 日本経済評論社, 1993.
2)厨義弘, 大谷義博:地域スポーツの創造と展開, 大修館, 1990.
3)北御牧村村誌編集委員会編:図説北御牧村の歴史, 北御牧村, 1989.
4)北御牧村教育委員会編:北御牧時報縮刷版I, 北御牧村, 1987.
5)北御牧村教育委員会編:北御牧時報縮刷版II, 北御牧村, 1987.
6)総務庁行政監察局編:スポーツ振興対策の現状と問題点, 総務庁行政監察局, 1990.
7)余暇開発センター編:レジャー白書2000, 余暇開発センター, 2000.
8)小林佳澄, 上岡洋晴, 岡田真平他:地域スポーツ行事の変遷と社会背景との関連について―長野県北御牧村運動会を事例として―, 身体教育医学研究第2巻1号, 21−28, 2001.
9)松田之利, 西村貢(編):地域学への招待, 世界思想社, 1999.
|