|
3. 結果
測定項目に欠損値がある者や杖なしで歩行ができない者を分析から除外し、468名(男性117名、年齢72.4±7.7歳;女性351名、年齢69.2±6.5歳)の測定値を本研究の分析対象とした。
1)性、年代別の移動能力及びバランス能力
表1と表2に性、年齢別の測定結果の基本統計を示した。男性の場合、年齢の増加に従って、10m全力歩行時間の平均値が60〜64歳の4.9±1.4秒から75〜79歳代の6.6±1.9秒まで、さらにに85歳以上では8.9±2.8秒までに増加した。下肢長補正後最大1歩幅の平均値は、60〜64歳の143.9±15.3%から85歳以上の107.3±15.6%まで減少した。
女性では10m全力歩行時間の平均値が60〜64歳代の5.1±1.3秒から85歳以上の9.8±2.5秒へと増加した。下肢長調整後最大1歩幅もそれぞれ136.4±18.2%から94.0±26.5%まで減少した。集団の平均値からみると、男女とも加齢による変化をよく反映していた。
40cm踏台昇降では、「楽に昇降できる」の人数が、男性60〜64歳代の100%から75〜79歳代の63.2%まで低下し、女性も同様に92%から27.7%まで低下した。
つぎ足歩行では、「確実にできる」だった人数が、男性60〜64歳の87.5%から、85〜89歳の33.3%まで、女性も74.5%から0%までに大きく減少した。
さらに、男女別各測定項目の結果と年齢、BMIの相関係数を見ると、男女ともに4つの測定項目すべてが年齢とやや強い有意な相関(P<0.01)があった。
男性において、各測定項目とBMIとの間には、有意な相関が見られなかったが、女性では、健脚度とBMIに弱い有意な相関が見られた。また、男女とも、年齢とBMIとの間には有意な相関は見られなかった。
表1 男性年代別にみた移動能力(健脚度)とバランス能力
| 年齢(歳) |
60〜64 |
65〜69 |
70〜74 |
75〜79 |
80〜84 |
85〜89 |
年齢との相関 |
BMIとの相関 |
| 人数 |
16 |
30 |
29 |
19 |
14 |
9 |
| 10m全力歩行(秒) |
4.8±1.4 |
5.7±1.1 |
5.8±1.3 |
6.6±1.9 |
6.42±1.64 |
8.9±2.8 |
***
r=0.435 |
NS
r=0.090 |
| 最大1歩幅 |
| 補正前 |
122.1±14.6 |
117.1±14.0 |
107.2±15.0 |
100.5±22.0 |
94.5±21.0 |
86.9±20.8 |
*** |
NS |
| 下肢長補正後 |
143.9±15.3 |
136.7±16.0 |
124.2±17.0 |
116.0±26.0 |
111.0±25.0 |
107.3±15.6 |
r=−0.568 |
r=−0.138 |
| 40cm踏台昇降 |
| 1 楽に昇降できた |
16(100%) |
29(96.7%) |
22(75.9%) |
12(63.2%) |
7(50.0%) |
3(33.3%) |
*** |
NS |
| 2 何とか昇降できた |
0(0.0%) |
0(0.0%) |
4(13.8%) |
6(31.6%) |
5(35.7%) |
4(44.4%) |
r=0.485 |
r=0.023 |
| 3 昇降できなかった |
0(0.0%) |
1(3.3%) |
3(10.3%) |
1(5.2%) |
2(14.3%) |
2(22.3%) |
|
|
| つぎ足歩行 |
| 1 確実にできること |
14(87.5%) |
18(60.6%) |
14(48.3%) |
6(31.6%) |
7(50.0%) |
3(33.3%) |
** |
NS |
| 2 途中よろける |
2(12.5%) |
12(40.0%) |
13(44.8%) |
9(47.4%) |
4(28.6%) |
3(33.3%) |
r=0360 |
r=0.070 |
| 3 つぎ足姿勢がとれない |
0(0.0%) |
0(0.0%) |
2(6.9%) |
4(21.0%) |
3(21.4%) |
3(33.3%) |
|
|
| [注]** p<0.01 *** P<0.001 NS 有意な相関なし |
|
表2 女性年代別にみた移動能力(健脚度)とバランス能力
| 年齢(歳) |
60〜64 |
65〜69 |
70〜74 |
75〜79 |
80〜84 |
85〜89 |
年齢との相関 |
BMIとの相関 |
| 人数 |
102 |
88 |
87 |
47 |
22 |
5 |
| 10m全力歩行(秒) |
5.1±1.3 |
6.14±1.6 |
6.6±1.7 |
7.5±2.1 |
8.1±2.3 |
9.8±2.5 |
***
r=0.524 |
*
r=0.135 |
| 最大1歩幅 |
| 補正前 |
108.0±13.4 |
100.5±12.3 |
93.8±14.2 |
87.1±13.9 |
83.0±17.1 |
71.3±18.7 |
*** |
** |
| 下肢長補正後 |
136.4±17.8 |
126.3±15.1 |
119.9±18.3 |
111±17.7 |
104.3±19.2 |
94.0±26.5 |
r=−0.547 |
r=−0.163 |
| 40cm踏台昇降 |
| 1 楽に昇降できた |
92(90.2%) |
61(69.3%) |
34(39.1%) |
13(27.7%) |
6(27.3%) |
0(0.0%) |
*** |
** |
| 2 何とか昇降できた |
7(6.9%) |
21(23.9%) |
35(40.2%) |
20(42.6%) |
7(42.6%) |
1(20.0%) |
r=0.519 |
r=0.178 |
| 3 昇降できなかった |
3(2.9%) |
6(6.8%) |
18(20.7%) |
14(29.7%) |
9(29.7%) |
4(80.0%) |
|
|
| つぎ足歩行 |
| 1 確実にできること |
76(74.5%) |
53(60.2%) |
26(29.9%) |
10(21.3%) |
3(13.6%) |
0(0.0%) |
*** |
NS |
| 2 途中よろける |
25(24.5%) |
31(35.2%) |
46(52.9%) |
28(59.6%) |
13(59.1%) |
1(20.0%) |
r=0.495 |
r=0.058 |
| 3 つぎ足姿勢がとれない |
1(1.0%) |
4(4.6%) |
15(17.2%) |
9(19.1%) |
6(27.3%) |
4(80.0%) |
|
|
| [注]*p <0.05 **p <0.01 *** p<0.001 NS 有意な相関なし |
|
表3 男女別測定対象の基本属性の集計
| 基本属性 |
男 |
女 |
| 職業 |
高級管理職 |
度数 |
33 |
52 |
| % |
28.7 |
15.3 |
| 一般管理職 |
度数 |
23 |
53 |
| % |
20 |
15.6 |
| エンジニア |
度数 |
22 |
42 |
| % |
19.1 |
12.3 |
| 医者・弁護士・教員 |
度数 |
8 |
56 |
| % |
7 |
16.5 |
| 企業労働者 |
度数 |
23 |
71 |
| % |
20 |
20.9 |
| サービス職 |
度数 |
5 |
28 |
| % |
4.3 |
8.2 |
| 無職 |
度数 |
1 |
38 |
| % |
0.9 |
11.2 |
| 合計 |
度数 |
115 |
340 |
| % |
100 |
100 |
| 家族構成 |
1人 |
度数 |
4 |
33 |
| % |
3.5 |
9.8 |
| 夫妻のみ |
度数 |
43 |
100 |
| % |
37.4 |
29.7 |
| 子と同居 |
度数 |
43 |
97 |
| % |
37.4 |
28.8 |
| 子、孫と同居 |
度数 |
25 |
107 |
| % |
21.7 |
31.7 |
| 合計 |
度数 |
115 |
337 |
| % |
100 |
100 |
| 月収 |
300元以下 |
度数 |
11 |
59 |
| % |
9.6 |
17.5 |
| 301〜1000元 |
度数 |
81 |
218 |
| % |
71.1 |
64.7 |
| 1001〜1700元 |
度数 |
17 |
49 |
| % |
14.9 |
14.5 |
| 1701元以上 |
度数 |
5 |
11 |
| % |
4.4 |
3.3 |
| 合計 |
度数 |
114 |
337 |
| % |
100 |
100 |
| 持病 |
なし |
度数 |
3 |
16 |
| % |
2.6 |
4.6 |
| 運動器と骨 |
度数 |
16 |
80 |
| % |
13.7 |
22.8 |
| 循環器 |
度数 |
52 |
124 |
| % |
44.4 |
35.3 |
| 糖尿病 |
度数 |
1 |
10 |
| % |
0.9 |
2.8 |
| その他 |
度数 |
13 |
34 |
| % |
11.1 |
9.7 |
| 運動器&循環器 |
度数 |
32 |
87 |
| % |
27.3 |
24.8 |
| 合計 |
度数 |
117 |
351 |
| % |
100 |
100 |
|
2)測定対象の基本属性
測定対象の基本属性調査結果を表3に示す。「退職前の職業」(「以下職業」)を見ると、男性は高級管理職が最も多かった。女性は、企業労働者の割合が高かった。
「家族構成」では、男性は夫妻のみ、子と同居の割合が女性より高かった。女性の場合、1人暮らし、子と孫と三世代同居の割合が高かった。これは女性の平均余命が男性より高いことと、高齢女性は孫の面倒を見るという家族内の役割を担当している北京の社会事情を一部反映していた。
「月収」では、女性は300元以下の低収入の割合が高く、また、男女ともに、301〜1000元の収入の群が最も多く、1701元以上の収入の者は少なかった。
3)移動能力及びバランス能力と各基本属性との関連
表4は移動能力及びバランス能力と職業、月収との関連についてである。
A. 「10m全力歩行」と基本属性
「10m全力歩行」を従属変数に、基本属性4項目を固定因子とした4元配置分散分析の男女別結果である。「職業」、「家族構成」、「月収」、「持病」の「10m全力歩行」に対しての主効果モデルの検定では、男性において「月収」で、各力テゴリーの平均値に有意差(p<0.05)が見られた。女性では、「職業」で有意差(p<0.001)があった。
B. 「下肢長補正後最大1歩幅」と基本属性
「下肢長補正後最大1歩幅」を従属変数としての4元配置の分散分析の結果である。「職業」、「家族構成」、「月収」、「持病」の主効果モデルの検定では、女性において、「職業」で有意差(p<0.001)が見られた。
C. 「40cm踏台昇降」、「つぎ足歩行」と基本属性
「40cm踏台昇降」、「つぎ足歩行」と各基本属性とのKruskal−Wallis分析の結果である。男性では「40cm踏台昇降」、「つぎ足歩行」と各基本属性に有意な関連は見られなかった。女性では、「職業」及び「月収」と「40cm踏台昇降」、「つぎ足歩行」にそれぞれ有意な関連が見られた。職業の「エンジニア」と「医師・弁護士・教員」群は有意に能力が高く、「無職」と「企業労働者」群は有意に能力が低かった。月収の「300元以下」の群は有意に能力が低かった。
男性の「月収」で、一番高い「1701元以上」群は、10m全力歩行の時間が他の群より有意に長かった。
表4 移動能力・バランス能力と職業・月収との関連
| |
男性 |
女性 |
| A. 分散分析の従属変数 |
10m全力歩行(秒) |
| 固定因子 |
平均値 |
標準誤差 |
F値 |
有意確率 |
平均値 |
標準誤差 |
F値 |
有意確率 |
| <職業> |
1.254 |
0.290 |
|
6.927 |
0.000 |
| 高級管理職 |
6.92 |
0.511 |
6.455 |
0.301 |
| 一般管理職 |
6.342 |
0.561 |
6.121 |
0.32 |
| エンジニア |
5.618 |
0.533 |
5.275 |
0.338 |
| 医者・弁護士・教員 |
6.462 |
0.808 |
5.617 |
0.294 |
| 企業労働者 |
6.482 |
0.563 |
6.841 |
0.31 |
| サービス職 |
6.19 |
0.94 |
6.666 |
0.39 |
| 無職 |
7.527 |
0.367 |
| <月収>* |
3.393 |
0.021 |
|
0.679 |
0.566 |
| 300元以下 |
6.596 |
0.686 |
|
|
6.732 |
0.378 |
|
|
| 301〜1000元 |
5.705 |
0.389 |
6.366 |
0.269 |
| 1001〜1700元 |
5.060 |
0.594 |
6.141 |
0.255 |
| 1701元以上 |
7.981 |
0.921 |
6.191 |
0.243 |
| B. 分散分析の従属変数 |
下肢長補正後最大1歩幅(%) |
| 固定因子 |
平均値 |
標準誤差 |
F値 |
有意確率 |
平均値 |
標準誤差 |
F値 |
有意確率 |
| <職業> |
1.843 |
0.112 |
|
6.117 |
0.000 |
| 高級管理職 |
115.595 |
5.997 |
118.600 |
3.140 |
| 一般管理職 |
119.576 |
6.590 |
127.537 |
3.334 |
| エンジニア |
132.337 |
6.264 |
134.438 |
3.518 |
| 医者・弁護士・教員 |
110.230 |
9.488 |
132.358 |
3.064 |
| 企業労働者 |
120.113 |
6.609 |
120.730 |
3.234 |
| サービス職 |
121.42 |
11.044 |
123.717 |
4.064 |
| 無職 |
115.298 |
3.824 |
| <月収> |
0.9000 |
0.444 |
|
0.956 |
0.414 |
| 300元以下 |
116.412 |
8.055 |
|
|
122.357 |
2.819 |
|
|
| 301〜1000元 |
126.147 |
4.565 |
125.227 |
1.818 |
| 1001〜1700元 |
123.023 |
6.976 |
121.538 |
3.149 |
| 1701元以上 |
113.932 |
10.816 |
129.551 |
6.019 |
| C.Kruskal−Wallis検定 |
40cm踏台昇降 |
つぎ足歩行 |
40cm踏台昇降 |
つぎ足歩行 |
| |
H値 |
有意確率 |
H値 |
有意確率 |
H値 |
有意確率 |
H値 |
有意確率 |
| 職業 |
8.372 |
0.137 |
6.416 |
0.268 |
32.506 |
0.000 |
34.988 |
0.000 |
| 月収 |
0.204 |
0.977 |
1.282 |
0.733 |
9.258 |
0.026 |
15.226 |
0.002 |
| [注]10m全力歩行と最大1歩幅は4元配置分散分析。 |
| 40cm踏台昇降とつぎ足歩行はKruskal−Wallis検定。 |
| * 1元は、日本円で約15円である。 |
|
4. 考察
北京の60歳以上の高齢者を対象とする移動能力及びバランス能力の測定は、健脚度(10m全力歩行、最大1歩幅、40cm踏台昇降)とつぎ足歩行のすべての結果において、年齢との有意な関連が見られた。
『老年者の生活の質に関する調査内容と評価基準』6)を参考にすると、本対象者は、低所得者層から高所得者層まで包括しており、一般住民を反映した高いサンプリングだと考えられる。
本研究のように高齢者の職業背景や経済状況と身体機能との関連を検討した報告はほとんど見られない。国家や地域の違い、経済水準によっても、差が生じると考えられるが北京の実態を明らかにすることができた。
北京の男性の月収が最も高い群は、他の収入群より有意に10m全力歩行が遅かった。そこで、男性の月収とBMIとの関連も調べて見ると(図1)、月収の最も高い群はBMIも他の群より高値だった。
したがって、身体教育の視点からすると、北京の収入の高い高齢男性に対して、健康管理、食生活及び運動習慣についての徹底した実態調査、それに基づいた運動・生活指導が必要である。
女性において、退職前の職業としてエンジニア、医師・弁護士・教師の群は、管理職群、企業労働者群及び無職群より、40cm踏台昇降とつぎ足歩行の能力が有意に高かった。また、月収300元以下の低い群は、有意に40cm踏台昇降とつぎ足歩行の能力が低かったが、月収の高い群と中間の群には有意差は見られなかった。ここで、中国の高齢者は以前の職業と現在の収入が繋がっているため、職業と月収との関連を調べた(図2)。女性の無職群、企業労働者群は、月収300元以下の者が多く、これが40cm踏台昇降とつぎ足歩行の能力が低いことに何らかの関係があると考えられる。過去に高級管理職に従事していた群は収入が高いが、エンジニア、医師・弁護士・教員群より40cm踏台昇降とつぎ足歩行が低かった。これは、過去の立ち仕事が少なく、その後も、直立支持の動作が少ないためだと考えられる。
女性において、低収入群は、昇降動作(40cm踏台昇降)及びバランス能力(つぎ足歩行)が低かったが、男性では異なっていた。北京の55歳以上の者を対象として骨量と筋量を調べた研究では、加齢に伴う低下は、女性の方が男性より大きいことを報告7)している。女性の骨は閉経期や老年期の代謝変化(Caの代謝変化)の影響を受けて、骨量が低下し、脊椎の圧迫骨折による変形を起こす8)9)。結果的に下肢の運動機能が低下する可能性が考えられる。つまり、中国では低収入が原因となる不十分な栄養状態は、男性よりも女性に及ぼす影響が大きいと推測される。
| (拡大画像:20KB) |
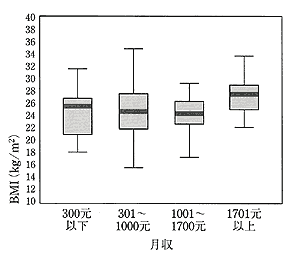 |
図1 男性における月収とBMIとの関連
箱ひげグラフ:箱の下が25%タイル、箱の中の実線が50%タイル、箱の上が75%タイル
5. まとめ
北京の高齢者(60歳以上)を対象とし、移動能力及びバランス能力とその社会特徴を調べた結果、以下のことが明らかになった。
高齢者における移動能力及びバランス能力は、年齢と有意な負の相関があった。さらに年齢を調整しても、高齢者の収入と有意な関連が残った。男性の一番収入の高い群は、10m全力歩行が遅く、BMIが高かった。また、女性の場合、以前の職業とも有意な関連があった。女性の無職群と企業労働者群は、一番収入が低く、40cm踏台昇降とバランス能力も低かった。中国では低収入が原因となる不十分な栄養状態は、男性よりも女性に及ぼす影響が大きいと推測された。
| (拡大画像:26KB) |
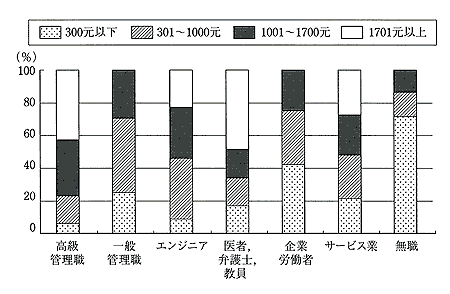 |
図2 女性における職業別の月収
●附記
本研究を行うのにあたり、北京老年スポーツ協会の李士英先生をはじめ多くの先生方や、北京市西城区各住民委員会、住民の方々のご協力をいただきました。心より厚く御礼申し上げます。
●参考文献
1)Zhang Y:中国已踏入老齢社会, 「2000年:中国社会形勢分析与予測」中国社会科学院編, 中国社会科学院出版社
2) Wu H, Meng C, Xiang M: A Longitudinal on Deterioration of physical Function in people Aged Over 55 in Beijing. Chin J Epidemiol 19:5-8, 1998
3) McArdle WD, Katch FI, Katch VL: Exercise physiology-energy, nutrition and human performance, 2nd ed. Lea & Febiger, Philadelphia 1986.
4)上岡洋晴, 岡田真平:健脚度の測定・評価, 武藤芳照ら編「転倒予防教室, 転倒予防への医学的対応」, 日本医事新報社, pp.46−53, 1999
5) Dargent-M. P, Favier F, Grandjean H, et al. Fall-related factors and risk of hip fracture: the EPIDOS prospective study Lancet, 348:145-149, 1996.
6)中華医学会老年医学分会疫学学組:老年者の生活の質に関する調査内容と評価基準, Chin J Geriatr. Oct. p−320, 1996.
7) Chi J, Zhang Y, Li G: Research on Characteristics of Bone Mineral Content, Body Composition and Muscle Force in Old People. J of Beijing University of Physical Education, 20(3):25-30, 1997.
8) Cummings S. :Appendicular bone density and age predict hip fracture in women. JAM, 263:665-668, 1990.
9)白木正孝:骨・運動器の加齢変化と高齢者における骨・運動器疾患の特徴, 折茂肇ら編「新老年学」, 東京大学出版会, pp.629−636, 1999.
|