|
6月24日講習【臨床心理学概論】
講師 工藤剛
資料「青年期の発達」他 作成者 工藤剛
| (拡大画像:71KB) |
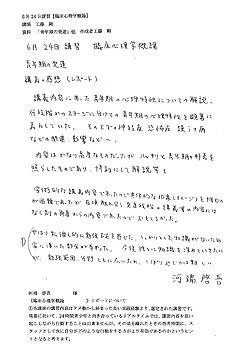 |
河端啓吾様
《臨床心理学概論》リポートについて
(1)当講座の講習内容はタメ塾から始まった長い実践経験より、選定された講習です。現場に於いて、24時間青少年と向き合っているリアルタイムでは、講習内容を思い起こしながら行動することは出来ませんが、その場を離れたときの思考時間に、スタッフとして次に自分がどのような行動をする方がより有効であるのかというヒントとなると考えます。
平成13年7月1日講習【医療】
講師 河合洋
資料 「社会的ひきこもり」著者斎藤環
社会的ひきこもり―終わらない思春期「斎藤環著」を読んでと 河合洋先生の講義―医療を聞いての感想 星野佳美
社会的ひきこもりを読んで
社会的ひきこもりの問題とは、複雑で裾野の広い、なかなか全貌が見渡しにくい問題で、様々な思春期の問題行動に結びつき、不登校、家庭内暴力、自殺企図、対人恐怖、強迫行為など、それぞれが、何らかのかたちで、社会的ひきこもりとともにあらわれてくるという。そして社会的ひきこもりの定義であるが、二十代後半までに問題化し、六ヶ月以上、自宅に引きこもって社会参加をしない状態が持続しており、他の精神障害が第一の原因とは考えにくいもの、であるという。主に思春期の問題であり、思春期心性に深く根ざし、人格発達の途上における一種の未熟さゆえに起こってくる問題と見ることができ、かたくなといってよいほどの無為、引きこもり状態が長期間続くことになると、数ヶ月から数年、長くなると十数年以上長期間にわたることもあるという。経過が長くなると、みかけは無気力で怠けているだけのような状態になるが、そのみかけの下には、深い葛藤や焦燥感が潜んでいることがあるのだが、そのような悪循環の中、予防や治療が十分に可能であるにもかかわらず、その受け皿はほとんどなく、家族が困りきって相談に行く場所としては、とり合えず精神科しかないのが現状であるという。社会の理解も、社会現象や風俗、病理や事件として思春期に関心はあっても、引きこもる思春期としては黙認されたままになっている。統計的には、男性、特に長男に多く、おとなしくてまじめな人が多いという。彼らの生活は昼夜逆転し、個人・家族・社会・という彼らを取り巻くシステムは壊れ、コミュニケーションの欠如が起こり、社会とかかわりを欲しつつも、ひきこもりシステムを強化していくのだと言う。
また医療的な面から言えば、退行や子ども返り、被害関係念慮、抑うつ気分、希死念慮や自殺企図等が絡んでくるし、過食・拒食などに発展することもある。スキゾフレニアや、スチューデント・アパシーと退却神経症、回避性人格障害、境界性人格障害、思春期妄想症、うつ病、分裂病質人格障害、循環性気分障害・等の精神医学の中での位置ずけ・診療が必要になってくる。
こうした中で、今後社会全体に対する社会的ひきこもり現象に付いては、啓蒙活動が必要になってくる。すでに社会現象という規模で発生しつつあるので、それらを広く知らせるために、定義をしっかりとすべきであり、判定のガイドラインを十分に策定し、対策の枠組みを作りやすくしていくべきであるという。そして十分な受け皿も整備していくことが必要である。さらに、社会的ひきこもりという現実を、目前の事実として受け入れ、正確に認識し理解し、ひきこもりのシステムの解除を促進できるように、私たち自身が努力していくことであると思う。
河合先生の講義から「感想」
河合先生の講義からは、とにかく41年間という医者になってからの臨床体験の重みを感じ、またご自分がやってこられた医療の自信のようなものが感じられ、とても勉強になった。まず診察やカウンセリングを行うときは、沈黙に耐えられない人や、対面の緊張から、追いつめられたり、攻撃的だったり、錯乱状態の人もいるが、診察室の椅子の座り方からも工夫があるという。診察室に入所する時から、治療が始まっているという。そのため先生は、路上やポスト前や駅の階段などの人間観察をしたりして、日常の光景観察にこだわりがあり、とても面白いという。
また、医学は物理学や植物学からスタートし、光のスピードやニュートンの法則などの話しから、日本の歴史であるオランダ医学の解剖学、内科外科の近代医学への発展したこと、それからデカルトの哲学的な話まで広がった。われ思うゆえにわれあり、という心身二元論があり、人間の病気には心の病気と体の病気とがあり、そして人間のあらゆる行動には意味があるという。そして抵抗力がどのくらいあるかという免疫力によって、病気になるかならないか決まってくるという。そして、愛されている人ほど病気に対する免疫力が高いというお話があり、人間の未知なる不思議さを実感した。ストレスなど胃潰瘍や十二指腸かい炎など、環境によりまた個人差にもよって生じてくるという。信じる人は救われるといわれるように、自分のことを、信じられる人は強いという。そしてまた、鉄のよろいを取った自分のことを正直に語れる人や、あらいざらい語れる人は、自己認識があり、自分自身を目覚めさせ自覚していくことができるという。そして自分を支えていけるわけである。人間には多様性があるというのだ。
このような話から、まず自分自身を信じ、自分自身を目覚めさせ、また支えていける力を養いたいと思う。そして、医療的な治療以外で、生活の中の臨床的なことに目を向け少しでも援助していけることを見つけていけたらと思う。
平成13年HRリーダー2級養成講座
リポート返却に際して
受講生の皆様から提出されたリポートは、実践時にどのように役立つのかという観点から添削させていただきますので、ご了承の上、お読み下さい。尚、添削に関するご意見、ご質問などは、12月2日の終了式に意見交換させていただきます。
星野佳美様
《医療》リポートについて
(1)2、3年前まではひきこもり状況にある青少年の問題は、恥ずべきもの、一家庭の問題として片付けられていました。最近ようやく社会的問題としての認識が芽生えつつあります。しかし、ご指摘のように、正確な認識、理解、ひきこもりの対処法など、課題は山積しています。当センターでも様々な角度からこの問題に取り組んでゆきたいと考えています。
平成13年7月1日講習【保健概論】
講師 小林啓子
資料「精神保健概論」「精神保健福祉士の基礎知識」作成者 小林啓子
リポート課題「心に悩みを持つ相談者との係わり方自分なりに考えてください」
今回の課題は「心に悩みをもつ相談者との関わり方」ということで、講義を拝見しながら考えていたのですが、一言でそういっても色んな状況とアプローチの仕方があるものだなあと改めて感じました。今回の講師の小林さんは、保健婦や精神保健福祉士の立場として、保健という視点から相談者との関わりをもってらっしゃいます。対象者の幅も広いですし、相談の内容も多種多様です。これが臨床心理士や精神化医だったら、相談の内容もアプローチの仕方もまたそれぞれちがってくるでしょう。関わり方として、どの立場が一番というのはないというのも、だいたいわかってきました。保健の立場からうまく行く場合もあれば、カウンセリングがピッタリあう人もいる。同じ虐待でもいろんなケースがあるわけですし。だから、まずお互いの特性を認め合って、横の連携を感じていることが大事でしょう。変な気負いをもたないこと、そうしたうえで、自分の関わり方はどういう関わり方なんだろうと考えてみました。
自分の理想としては、あまり相手と距離をつくりたくないです。相談する側される側の関係というのをあやふやにしたいと言う意味でです。しかし、あくまでも、他人として近いところにいたいです。つまり、子供や相談者が木の苗だとします。そうすると、倒れそうだからと言って添え木になるのでなく、薬や肥料をただ与えるのではなく、その木が感じれる近くで立っていたいです。それが、同じような木なのか人なのか、邪魔な雑草なのかはわからないけど、そうしてその存在を感じながら自分の力で根をはり育っていく感じ。それが、自分の中での理想です。ただ、今の段階では本当にただの理想だろうなというのもなんとなくかんじています。自分の力で立てないから相談にくるわけですし。だから、重要なことは、まず今の状況から抜け出すこと。いきなり大きく変化できなくても、すこしづつでも変わっていくことが重要です。そうして、少しづつ糸のからまりをたぐっていきながら、前にすすんでいくということです。そのためには、場合によっては危機介入をして、違った環境を作る必要性もあるでしょう。ただ、全て手取り足取りというのは、少し違う気がします。結局、悩みや苦しみは当人にしかわからないことです。ですから、どこかへ導く為のわかったふりや、共感するふりはしたくないのです。本人がのり越えていく為に、なんとなく近くにいてなんとなくサポートしたりできる立場というのを目指したいと思います。また、そのための信頼関係作りも必要だと思います。相手の気持ちをわかろうと努力すること、自分という人間をわかってもらうこと。
それと同時に相談者と家族との関係も大事だと思います。今回の小林さんの講義でも、それは感じました。子供の起こす問題と親の影響の関係であったり、家庭環境による問題であったり、家族との関係は無視できないものです。実際私の経験でも、家族で問題にとりくんできたところは、子供達にも敏感に変化が見られました。ですから、家族ともコミュニケーションをとりながら、いっしょに問題を考えていくことが重要だと思います。家族の愛情を感じてこそ、私達他人のやれることも広がっていくでしょうし、その逆もあるでしょう。当たり前ですが、私はまだ自信がもてる、自分なりの関わりをみいだすことができていません。うわべのリアクションや発言に惑わされずに、そこの奥にあるものを読みとれるように、いろいろな体験をして自分なりの関わりを見出せたらと思います。
平成13年HRリーダー2級養成講座
リポート返却に際して
受講生の皆様から提出されたリポートは、実践時にどのように役立つのかという観点から添削させていただきますので、ご了承の上、お読み下さい。尚、添削に関するご意見、ご質問などは、12月2日の終了式に意見交換させていただきます。
大嶺繁徳様
《精神保健概論》リポートについて
(1)当センターは、おおむね家族関係が限界に達した人々が利用する施設ですので、在籍生には、自分の家族が客観的に見えるようになるまでは、あまり家族にはこだわらない方針を取っています。しかし、問題は多々残ります。子供が変わっても親が変われない、センターを卒業した後は、いずれにせよ家族関係は復活する。そのような問題をセンター在籍中に解決できれば良いのですが、現実的には、家族までのケアが出来ていません。大きな課題です。
|