|
三、生蝋と晒蝋の生産
生産は、蝋搾り小屋で行われた。ハゼノキの実を小屋の一角にある「こなし場」に広げて、ブドウの房状の実を「ブリコ」と呼ばれる農具で叩き、粒だけにする。粒のとれた房の茎は、「ボサ」とよばれ、竈(かまど)のたき付けにして活用した。粒は、土間に設けられた「ダイガラウス」に移す。足を踏み込んで杵を上げ、足を離して臼に杵を落下させる動作を繰り返した。臼内部は、種と繊維の束が粉になった状態となる。それを「ケンド」でふるって種と粉により分ける。種は入り釜で入ってさらに石臼でひいて粉にし、搾り機に入れて蝋を搾ったが、これは種に含まれる蝋の質が落ちるために、粉と分けて搾った。
種をより分けた粉は「セイロ」で蒸し、「立木式蝋搾り機」で搾る。搾り機の中央に設置してある「カナバチ」にシュロのネットを敷き詰め、蒸したハゼノキの粉を麻布からシュロの内側に入れて「ショウトイシ」を載せてさらにその上に「オオヌキ」を載せ、立木とオオヌキの隙間に「ヤ」を差し込む。両側からお寺の鐘つきの要領で「ヤ」の頭を「シュモク」で突き、「ヤ」を進ませることで、「オオヌキ」を押し下げ、「ショウトイシ」をプレスした。蝋は、「カナバチ」下の穴からゆっくりと落ち、それを「テツナベ」に受ける。「テツナベ」から小皿の「ロウザラ」に小分けして成形し、餅の形となった生蝋を袋(カマス)に詰めて出荷した。
生蝋は、煮とかしてアクを入れ、冷水に落として細かい小片にする。それを「蝋花(ろうばな)」とよび、「ロウブタ」という木箱に薄く広げて太陽にさらして漂白した。融点は五二度前後のため、夏などは箱内の蝋花が溶け出すおそれがあり、桶に水を入れて首から吊り、わらでつくった「ミズハケ」で水を含ませ、箱内の蝋花に水を打って冷却した。真夏は三十分に一回の割合で水打ちを行った。
木箱に入れて太陽に晒す作業は、一週間から二週間かけて行い、晒し終わるとまた「蝋花」を集めて大釜で煮詰め、冷水に落として再び「蝋花」にし天日干しにする。それを二行程実施。
最後(三度目)に「蝋花」を大釜で煮溶かし、直方体などに整形した後木箱に詰めて、関西や海外へ出荷、輸出した。
それ以前は、生蝋を大きな鉋「ロウガンナ」で削っており、日光に晒すための小片に加工するには、長時間を要した。この作業は家内手工業的であったが、生蝋を煮溶かして冷水に落とし、一瞬のうちに大量の小片にすることに着眼し、成功してからは、本格的な工業化となった。
上方流曝蝋場の図(『農家益』」)
晒蝋ができるまで(鈴木光代・画)
| (拡大画面:303KB) |
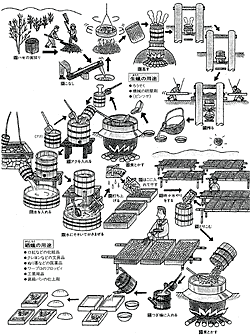 |
明治十年(一八七八)には、内ノ子村(昭和三〇年合併以前の内子町の名称)での蝋生産が一八〇・二一キログラムで三〇、三五〇円の生産額。村全体の移出総額は、三、三六五六円五十銭であったため、九〇パーセントは蝋生産で占められていた。
この製法を「伊予式蝋花箱晒法(いよしきろうばなはこざらしほう)」といった。
この製法による、品質は次の実績から評価がうかがえる。
明治二十七年(一八九四)パリ万博、シカゴ万博ともに賞状を受ける。明治二十八年(一八九五)第四回内国勧業博覧会で「有効一等賞」、明治三十三年(一九〇〇)パリ万博で三位銅メダルを受けた。隆盛を極めた明治三十九年(一九〇六)は、喜多郡(内子町を含む近隣五か町村)の晒蝋生産量が約七八八トンで、このうち内子町が約五四八トンで六九パーセントを占め、全国の輸出晒蝋の八分の一を内子町が占めていた。
内子町では明治時代から大正八年ないし十二年まで、この製法による晒し蝋生産が続き、十二年を最後に、町内の資本家たちは生糸生産にシフトし、晒し蝋生産は終焉を迎えた。
|