|
4. 自動車の点検・整備
(1)取組のポイント
○ドライバーや整備員に対する、整備に関連する教育や情報の提供
○点検・整備計画に基づく着実な実施と点検・整備結果の記録
○車両の状態の把握による迅速な点検・整備の実施
○車両の使用状況に合わせ環境に配慮した独自の点検・整備
自動車走行に伴うCO2や大気汚染物質の排出を適正な状況に保つためには、法定点検および整備の実施が不可欠ですが、それに加えて、車両の使用状況等を見ながら、適切な点検・整備を自主的に進めることが必要です。
そのためには、まず、点検・整備責任者の任命、ドライバーへの教育や情報の提供、点検・整備結果の把握などの体制を整えます。また、整備の実施時には、日常から車両の状況を把握し、それを反映させる必要があります。さらに、車両の使用状況によっては、会社として独自の点検・整備基準(走行距離、点検期間など)を設けて点検・整備を進めてください。
■ 点検・整備について
点検とは、車両やその付属する装置や部品の現在の状態及び次回の点検までの状態が保安基準に適合するかどうかを判断することをいいます。
点検には、法定点検と自主点検があり、法定点検には道路運送車両法で規定する日常点検と定期点検の2種類があります。また自主点検とは、随時必要に応じて行う点検です。
整備とは、保安基準に適合させるために、また不具合の発生を予防するために行う、修理、調整、部品交換等をいいます。
(2)チェック項目の解説と関連資料
(1)点検・整備のための実施体制
チェック項目
| (拡大画面:20KB) |
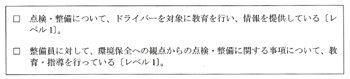 |
解説
適切な時期に、適切な個所の点検・整備を行うためにはドライバーの協力が必要です。このため、ドライバーに対し日ごろの乗務のなかで、排ガスや燃費、エアコン、騒音等について異常の見分け方など点検・整備に結びつく事項についての教育や情報提供が欠かせません。
また、整備員に対しては、環境保全の観点から特に留意すべき点検・整備箇所や具体的な整備に関する事項について教育・指導が必要です。
燃費の向上や排気ガスの汚れの抑制、エンジン音や走行音の低減につながる点検・整備の主な内容として、次の事項があげられます。
・タイヤの空気圧・偏摩耗の点検
・エア・クリーナーの目詰まりがないかどうか
・ファンベルト、冷却水の状態を確認する
・点火プラグの汚れ、ギャップを点検
・エンジンオイルの量と汚れの確認
・排気ガスの色の異常の有無を確かめる
・ハンドルの重さや取られが無いかを確かめる
・クラッチに滑りが無いかを確かめる
・ブレーキの引きずりが無いことを確かめる
・不必要な物の積載を排除する
(2)車両の状態に基づく適切な点検・整備
チェック項目
| (拡大画面:44KB) |
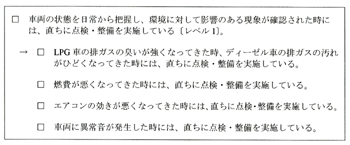 |
解説
ここで取り上げた事項は、環境に対して影響があるため、日常の運行に際して異常に気付いた場合には速やかに点検・整備を実施する必要があります。
LPG車の排気ガスの臭いが強くなったり、ディーゼル車の排気ガスの汚れがひどくなる原因は、燃料の異常な燃焼にあります。その場合、LPG車ではCOやHCの増加が、ディーゼル車では黒煙の増加が問題となります。
燃費の悪化の原因は、原動機や走行装置など様々な箇所にあると考えられます。その場合、燃料消費量やCO2排出量の増加が問題となります。
エアコンの効きが悪化する原因は、主にエアコンガスの漏れが考えられます。その場合、フロンガスの影響による地球温暖化が問題となります。
排気音やエンジン音、走行音などの車両の走行に伴う騒音も環境問題のひとつです。通常とは異なる音がする場合にはすぐに対処することが重要です。
日常の乗務等の中で車両の異常について記録し、点検・整備担当者に報告する体制等を整備しておくことが必要になります。
関連資料
a. 黒煙対策の実施
点検・整備に関連して、黒煙・PM対策については大変重要な課題です。使用過程車に対する排出ガス規制の基準は、表の通りです。
使用過程車に対する黒煙の規制
| 規制値等 |
対象自動車 バス |
適用時期 |
| 40% |
平成5年規制に適合 |
H5.10.1 |
| 40% |
平成6年規制に適合 |
H6.10.1 |
| 25% |
平成9年規制に適合 |
H9.10.1 |
| 25% |
平成10年規制に適合 |
H10.10.1 |
| 25% |
平成14年規制に適合 |
H14.10.1 |
| 25% |
平成15年規制に適合 |
H15.10.1 |
| 25% |
平成16年規制に適合 |
H16.10.1 |
|
|
| 資料:国土交通省自動車交通局 |
b. 黒煙の測定
黒煙の測定には、テスターを使用する方法と、簡易測定としてチャート紙を使用する方法があります。チャート紙を使用したチェックは、日常点検でおこなうことが望まれます。
テスターを使用したチェックは、車検時以外にも、定期的に行うことが望まれます。
事業者の中には、3ヶ月点検時に必ずテスターを使用した黒煙の測定を実施し、測定値を整備記録簿に記入しているところもあります。
また、東京や大阪では、自治体の協力により、年に1回、ディーゼル車全車種(ユーザーが無料測定を希望した車両と車検、一般整備で入庫した車両)を対象として、黒煙測定器を保有している整備事業場において、無料で測定及び点検を行うキャンペーンが実施されています。
○黒煙測定器(ディーゼルスモークテスター)
運輸省の道路運送車両保安基準に示された黒煙規制値に基づき、陸運事務所又は陸運局認定の民間車検工場が車検時等に黒煙濃度を計測する装置です。運輸省の認定・検査を受けた測定器のみが使用でき、規制値をクリアできないと車検は通りません。
この黒煙測定器を用いて、ディーゼル車が排出する黒煙の汚染度を測定します。排気黒煙をろ紙で受け、その汚れ具合を光電素子で検索、電流量に換算して読み取る、ろ紙反射式という方法で測定します。
民間車検場ではこの黒煙測定器が無ければ指定工場の資格がとれませんが、認証工場や特定工場(ディーゼルは除く)には設置の義務はありません。
指定工場の黒煙測定器は年に一度国の更正検査を受けており、測定データは信頼がおけるものです。
○ディーゼルスモークテスト検査基準
保安基準第31条15項に規定する程度を超えた黒煙を排出するおそれがあると認められたときには、黒煙測定器を用いて以下により計測します。
1. 黒煙は、プローブ(黒煙測定器の排ガス採取部)を排気管内に20cm程度挿入して測定するものとする。尚、黒煙測定器は、使用開始前に十分暖機し、1日1回較正を行った上で使用する。
2. 自動車は、停止状態とし、変速ギアは中立とする。
3. 黒煙の採取は、次の運転条件のもとで行うものとする。
(イ)原動機を無負荷運転した後、加速ペダルを急速に一杯踏み込み最高回転数に達した後ただちに加速ペダルを離して無負荷運転に至る操作を2〜3回繰り返す。
(ロ)無負荷運転を5〜6秒間行う
(ハ)加速ペダルを急速に一杯踏み込み、踏み込み始めてから4秒間持続した後、加速ペダルを離し11秒間持続する。
(ニ)(ハ)の操作を継続して、3回繰り返す。
(ホ)黒煙の採取は、(ハ)において加速ペダルを踏み込み始めた時から行う。なお、黒煙を採取する直前にプローブのパージ(滞留黒煙の掃気)を行う。
4. 汚染度は、3回の測定値を平均した整数値とする。
| (拡大画面:42KB) |
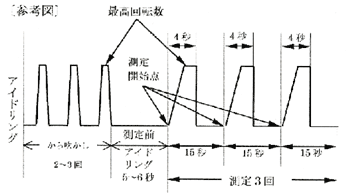 |
○黒煙チャート
黒煙の濃度が25%を超えると、目視により異常かどうか判断することも可能となってきます。目視による黒煙チェック法の例としては、黒煙の濃度に応じて色分けされた「黒煙チャート」を使用して、排気管出口で排気の色を見る方法があります。
黒煙の採取は、上記の黒煙測定器を用いる場合と同様に、2〜4によります。
| (拡大画面:131KB) |
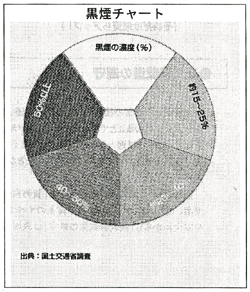 |
|