|
b. 自動車運送事業者等の判断基準(H14.4.30告示)の概要
自動車NOx・PM法では、車種規制の他に、事業者排出抑制対策(一定規模以上の事業者の自動車使用管理計画の作成等によりNOxやPMの排出抑制を行う仕組み)が定められています。そのために、事業所管大臣が総量削減基本方針に基づきNOxやPMの排出抑制のために必要な措置に関する事業者の判断基準を定めています。
| 第1 趣旨 |
| 第2 取組方針の作成とその効果等の把握 |
| 事業者は、事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出抑制のための措置を計画的かつ効果的に行うよう、以下のように取り組むこととする。 |
| |
(1)計画(自主目標、措置の方針)を作成 |
| |
(2)具体的措置を実施 |
| |
(3)措置の実施状況、効果を把握 |
| |
(4)計画(自主目標、措置の方針)を再検討 |
| また、上記の取組のため、自動車の使用状況等について記録化を行う。 |
| 第3 排出量の抑制のための措置 |
| 事業者は、次のような措置の中から適切に選択した措置を講ずることにより、事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制を図る。 |
| 第3−1 すべての自動車運送事業者等に共通する措置 |
| |
1. 車両1台当たりの自動車排出窒素酸化物等の排出量の削減 |
| |
|
(1)自動車排出窒素酸化物等の排出量がより少ない車両への転換 |
| |
|
(2)低公害車の積極的導入 |
| |
|
(3)適正運転の実施等 |
| |
|
|
(1)適正運転の実施 |
| |
|
|
|
ア)おだやかな発進と加速(急発進・急加速の排除) |
| |
|
|
|
イ)早めに一段上のギアにシフトアップ |
| |
|
|
|
ウ)定速走行・経済速度の励行 |
| |
|
|
|
エ)エンジンブレーキの多用(ディーゼル車) |
| |
|
|
|
オ)予知運転による停止・発進回数の抑制 |
| |
|
|
|
カ)空ぶかしの排除 |
| |
|
|
|
キ)アイドリング・ストップ |
| |
|
|
|
ク)不要な積荷の抑制 |
| |
|
|
(2)車両の維持管理 |
| |
|
|
|
ア)エアクリーナーの清掃・交換 |
| |
|
|
|
イ)エンジンオイルの適正な選択・定期的な交換 |
| |
|
|
|
ウ)適正なタイヤ空気圧の維持 |
| |
|
|
|
エ)DPF等排出ガスを低減する装置等については、所要の性能を維持するための点検・整備 |
| 第3−2 貨物自動車運送事業者及び第二種利用運送事業者に係る措置 |
| |
1. 車両走行量の削減 |
| |
|
(1)車両の有効利用の促進 |
| |
|
|
(1)共同輸配送、積合せ輸送等の推進 |
| |
|
|
(2)営業用トラックの利用促進のための環境醸成 |
| |
|
|
(3)ジャスト・イン・タイムサービスの改善、道路混雑時の輸配送の見直し等 |
| |
|
(2)モーダルシフトの推進 |
| |
|
(3)情報化の推進 |
| |
|
(4)物流施設の高度化、物流拠点の整備等 |
| |
2. 荷主等関係者との連携・協議体制の構築とこれへの積極的な参画 |
| |
3. 事業者団体を中心とした自主的な取組 |
| |
|
(1)自動車排出窒素酸化物等削減ハンドブック等の作成 |
| |
|
(2)調査研究体制の確立等 |
| 第3−3 旅客自動車運送事業者に係る措置 |
| |
1. バスの利用促進 |
| |
|
(1)バス輸送サービスの改善、情報化の推進 |
| |
|
(2)走行環境の改善 |
| |
2. 一般乗用旅客自動車運送事業における車両走行量の削減 |
| |
|
(1)情報化の推進 |
| |
|
(2)需要動向に応じた車両管理 |
| |
3. 事業者団体を中心とした自主的な取組 |
| |
|
(1)自動車排出窒素酸化物等削減ハンドブック等の作成 |
| |
|
(2)調査研究体制の確立等 |
(4)条例に定める運行規制対象車数の把握
チェック項目
| (拡大画面:26KB) |
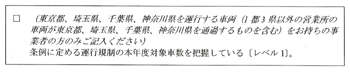 |
解説
東京都など1都3県では、条例で定める粒子状物質の排出基準を満たさないディーゼル車は区域内での運行が禁止されます。規制対象車は規制適合車への代替を行うか、もしくは規制対象車を引き続き使用するためには知事が指定する粒子状物質減少装置(DPF、酸化触媒)の装着が必要になります。
この規制は、平成15年10月より適用されます。ただし、初度登録新車登録から7年間は規制適用が猶予されます。例えば、平成8年10月1日以前に登録された排出基準を満たさないディーゼル車は、平成15年10月1日に猶予期間が経過するため、平成15年10月から区域内を走行することができなくなります。また、千葉県においては、自動車NOx・PM法の対策地域以外に使用の本拠があり同対策地域外のみを走行する車両については、その使用目的、形態、運行範囲等を届け出ることにより、初度登録から12年間は規制適用が猶予されます。
(規制の基準値)
規制値の考え方としては、すでに走っているディーゼル車の排出基準を、国が新車に対して適用している排出基準(「長期規制」と呼ばれる)にまで下げさせるというものです。なお、平成17年4月1日以降の知事が定める日から規制値は強化され、この場合の規制値は、国が2003年から新車に対して適用する排出基準(「新短期規制」と呼ばれる)と同じ値となります。
【例】2トン積トラック(車輌総重量4トン強)の場合
| (拡大画面:338KB) |
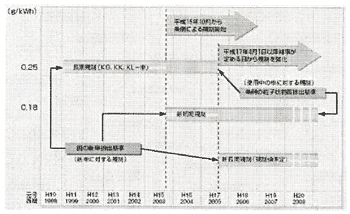 |
(対象車種)
規制対象車種は以下の表に示すとおりです。乗用車は規制の対象外となります(NOx・PM法では規制対象)。
| 規制対象車種 |
例示 |
ナンバープレートの分類番号 |
備考 |
| 貨物自動車 |
トラック、バン |
1−、4−、6− |
自家用、事業用の種別を問わない。 小型、普通自動車の種別を問わない。 |
| 乗合自動車 (乗車定員11人以上) |
バス、マイクロバス |
2− (一部5−、7−) |
| 特種用途自動車 |
冷蔵冷凍車、コンクリート・ミキサー車 |
8− |
乗用車タイプをベースにしたものは規制の対象外。 |
|
また、車の型式と初度登録年により、所有している車がいつから規制を受けるのかについては、次の表のようになっています。
| (拡大画面:528KB) |
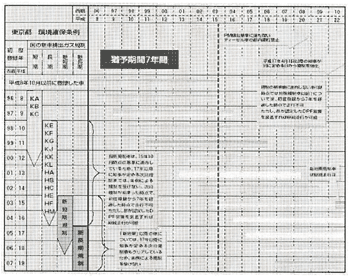 |
|