|
(2)最新規制適合ディーゼル車:導入目標の設定と取組
チェック項目
| (拡大画面:55KB) |
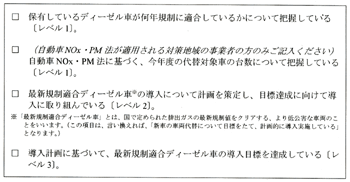 |
解説
最新規制適合ディーゼル車とは、国の定める排出ガスの最新規制値をクリアする、より低公害な車両をいいます。
現状では、燃料供給等のインフラ整備が遅れていたり、車両重量によっては該当する低公害車がないなどにより、バス事業では今後もディーゼル自動車に依存せざるをえない状況にあります。このため、最新規制適合車の早期導入が期待されます。特に、自動車NOx・PM法の対象地域では、法に定める排出基準に適合しない車両は、地域内であらたに車検が受けられなくなります。地域内に登録されている使用過程車については、平成14年8月1日以降の車検時に、車検証の備考欄に排出基準への適否、使用可能最終日に関する情報などが表示されています。
対象地域の事業者にあっては、代替え対象車を把握し、最新規制適合車を導入することが望まれます。
(3)燃料の管理
チェック項目
| (拡大画面:13KB) |
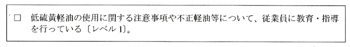 |
解説
低硫黄軽油とは、石油の精製過程で硫黄分を大幅に取り除いた(脱硫)ディーゼル車用燃料の軽油のことです。硫黄分が少ない軽油は、排出ガス中のPMなどの発生を減少させたり、粒子状物質減少装置の性能や耐久性を向上させたりします。
粒子状物質減少装置の中には、硫黄が50ppm以下の軽油(低硫黄軽油)を使用しなければ正常に機能しないものや装置の寿命が短くなるものがあります。また、低硫黄軽油の使用を前提に製造される超低PM排出ディーゼル車に硫黄が500ppm程度の従来タイプの軽油を給油すると、排出ガス性能が大幅に悪化します。このため、硫黄分の多い従来タイプの軽油を誤って給油しないよう車両には「S50」と記したラベル(下図参照)を給油口付近や運転者席の見やすい位置に貼付することになりました。
また、低硫黄軽油は全てのディーゼル車に使える軽油ですが、東京都などによる試験導入において、7〜8年以上使った路線バスの一部で燃料噴射ポンプから軽油のにじみが見つかっています。その原因は、ゴム製シールが熱で固くなったためで、エンジンルームの温度が特に高い路線バス特有の問題であると考えられています。軽油はガソリンと異なり、極めて引火性が低く、単体で燃えることはありませんが、特に燃料噴射ポンプのまわりの点検は重要となります。
また、不正軽油とは、ディーゼル車の燃料として使用される軽油に、脱税を目的として重油などを混ぜるなどしたものを軽油と偽り販売されたもののことです。この不正軽油は、正常な軽油の流通を阻害するばかりではなく、排出ガス中のPMやNOxが正常な軽油よりも増加するため、環境に悪い影響を与える原因ともなっています。
このように、低硫黄燃料の使用に当っての注意事項や不正軽油の問題点等について、従業員に教育・指導することが必要です。
「S50低硫黄軽油専用」ラベル
関連資料
a. 「自動車NOx・PM法」における車種規制
車種規制とは、自動車NOx・PM法の対策地域(東京都とその周辺地域、大阪府とその周辺地域、名古屋市とその周辺地域で政令で指定された地域)で、ディーゼル車、ガソリン車、LPG車を問わずトラック、バス等に関して特別の排出基準(窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準)を定め、これに適合する窒素酸化物等の排出量がより少ない車を使うことが必要となる規制です。
この規制は、平成14年10月1日より新車はもとより、現在使用中の自動車に対しても適用されています。
排出基準
| (拡大画面:58KB) |
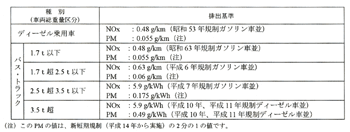 |
(注意事項)
○車種によっては、最新規制ディーゼル車でも自動車NOx・PM法の排出基準非適合車があります。
○ディーゼル車のハイブリッド車にも自動車NOx・PM法の排出基準非適合車があります。
非適合車の型式:HA,HB,HC,HD,HE,HT,HU,HW,HX,HY(3.5 t以下)
○トラック・バス等についてはガソリン車、LPG車でも排出基準に適合しない場合があります。
非適合車の型式:H,J,L,M,T,Z
排出基準を満たしていない使用過程車に対する適用猶予期間は、表のとおりです。正確な期日は、平成14年8月1日以降の車検時から車検証に記載されています。これらの情報をもとに、現在保有しているディーゼル車の規制区分を把握し、買い替え時期を把握しておくことが必要です。
排出基準を満たしていない使用過程車に対する適用猶予期間
| 種別 |
ナンバープレートの分類番号 |
初度登録日
からの年数 |
| 普通貨物自動車 |
1、10〜19及び100〜199 |
9年 |
| 小型貨物自動車 |
4、6、40〜49、60〜69、400〜499及び600〜699 |
8年 |
大型バス
(乗車定員30人以上) |
2、20〜29及び200〜299 |
12年 |
マイクロバス
(乗車定員11人以上30人未満) |
2、20〜29及び200〜299(一部、5、7、50〜59、70〜79、500〜599及び700〜799) |
10年 |
| ディーゼル乗用車 |
3、5、7、30〜39、50〜59、70〜79、300〜399、500〜599及び700〜799 |
9年 |
| 特種自動車 |
8、80〜89及び800〜899 |
原則10年 |
|
以下に、排出基準を満たしていない使用過程車の使用可能最終日の一覧を示します。
排出基準を満たしていない使用過程車の使用可能最終日の一覧
| 種別 |
初度登録日 |
使用可能最終日 |
| 普通トラック |
平成元年9月30日以前 |
平成15年9月30日以降の検査証の有効期間満了日 |
| 平成元年10月1日〜 平成5年9月30日 |
平成16年9月30日以降の検査証の有効期間満了日 |
| 平成5年10月1日〜 平成8年9月30日 |
平成17年9月30日以降の検査証の有効期間満了日 |
| 平成8年10月1日〜 平成14年9月30日 |
初年度登録日から起算して9年間の末日に当たる日以降の検査証の有効期間満了日 |
| 小型トラック |
平成2年9月30日以前 |
平成15年9月30日以降の検査証の有効期間満了日 |
| 平成2年10月1日〜 平成6年9月30日 |
平成16年9月30日以降の検査証の有効期間満了日 |
| 平成6年10月1日〜 平成9年9月30日 |
平成17年9月30日以降の検査証の有効期間満了日 |
| 平成9年10月1日〜 平成14年9月30日 |
初年度登録日から起算して8年間の末日に当たる日以降の検査証の有効期間満了日 |
大型バス
(定員30人以上) |
昭和61年9月30日以前 |
平成15年9月30日以降の検査証の有効期間満了日 |
| 昭和61年10月1日〜 平成2年9月30日 |
平成16年9月30日以降の検査証の有効期間満了日 |
| 平成2年10月1日〜 平成5年9月30日 |
平成17年9月30日以降の検査証の有効期間満了日 |
| 平成5年10月1日〜 平成14年9月30日 |
初年度登録日から起算して12年間の末日に当たる日以降の検査証の有効期間満了日 |
マイクロバス
(定員11人以上30人未満)
特種自動車
(車検期間が1年のもの) |
昭和63年9月30日以前 |
平成15年9月30日以降の検査証の有効期間満了日 |
| 昭和63年10月1日〜 平成4年9月30日 |
平成16年9月30日以降の検査証の有効期間満了日 |
| 平成4年10月1日〜 平成7年9月30日 |
平成17年9月30日以降の検査証の有効期間満了日 |
| 平成7年10月1日〜 平成14年9月30日 |
初年度登録日から起算して10年間の末日に当たる日以降の検査証の有効期間満了日 |
特種自動車
(車検期間が2年のもの) |
昭和63年9月30日以前 |
平成15年9月30日以降の検査証の有効期間満了日※ |
| 昭和63年10月1日〜 平成4年9月30日 |
平成16年9月30日以降の自動車検査証の有効期間満了日 |
| 平成4年10月1日〜 平成7年9月30日 |
平成17年9月30日以降の検査証の有効期間満了日 |
| 平成7年10月1日〜 平成14年9月30日 |
初年度登録日から起算して10年間の末日に当たる日以降の検査証の有効期間満了日 |
ディーゼル乗用車
(車検期間が1年のもの) |
平成元年9月30日以前 |
平成15年9月30日以降の検査証の有効期間満了日 |
| 平成元年10月1日〜 平成5年9月30日 |
平成16年9月30日以降の自動車検査証の有効期間満了日 |
| 平成5年10月1日〜 平成8年9月30日 |
平成17年9月30日以降の検査証の有効期間満了日 |
| 平成8年10月1日〜 平成14年9月30日 |
初年度登録日から起算して9年間の末日に当たる日以降の検査証の有効期間満了日 |
ディーゼル乗用車
(車検期間が2年のもの) |
平成7年9月30日以前 |
平成16年9月30日以降の自動車検査証の有効期間満了日 |
| 平成7年10月1日〜 平成14年9月30日 |
初年度登録日から起算して9年間の末日に当たる日以降の検査証の有効期間満了日 |
|
|
| ※ |
平成14年9月30日現在において、検査証の有効期間の残余期間が1年を超える自動車にあっては、「平成15年9月30日」を「平成16年9月30日」と読み替える。 |
|