|
c. 地方公共団体で定める低公害車(低排出ガス車)
七都県市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市)や京阪神六府県市(京都府、大阪府、兵庫県、京都市、大阪市、神戸市)、山梨県、札幌市等においては、自動車排出ガス対策の観点から、低公害車(低排出ガス車)指定制度を設けています。この制度は、NOx等の排出量が少ない(国の規制レベルを大幅に下回る)自動車を指定することにより、これを広く普及させることを目的としています。指定のための基準は国の「低排出ガス車認定制度」の認定基準とほぼ同様となっています。
指定低公害車に認定されると、地方公共団体が率先して購入するほか、指定低公害車の購入者、使用者には、自動車取得税や自動車税の軽減、公的駐車場の料金の割引などのメリットがあります。また、指定低公害車の購入に際しては、助成制度等の支援制度も設けられています。
また、七都県市指定低公害車や京阪神六府県市指定低排出ガス車は、NOx・PM法で義務づけられた自動車使用管理計画書における「特定自動車の低公害車等への代替に関する計画」で対象としている低公害車に含まれます。
d. 「低公害バス」並びに「人にやさしいバス」の導入状況
(平成14年3月末現在 日本バス協会会員事業者保有車両)
| (単位:両) |
| |
低公害バス |
人にやさしいバス |
| アイドリングストップ装置付バス |
電気式 |
CNGバス |
DPF装着バス |
リフト付バス |
ワンステップバス |
ノンステップバス |
| 乗合 |
貸切 |
小型 |
中・大型 |
計 |
| H11.3末計 |
2,645 |
280 |
215 |
− |
289 |
175 |
− |
− |
2,198 |
436 |
| H12.3末計 |
3,806 |
303 |
294 |
− |
291 |
248 |
− |
− |
3,145 |
830 |
| H13.3末計 |
5,025 |
317 |
325 |
− |
338 |
253 |
− |
− |
3,706 |
1,424 |
| H14.3末計 |
6,433 |
322 |
364 |
798 |
415 |
293 |
441 |
4,415 |
4,856 |
2,545 |
|
|
| (出典)日本バス協会HP(http://www.bus.or.jp/info/nonstepbus.htm) |
e. 粒子状物質減少装置(DPF、酸化触媒)の概要
○DPF(Diesel Particulate Filter)
軽油を燃料とする自動車の排気管等に装着して、自動車から排出される粒子状物質を捕集し、粒子状物質の排出を減少させる装置です。
捕集した粒子状物質の処理方法により、以下の方式に区分されます。
(1)捕集した粒子状物質を電熱線等により燃焼してフィルターを再生する方式(強制再生方式)
(2)捕集した粒子状物質を自動車の排出ガスの熱または触媒等の作用で酸化除去して連続的にフィルターを再生する方式(連続再生方式)
(3)自動車が稼働していないときに、フィルターを整備し、捕集した粒子状物質を処理する方式(非再生方式)
○酸化触媒
白金などの触媒による酸化作用により粒子状物質を減少させる装置です。PMの減少率はDPFよりも低くなりますが、一酸化炭素および炭化水素を大幅に減少させるとともに、ディーゼル自動車特有の排気ガス臭を低減させます。
f. 低公害車メールマガジン
国土交通省 報道発表資料 平成14年10月29日
国土交通省では、低公害車普及を図るため、自治体・企業等の自動車購入責任者などを対象に、低公害車メールマガジンを発行し、低公害車普及の必要性やグリーン税制対象車種に関する情報、整備・エコドライブ・環境物品等に係る実用的な情報提供に取り組んでいます。
報道発表資料 低公害車メールマガジンの創刊について 平成14年10月29日
<問い合わせ先> 総合政策局環境・海洋課(内線24312)TEL:03-5253-8111(代表)
低公害車普及を図るため、自治体・企業等の自動車購入責任者などを対象に、低公害車メールマガジンを10月31日(木)に創刊しますので、お知らせします。
今後、低公害車普及の必要性やグリーン税制対象車種に関する情報、整備・エコドライブ・環境物品等に係る実用的な情報を提供することとしています。
なお、刊行は年6回程度を予定しています。
また、同時に「フォーラム」を立ち上げ、ネット上でメルマガ読者が相互に情報をやり取りできるようにし、低公害車普及のための情報交換の促進を図ります。
------------------------------------------------------
別紙
■■■■┏━━ 低公害車メールマガジン ━━┓■■■■
■■■■┗━━━━ 2002/創刊号 ━━━━━┛■■■■
□はじめに□
皆様はじめまして。本日、低公害車メールマガジンを創刊しました。今後充実した誌面づくりに努めていきますので、どうかご愛読いただきますようお願いいたします。
自動車に起因する環境問題は、近年ますます深刻な問題になっています。地球温暖化問題については、我が国から排出される二酸化炭素の約2割までが自動車からであり、しかも90年に比べて2000年で約21%増と、急増しています。
また、大都市圏での大気汚染問題に関しては、窒素酸化物(NOx)の約5割、粒子状物質(PM)の約4割が自動車に起因しています。
一方、自動車は今や国民生活にはなくてはならないものであり、その利便性を確保しつつ、自動車に関する環境問題に取り組んでいくには、環境性能が優れた低公害車を普及させることが必要ですが、これには低公害車やその普及についての情報が重要です。
そこで、国土交通省では、低公害車に関する情報を発信するとともに、低公害車の導入促進に有効な情報交換を進めるため、メールマガジンを発行し、読者が参加するフォーラムを開設することとしました。読者の皆様におかれましては、ご勤務先などでの低公害車に関する情報や導入に向けた事例についての情報をご提供いただければ幸いです。
低公害車普及協議会の活動が始まる
現在各地において、地方運輸局をはじめとする国の関係機関、地方公共団体、運輸関係事業者、経済関係団体等で低公害車の普及に向けた地域協議会を立ち上げ、普及目標の設定、広報活動、情報交換等の取り組みが始まっています。
□北海道ブロック
本年7月22日に第1回協議会を札幌市内で開催し、議長に佐藤馨一北海道大学大学院教授を選出、道内における低公害車の普及を目指して導入計画の策定の呼びかけや導入状況及び導入計画の把握を内容とする「低公害車導入促進実施要領」を決定しました。
□東北ブロック
<<<<中略>>>>
●低公害車に関する情報、導入に向けた事例をお寄せ下さい。
E−mail:teikougaisha@mlit.go.jpでお願いします。
(ご寄稿されたメールは、ご了解いただいた上でサイト上で紹介する場合がございます。)
●本メールサービスについてのお問い合わせは、
E−mail:teikougaisha@mlit.go.jpまでお願いします。
掲載記事の積極的な転載をお願いします。
〒100−8918 東京都千代田区霞ヶ関2−1−3
発行人:国土交通省総合政策局環境・海洋課長
編集人:国土交通省総合政策局環境・海洋課長補佐
g. 低公害車の普及促進に対する主な補助制度の概要
1. 自動車税の重軽課
1.
|
環境自動車(環境負荷の小さい自動車)を購入した場合は軽課、環境負荷の大きい古い型式の自動車に対しては重課
|
2. |
自動車税の重軽課は、軽課と重課とがバランスする税収中立で設定
|
|
|
軽課 約220億円
|
・低公害車のうち電気、圧縮天然ガス、メタノール車
|
50%軽減(2年間)
|
|
・☆☆☆かつ低燃費車
(☆☆☆は、排出ガスが最新規制値の1/4以下の自動車)
|
50%軽減(2年間)
|
|
|
・☆☆かつ低燃費車
(☆☆は、排出ガスが最新規制値の1/2以下の自動車)
|
25%軽減(2年間)
|
|
|
・☆かつ低燃費車
(☆は、排出ガスが最新規制値の3/4以下の自動車)
|
25%軽減(2年間)
|
|
|
|
|
※H13.4.1〜H14.3.31に新車新規登録を受けた場合にH14年度・H15年度分の自動車税が軽減
|
|
※H14.4.1〜H15.3.31に新車新規登録を受けた場合にH15年度・H16年度分の自動車税が軽減
|
|
※低燃費車:改正省エネ法に基づく2010年新燃費基準達成車
|
重課 約220億円
|
|
|
※H14.3.31までに車齢11年あるいは13年を超えた場合はH14年度以降重課
|
|
※H15.3.31までに車齢11年あるいは13年を超えた場合はH15年度以降重課
|
|
※一般乗合用バス、低公害車は除く。
|
|
※車齢とは、新車新規登録を受けてからの経過年数。
|
2. 自動車取得税の軽減
(1)ディーゼル車の廃車代替
軽課 ・旧型ディーゼル車を廃車して取得する最新規制適合車
|
NOx・PM法対策地域内
|
2.3%の軽減
|
|
(営業用 3%→0.7% 自家用 5%→2.7%)
|
|
|
・NOx・PM法に基づく廃車代替
H14.3.2〜H15.3.31 2.3%の軽減
H15.4.1〜H17.3.31 1.9%の軽減
H17.4.1〜H19.3.31 1.5%の軽減
H19.4.1〜H21.3.31 1.2%の軽減
H13.4.1〜H15.3.31 0.5%の軽減
(2)低燃費車特例
軽課 ・低燃費車かつ☆(排出ガスが最新規制値の3/4以下の自動車)の取得
H13.4.1〜H15.3.31までの取得
(3)低公害車特例
軽課 ・電気自動車等低公害車の取得(現行のまま2年延長)
|
電気、メタノール、圧縮天然ガス、ハイブリッド車(バス、トラック)
|
2.7%の軽減
|
|
ハイブリッド車(乗用車)
|
2.7%の軽減
|
|
|
H13.4.1〜H15.3.31までの取得
(4)最新排出ガス規制適合車の早期取得特例
軽課 ・平成14年排出ガス規制適合車(ガソリン軽トラック、ディーゼル乗用車、ディーゼル軽量トラック)の取得
|
H13.4.1〜H14.9.30
|
1.0%の軽減
|
|
H14.10.1〜H15.2.28
|
0.1%の軽減
|
|
|
・平成15年排出ガス規制適合車(ディーゼル中量トラック、ディーゼル重量トラック)の取得
|
H14.4.1〜H15.9.30
|
1.0%の軽減
|
|
H15.10.1〜H16.2.29
|
0.1%の軽減
|
|
|
3. 所得税、法人税(国税)の優遇措置
| 優遇の対象: |
(1)低公害車(電気、天然ガス、メタノール、ハイブリッド)の取得 |
| (2)燃料等供給設備(天然ガス、メタノール)の設置 |
| 優遇の内容: |
次のa)またはb)の優遇措置を選択的に受けることができる。 |
| a)初年度30%の減価償却の特例 帳簿価格の30%の額を普通償却限度額に上乗せできる。初年度の納税額が減額され、税の支払いの繰り延べになる。 |
| b)7%の所得税(法人税)の特別控除(資本金1億円未満の法人等に限る) 当期に納付すべき所得税(法人税)から、当該車両・設備の取得評価額の7%(所得税(法人税)額の20%を限度とする)を控除する。 |
| 期間: |
平成16年3月31日まで |
h. エコ・ステーションの概要
低公害自動車であるクリーンエネルギー自動車(電気・天然ガス・メタノール)及びディーゼル代替LPガス自動車への燃料供給を事業として行う燃料等供給施設を「エコ・ステーション」と呼んでいます。
平成5年4月、通商産業省(現経済産業省)資源エネルギー庁の指導のもと財団法人エコ・ステーション推進協会が設立され、エコ・ステーション事業は、既設のガソリンスタンドやLPガススタンドに併設することをベースにスタートしました。
1)電気、天然ガス エコ・ステーションの定義
電気、天然ガス自動車への燃料等供給を事業として行うための燃料等供給設備を設置する施設をいいます。
事業名:クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金燃料等供給設備普及事業
2)LPガス エコ・ステーションの定義
ディーゼル代替LPガス自動車用燃料供給設備を設置する施設をいいます。ディーゼル代替LPガス自動車とは、タクシーなど乗用車及び軽自動車を除くLPガス自動車を意味します。
事業名:ディーゼル代替LPガス自動車普及基盤整備事業
3)エコ・ステーション事業(補助事業)の概要
エコ・ステーションの一層の整備推進を図るため、その支柱となる事業として協会ではエコ・ステーション事業を行う事業者に国の補助金を交付する補助事業を実施しています。
補助金限度額
| 設備名 |
設置費 |
改造費 |
運営費/年 |
| 新設 |
| 電気自動車用充電設備 |
急速充電設備 |
30百万円 |
|
|
| 普通充電設備 |
30百万円 (3.5百万円/基) |
11百万円 |
1,980,600円 |
| 天然ガス自動車用充てん設備 |
90百万円 |
− |
− |
| ディーゼル代替LPガス自動車用充てん設備 |
1/2補助 ただし、上限30百万円 |
17百万円 |
1,980,600円 |
|
クリーンエネルギー自動車導入促進事業全体のしくみ
| (拡大画面:184KB) |
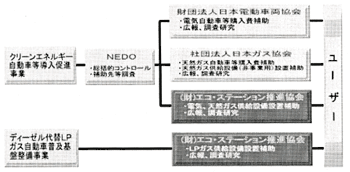 |
4)エコ・ステーションの例
(1)天然ガス[併設型]
天然ガス自動車充填設備をSS(ガソリンスタンド)に併設したエコ・ステーションです。全国の天然ガスエコ・ステーションの中で最も多い設置方式で、この他、併設型としてはLPガススタンドに設置するケースもあります。併設型は、SS等の敷地と充填に必要な人員を有効活用できるなどのメリットがあります。敷地に余裕がない場合は、主要設備を屋上又は地下に設置するケースもあります。設置に関しては、消防法の他、高圧ガス保安法、建築基準法等の規制の対象となります。
(2)天然ガス[マルチ型]
天然ガス自動車充填設備を含め、複数の低公害自動車用燃料供給設備をSS(ガソリンスタンド)等に併設したエコ・ステーションです。一つのエコ・ステーションにおいて、多様な燃料供給のニーズに応えることができ、将来、異なる燃料種別の低公害自動車の普及動向に合わせてより多くの設置が望まれるエコ・ステーションです。設置に関しては、消防法の他、高圧ガス保安法、建築基準法等の規制の対象となります。
(3)天然ガス[単独型]
天然ガス自動車充填設備のみ単独に設置されたエコ・ステーションです。併設型に比べ、専用の敷地と充填に必要な人員の確保が必要となりますが、エコ・ステーションを設置したい地域に敷地条件やガス導管の敷設条件等の面でSS併設型の適地がない場合用いられる設置方式です。設置に関しては、高圧ガス保安法、建築基準法等の規制の対象となります。
|