|
(3)アイドリングストップの励行
チェック項目
| (拡大画面:5KB) |
 |
解説
アイドリングストップはエコドライブの取組のひとつですが、エコドライブの中でもとくに重要な取組であり、東京都などではアイドリングストップの遵守が条例で義務づけられています。また、大型車1台が毎日30分ずつアイドリングストップを行った場合、1年間で燃料を約300l、燃料費にして約22,500円削減できるといわれています。
アイドリングストップの重要性を認識したうえで、エコドライブに関する情報提供・教育の実施などに加え、特に、アイドリングストップの必要性や実施方法について周知することが必要です。
従業員に対する周知方法としては、資料の掲示や回覧、点呼・出庫時の確認などがあります。
チェック項目
| (拡大画面:7KB) |
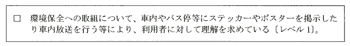 |
解説
環境保全への取組については、従業員の理解や意識を高めることと同様に、利用者に対して理解を求めることが重要です。アイドリングストップの実施により、冷暖房などで利用者に不便をかけることも想定されますので、利用者の理解を求める内容のステッカーや車内ポスターなどを車内掲示したり、車内放送を活用することにより、取組内容や取組姿勢を伝えることが望まれます。
アイドリングストップについて利用者の理解を求める車内掲示用のステッカー等の内容として、次のようなものがあります。
○車内掲示の例
エコドライブ推進について
地球環境を保全するため、
アイドリングストップ(エンジン停止)をいたします。
このため、車内の温度調整が十分でない場合がありますが、
何卒趣旨をご理解いただき、皆様のご協力をお願いいたします。
株式会社△△
チェック項目
| (拡大画面:4KB) |
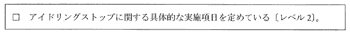 |
解説
アイドリングストップ装置が装着されていない車両の場合、アイドリングストップを具体的に行う場合の基準を定め、あらかじめドライバーに周知しておくことが重要です。
基準として、次のような例があります。
・始業点検時
・営業所及び車庫停車時
・始発停留所
・決められた停留所等(時間調整を実施する停留所、休憩停車するSA、PA等)
・貸切バスにおいて乗客が降りたとき(車外見学等)の停車時
・交差点での信号待ち
・一定時間以上停車する場合
チェック項目
| (拡大画面:7KB) |
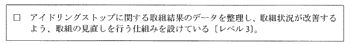 |
解説
アイドリングストップに関する取組状況は、レボタコの分析や運転日報に設けられたアイドリングストップ実施状況に関する記載等によって把握することが出来ます。
見直しの仕組みとしては、実施状況の把握、評価の手法、ドライバー教育、見直し時期などエコドライブ推進計画に定めておきます。
関連資料
a. アイドリングストップによる経済効果
<アイドリングストップによる1台あたりの燃料消費削減量>
| (拡大画面:17KB) |
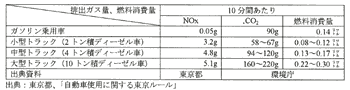 |
|
<大型車が毎日30分づつ1年間アイドリングを停止した場合のコスト効果>
|
| 大型車の年間消費削減量 |
約300リットル |
| 年間の燃料削減費 |
約22,500円 |
|
|
| 出典:東京都、「自動車使用に関する東京ルール」 |
b. 整備管理者によるチェックの具体例(京浜急行電鉄株式会社)
京浜急行電鉄株式会社では、各営業所毎に主要駅のターミナルなどにおいて、整備管理者が、乗務員によるアイドリングストップの実施状況を確認し、必要に応じて適宜指導しています。チェックする内容や報告する項目は特に定められていませんが、以下に、整備管理者が作成する報告書の一例を示します。
この取組においては、評価や指導のためのデータ収集を目的とするのではなく、整備管理者が確認を行っていることが乗務員に伝わることによってアイドリングストップの実施率が上がっていくことを期待しています。
○○営業所
アイドリングストップについて
1. 巡回立会日:平成XX年12月X1日、X2日、X3日、X4日、X5日、X6日、X7日
2. 場所:△△駅、□□駅、◇◇駅
3. エンジン停止割合:
| (拡大画面:32KB) |
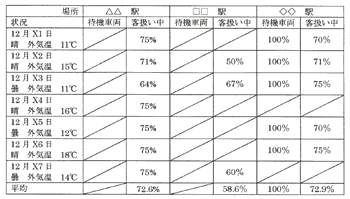 |
4. コメント:
・待機車両、乗務員控室有り(◇◇駅)は100%エンジンストップしているが、客扱い車両は、△△駅で72.6%、◇◇駅では72.9%ある、□□駅のバス停では、お客様が多い時はエンジン停止をしているが、少ない時はエンジン停止していない為58.6%である。
・乗務員の指導については、事故防止懇談会を月2回実施し、又車両室及び乗務員室等へポスター掲示にて指導し巡回立会いを実施して、アイドリングストップ進捗状況の調査を実施している。
・エコドライブ強化月間には、◎アイドリングストップ ◎急発進、急加速の防止 ◎速度に適したギアでの走行並びに適応ギアへの早めのシフトチェンジを、重点に指導し、又黒煙チェックをチャート紙にて街頭及び、点検整備時に調査を実施している。
(4)推進手段等の整備
チェック項目
| (拡大画面:6KB) |
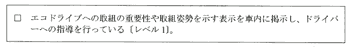 |
解説
エコドライブの実施率を向上するためにはドライバーの努力は欠かせません。そのためには、まず、エコドライブの重要性や取組姿勢について運転席の周囲などドライバーによく見える所へ掲示し、注意を喚起することが必要です。また、乗務員手帳や社員証、運転日報などへ記載するなどにより、それらを手にしたときにエコドライブについて意識することができるような仕掛けを作ることも重要です。この取組は、ドライバーへの意識の喚起という基本的な内容なので、レベルは1としてあります。
エコドライブへの取組に対するドライバーの意識の高揚を図るために、エコドライブの取組内容の中から主なものを厳守事項として取り上げたステッカーの内容の例として次のようなものがあります。
○ドライバーに対する掲示の例
エコドライブを推進しましょう
・急発進、急加速、急ブレーキを控えます。
・アイドリングストップを心がけます。
・エアコンの設定温度を控えめにします。
・シフトアップを早めに行います。
・タイヤの空気圧を適正にします。
チェック項目
| (拡大画面:6KB) |
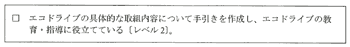 |
解説
さらに、より効果的な取組としては、エコドライブに関する手引きを作成し、具体的な取組方法や効果についてドライバーの理解を深めることが望まれます。
エコドライブへの各取組内容の目的や効果については、「(2)エコドライブのための実施体制」で整理しましたが、事業者の中には、これらの情報に加えて、保有している車両の実際の燃料消費量を集計した結果などを反映させて、より詳細に補足している例も見られます。また、手引きの形態としては、エコドライブに関して独立させた冊子を作成し、ドライバーに配布している事業者もありますし、乗務員手帳や安全などに関するドライバー向けの教育用テキストの中に、エコドライブに関する内容を取り上げて記載している事業者もあります。この取組は意識の喚起に止まらず、具体的な指導内容を示しているので、取組レベルは2としています。
チェック項目
| (拡大画面:10KB) |
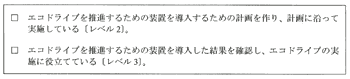 |
解説
エコドライブへの取組には、ドライバーに対する教育やドライバーによる積極的な協力が不可欠ですが、さらにエコドライブへの取組が容易に進むような装置(一例として、レボタコグラフやキー抜きロープ)等を整備することが有効です。
また、装置類の導入にあたっては、計画的な導入や、導入した効果の確認が望まれます。
関連資料
a. エンジン回転数警報装置の具体例(神奈川中央交通株式会社)
エンジン回転数警報装置は、必要以上にエンジン高回転域を使用することを抑制するために、設定された回転数を超えた場合に、音で警報を発する装置です。神奈川中央交通株式会社では、エンジン回転数が2000回転を超えた場合に、ドライバーに警告を与えるとともに、超えた回数をカウントする仕組みになっています。カウンターの数字は、乗務終了時にドライバーが読み取り、点検表に記入しチェックしています。
b. アイドリングストップ装置
アイドリングストップ装置は、渋滞や信号待ちなどの停車時に、自動的にエンジンを停止し、発進操作時には自動的にエンジンを始動するシステムです。この装置により、排出ガスの低減や燃費改善を図ります。
c. キー抜きロープ
運転席から離れる際などに、確実にエンジンの回転を止めるために、ドライバーとエンジンキーを結ぶロープです。
d. 運行記録計(タコグラフ)
運行記録計は「速度・時間・距離」の3要素の記録を行う装置です。
道路運送車両法で、貸切バス、往路100kmを超える路線バス、5トン以上の業務用トラックおよび、地方運輸局長の指定する地域(下記参照)のタクシー(個人タクシーを除く)等への装着が義務づけられています。
1998年3月にはアナログ式に加え、デジタル記録方式も新たに運輸省の型式指定品目となりました。
○アナログ式とデジタル式の違い
アナログ式は、速度・時間・距離の3要素を、円盤状の紙(タコチャート)に線描して記録する方式です。デジタル式(正式名・デジタル式運行記録計)は、運行データをデジタル(ビット数字)化して記録する方式です。
○運行記録計(タコグラフ)の装着義務対象車の指定
運行記録計の装着が義務付けられた時期およびその対象車は以下の通りです。
| 時期 |
対象車 |
| 昭和37年10月 |
・貸切バス
・往路100kmを超える路線バス
・路線トラック |
| 昭和42年5月 |
・8トン以上のトラック
・最大積載量5トン以上のトラック
・上記を牽引するトラクター |
| 昭和42年10月 |
・全国15都市のハイヤー・タクシー |
| 平成2年12月 |
・特別積み合わせ貨物運送に係わる運行系統に配置する事業用自動車 |
|
「速度・時間・距離」の3要素の他に、エンジン回転数も記録できるレボタコグラフ(回転記録付きタコグラフ:アナログ式タコグラフの一部やデジタル式タコグラフにその機能が付加されている)を活用することにより、アイドリングストップの実施状況を把握することが可能となります。
e. レボタコグラフ(回転記録付きタコグラフ)の具体例(遠州鉄道株式会社)
遠州鉄道株式会社では、全ての路線バス(約400両)と一部の貸切バス(約200両中の17両)にレボタコグラフを装着しています。
同社では、例えば大型車の場合、エンジン回転数を1,600r.p.m以上にしないという社内基準を設けており、チャート紙による確認が可能となっています。
乗務員は、終業時にチャート紙を提出する際に、自ずと結果を確認することになります。会社として常に全てのチャート紙を詳細にチェックしている訳ではありませんが、燃費が伸びない乗務員に対する指導などの際に、燃費の良い場合と悪い場合のチャート紙を比較して示すなどして役立てています。
|