|
(2)エコドライブのための実施体制
チェック項目
| (拡大画面:4KB) |
 |
解説
会社としてエコドライブを推進するため、エコドライブについての推進責任者を指名します。エコドライブ推進責任者には、運行管理者が任命されるのが一般的です。
チェック項目
| (拡大画面:10KB) |
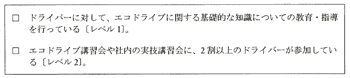 |
解説
エコドライブについては、ドライバーの日常的な実施を促すための教育や指導が必要です。エコドライブへの各取組内容の目的や効果は、次の通りです。
○急発進、急加速、急ブレーキを控える
急発進・急加速をすると、必要以上にエンジンの高回転域を使うことになり、通常の加速に比べて著しく燃費が悪化します。
○シフトアップを早めに行う
大型車が5速でなく4速、中・小型車が4速でなく3速というように、一段下のギアで走行したとすると、燃費はそれぞれ20〜40%も悪くなります。
○定速走行、経済速度の励行
一般道なら40〜50km/hで走行するのが経済的です。また、のろのろ運転やスピードの出し過ぎなど波状走行は10%以上燃費を悪くしますので、定速走行に努めます。
○エンジンブレーキを多用する(ディーゼル車)
ディーゼル車は、走行中にアクセルペダルの踏み込みをやめてエンジンブレーキの状態にすると、エンジンの燃料供給がカットされ無噴射状態となるので、この状態を多用すると燃費向上につながります。
フットブレーキのみの使用に比べて、エンジンブレーキを使用して停止した場合、一般的に大型車で1回当たり20〜25ccの燃料を節減できます。
これを、1日のブレーキ回数を600回として、さらに、年間に換算すると延べ18万回となり、燃料消費量としては3,600〜4,500l、金額として23.4〜29.3万円(65円/l)の節約となります。
○予知運転による停止・発進回数の抑制
交通状況や次の信号が変るタイミング等を予知することにより、停止・発進回数を抑制します。
○空ぶかしをしない
空ぶかし1回あたりの燃料消費量は、
| 大型車 |
中型車 |
小型車 |
| 10〜12cc |
5〜7cc |
3〜5cc |
|
例えば、燃料1lで大型車が約3km走行(1ccで3m走行)できると仮定すれば、大型車が1回空ぶかしすると、30〜36m走行分の燃料を無駄にしていることになります。
○アイドリングストップに心がける
アイドリング状態(大型車の場合450〜550r.p.m.)にある時の時間あたりの燃料消費量は、そのエンジン排気量の約10%程度です。つまり、排気量10lのエンジンならば、1時間のアイドリングで1l(1分間で約20cc程度)を消費することになります。
○タイヤの空気圧を適正にする
空気圧が100kPa(=1.0kgf/cm2)低いと燃費は約1.5%悪化するといわれます。
実験データから得られた空気圧と燃費の関係
| 空気圧 |
500kPa 5.0kgf/cm2 |
700kPa 7.0kgf/cm2 |
900kPa 9.0kgf/cm2 |
| 燃費(指数) |
97 |
100 |
102 |
|
|
| 車両:前2軸大型車、荷重:100%積載、速度:80km/h |
| タイヤ:11R22.5/14PR、平坦路直進定速走行(出典:ブリヂストン) |
○エアコンの設定温度を控えめにする
エアコン使用によりエンジンの回転数が高くなるため、結果として燃料の使用量が増加します。エアコンの使用は最小限度に心がけ、こまめに適正な温度に調整することが重要です。
参考:(社)全日本トラック協会発行「エコドライブ推進マニュアル」「環境基本行動計画推進マニュアル」
国土交通省「エコドライブ(10)のおすすめ」
西日本鉄道株式会社「乗務の手引き(運行マニュアル)」
注:トラックとバスの大中小型の区分について
トラックとバスでは、大中小型の区分は異なりますが、搭載されているエンジン等は共通する場合が多く、トラックにおける燃費消費量等のデータが参考となります。
エンジンの排気量は、トラックでもバスでも、
大型車は、概ね10リットル以上
中型車は、概ね5〜10リットル
小型車は、概ね7リットル以下
となっています。
自動車の大中小型の区分は、「道路運送車両法施行規則」により以下のように分けられます。
トラックの普通自動車と小型自動車は車両寸法で分けられ、普通自動車である大型車(ナンバープレートが大型)と中型車(ナンバープレートが小型)は重量で分けられます。
| 自動車の種別 |
全長×全幅×全高 |
重量 |
| 普通自動車 |
大型車 |
12m×2.5m×3.8m以内 |
車両総重量8t以上もしくは最大積載量5t以上 |
| 中型車 |
車両総重量8t未満かつ 最大積載量5t未満 |
| 小型自動車 |
4.7m×1.7m×2m以内 |
最大積載量概ね2t以下 |
|
バス(乗車定員が11人以上)の大中小型の区分は、以下のように分けられます。
なお、ナンバープレートは車両寸法に係わらず、乗車定員が30人以上の場合は大型になります。
| |
全長等 |
| 大型バス |
全長9m以上または旅客席数50人以上 |
| 中型バス |
大型・小型にあてはまらぬもの |
| 小型バス |
全長7m以下でかつ旅客席数29人以下 |
|
したがって、路線バス等で立席を設けて定員を増やしたものは、中型バスのシャシでも大型バスになり、小型バスのシャシでも中型バスとなります。
日常的に実施できる具体的な指導・教育としては、次のような例があります。
○ドライバー・車両毎の実施状況の確認・指導
・点呼時におけるドライバーごとのエコドライブ目標の確認
・エコドライブ運転の取組を確認する表を活用した確認・指導
・デジタコ活用による空ぶかし・運行速度の点検・指導
・点呼時のキー抜きロープの装着確認
エコドライブ運転確認表の例
| (拡大画面:17KB) |
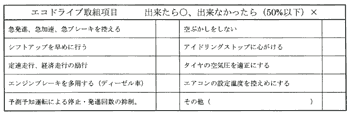 |
○職場巡回時等におけるチェック
・アイドリングストップの添乗指導
・職場巡回時のアイドリングストップの指導
・運行管理者による抜き打ちチェック・指導
○従業員への情報提供
・アイドリングによる燃費・経費の節減情報の伝達
・エコドライブ結果の社内報への掲載
・営業所別取組結果の公表
・省エネ資料・エコドライブ資料の配布
・営業所への啓発資料の提示
○従業員の取組への参加
・環境保護ステッカーの作成と車輌への貼付
・標語やポスターの募集やコンクールの実施
・エコドライブへの取組に関する提案制度の実施
上記の内容をはじめとして、(社)日本バス協会によって開催される「環境対策を強化する月間」に合わせた重点的な取組が進められています。
さらに、エコドライブの実効性をより高めるために、ディーラーやドライバー安全教育研修施設などで開催される実車での運転方法を体験する実技講習会に参加させたり、社外の研修で習得してきた内容を、社内で互いに確認し教えあう実技講習会を開催することが考えられます。
チェック項目
| (拡大画面:10KB) |
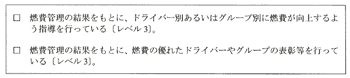 |
解説
エコドライブへの取組が一時的に終わることなく継続するように、ドライバー別あるいはグループ別の燃費管理の結果をもとに、日常の指導や教育に加えて、燃費の悪いドライバーやグループの指導、実技講習会への参加の促進など具体的な指導も必要です。
また、燃費の優れたドライバーやグループ、営業所に対して表彰等を行ったり、人事考課へエコドライブの取組結果を算入するなどにより、従業員の取組意欲を向上させることも必要になります。
|