|
第2章 グリーン経営認証制度の枠組み
単なる認証の実施に止まらず、指導、支援をあわせ行って、より実効ある取組みの推進を図るため、民間団体でかつ公正・中立であり、運輸交通に関わる環境改善の取組みにノウハウのある交通エコロジー・モビリティ財団が行うこととする。
認証にあたっての審査実務は、交通エコロジー・モビリティ財団及び同財団から委託(※)を受けた審査員が行い、審査結果に基づき同財団が認証合否を判定する。
(※)取組み内容を裏付けるための資料等について現場での確認が必要であり、全国的かつ膨大な業務量となるため、審査の実務を全国的規模での実施が可能なISO14001審査登録機関等への委託も行う。
| (拡大画面:54KB) |
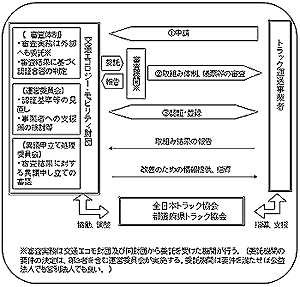 |
<認証取得までのフロー>
(1)申請
交通エコモ財団は事業者よりグリーン経営認証事業を運営するに必要な費用を認証手数料として受け取る。
(2)取組み体制、帳票等の審査
グリーン経営推進マニュアルに沿った取組状況等について、取組み体制、帳票等の審査を行う。
(3)認証・登録
審査結果に基づき、交通エコモ財団が認証の合否を判定する。
なお、審査結果等に対する異議申し立てについては異議申立て処理委員会で審査する。
環境と資源に対する改善の取組みを私的に認証する制度を調査し、検討の参考とした。また、グリーン経営認証制度の基本的な枠組みとISO14001認証制度との比較を行った。
(1)京都・環境マネジメントシステム・スタンダード 京都市の「京(みやこ)のアジェンダ21フォーラム」が中小企業向けの分かりやすい環境マネジメントシステム規格として、「京都・環境マネジメントシステム・スタンダード(KES)」を策定し、審査・認証を行う制度。
「エコステージ研究会」が環境マネジメントシステムを段階的に推進するために、5段階のステージを設定し、評価・認定する制度。
−KES、エコステージの比較表−
| |
KES |
エコステージ |
| 制定の背景 |
ISO14001は中小企業にとって経費負担や内容の高度さが障害となり取得が困難であることから、よりわかりやすく取組みやすい規格を制定。 |
中小企業にとり、ISO14001は経済的負担が大きく、また審査登録による合否判定のみではシステム及びパフォーマンスの継続的改善を推進する糸口がるかめないため。 |
| 認証段階* |
ステップ1: |
環境問題に取組み始めた段階 |
エコステージ1:重要なエッセンスのシステム構築・運用レベル |
| ステップ2: |
ISO14001 審査登録を目標にする段階 |
エコステージ2:ISO14001審査登録レベル |
| *エコステージでは『認定』と呼ぶ |
エコステージ3:システム改善が有効に行われている |
| エコステージ4:パフォーマンス改善が有効に行われている |
| エコステージ5:原価評価と情報開示が有効に行われている |
| 審査認証費 |
6〜20万円1年 |
20万円 |
| 認証有効期限 |
3年 |
| 認証の更新 |
認証登録後、1年後とに確認審査を受け更新 |
1年後ごとに定期評価があり。あつ3年目に更新評価を受ける |
| 認証の登録と証明 |
認証証の発行と登録リスト掲載、HPで開示 |
認定証の発行と登録知ると掲載、HPで開示 |
| 審査員の資格 |
ISO14001審査員補以上 |
ISO14001審査員補以上 審査登録機関との提携あり |
| 審査方法 |
書類審査、実地審査 |
書類審査、実地審査 |
| 導入コンサル |
有 |
有 |
| その他 |
認定企業のプレスリリースあり。またベンチマーキング情報を提供 |
認証実績
(14年7月現在) |
ステップ1:94社 |
エコステージ1:10社 |
| ステップ2:25社 |
エコステージ2:3社 |
|
(3)グリーン経営認証制度とISO14001認証制度との比較 グリーン経営認証制度は、指導、助言を含み、事業者の環境改善に対する自主的な取組みを審査する仕組みである。この点、事業者の環境マネジメントシステムが国際規格のISO14001へ適合しているかどうかを審査する、ISO14001の認証制度とは目的が異なる。
さらに、(財)日本適合性認定協会へヒヤリングしたところ、グリーン経営認証制度の原案であれば、ISO14001認証制度とのバッティングはないことを、確認している。
| |
グリーン経営認証制度 |
ISO14001 |
| 認証機関 |
交通エコモ財団 |
審査登録機関(現在33機関) |
| 認証機関の認定 |
なし |
日本適合性認定協会(JAB) |
| 対象企業 |
トラック運送事業者 |
あらゆる業種の企業 |
| 適用規格(基準) |
グリーン経営推進チェックリスト |
ISO14001(グローバルスタンダード) |
| 目的 |
環境改善への取組み確認 |
システムの適合性審査 |
| 環境パフォーマンス評価(EPE)との関係 |
認証基準の考え方に含む (ISO14031の環境パフォーマンス評価の考え方に則る) |
審査基準には含まず (ISO14031は指針であり、審査基準として使用されない) |
| 指導、助言 |
あり |
禁止 |
|
認証付与では、1段階とする方式と、“一つ星” “二つ星”のように複数の段階に分ける方法を比較検討した。
−検討案の比較−
| (拡大画面:53KB) |
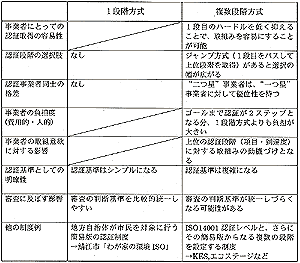 |
グリーン経営認証制度は、中小事業者が取組みやすい制度とするために、大幅に負担を軽減した認証基準を設定するものである。
複数段階方式には上記のように上位段階への動機づけとなるなどのメリットはあるものの、事業者の負担の少なさを考慮し、平易な内容の認証基準とすることを前提に、付与方式は1段階方式とする。
なお事業者の到達努力を高めるために、実績が積んだ段階で、優秀事業者の表彰制度や到達レベルに応じたランク付け等を運営委員会で検討していくこととする。
グリーン経営推進チェックリストの内容に基づき、認証の合否を判定するための基準を検討した。
1)大項目、小項目に対する基準設定の考え方
※大項目、小項目とは、「グリーン経営推進チェックリスト」の項目。
以下の複数案を検討した。
| 1案: |
すべての小項目に取組み、各小項目ごとに合格ラインとする到達度を定める(レベル1,2など)。 |
| 2案: |
大項目単位で合格ラインとする点数を定める。 |
| 3案: |
全体の総合計点数で合格ラインを定める。
―以上1〜3案の例を次ページに示した。 |
| 4案: |
定量的な達成度合いを認証基準に反映させる。
(例:低公害車導入率が○○%以上を達成していることなど) |
−各案の比較−
| |
メリット |
デメリット |
| 1案 |
事業者間の取組み項目にバラツキが生じない |
事業者が特定項目に経営資源を集中できる余地が少ない |
| 2案 |
事業者は、重点志向で特定項目に経営資源を集中できる |
事業者間の取組み状況にバラツキが生じる恐れがある |
| 3案 |
事業者は、より特定項目に経営資源を集中できる |
事業者間の取組み状況にバラツキが大きくなる恐れがある |
| 4案 |
事業者にとって、どこまで取組めばよいかがはっきりする |
事業者の自主的活動の制約(足枷)となる恐れがある |
|
| 1案: |
取組項目にバラツキが生じないため、認証基準として適している。 |
| 2案: |
事業者が特定項目に経営資源を集中できるというメリットがある一方、事業者間の取組状況にバラツキを生じる可能性がある。 |
| 3案: |
2案に同様である。 |
| 4案: |
「事業者の自主的な環境改善に対する取組を公正・中立な第3者の立場で評価し、取組意欲の向上を図る」というグリーン経営認証制度の考え方からすると、自主的活動の制約となることが懸念される。但し、目標値として客観性がある場合は基準設定もあり得る。 |
以上の検討から認証基準としては、全項目に最低限到達レベルを設定する方法に決定した。
なお、改善優秀事業者に対しては、表彰制度等の枠組みで考えることにする。
チェック結果 集計・評価表
| (拡大画面:62KB) |
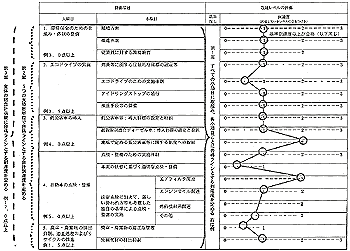 |
|