|
<講義要旨>
(1)はじめに
トラック運送事業者が環境保全活動を自主的に進めるための「グリーン経営推進マニュアル」を全日本トラック協会と協働して作成しました。
全日本トラック協会が定めた「環境基本行動計画」を実践していく際の支援ツールとして、マニュアルを活用されることが期待されます。
(2)グリーン経営の意味
グリーン経営とは、「環境に配慮した経営」であり、利益の追求と同時に企業の社会的責任として、環境問題にも積極的に取組んでいくことです。
(3)グリーン経営の位置付け
グリーン経営とは、ISO14001(環境マネジメントシステムに関する国際規格)認証の取得が難しい事業者にも、容易に環境保全を進めていただくためのものです。
○近年、環境保全活動を進める一つの方法として、ISO14001認証が注目されております。一部の事業者はISO14001認証を取得して、環境保全に対する自社の積極的な姿勢を社会にアピールしていますが、経済的、人的負担が大きい認証取得はなかなか容易ではありません。
(認証取得費用は、審査登録機関への申請費用やコンサルタント費用等の直接費用だけでも、およそ300万円程度必要です)
○グリーン経営推進マニュアルを活用することで、中小規模の事業者でも自社の経営規模に合わせて、環境改善に向けた取組みが容易になり、自主的で継続的な環境保全活動を行うことができます。
(4)グリーン経営が必要な背景
○地球温暖化問題や大気汚染問題等がますます深刻化しており、企業の社会的責任として、業界あげて対応を迫られております。特に、2002年3月、政府が定めた新たな「地球温暖化対策推進大綱」では、各業界における積極的な環境保全活動が強く求められており、運送事業者のグリーン経営の推進が運輸部門の重要な対策の一つとして位置づけられました。
<地球温暖化問題>
1999年度の我が国の部門別二酸化炭素排出量は、運輸部門が21.2%で、その中で営業用貨物車が16.7%を占めている。
<大気汚染問題>
大都市圏において排出される窒素酸化物(NOx)の52%、粒子状物質(PM)の43%は自動車部門からのものであり、そのうちNOxに関しては約8割が、PMに関しては全てがディーゼル車からの排出となっている。
○荷主側がトラック運送事業者を選定する上で、環境保全活動に取組んでいることを条件の一つとして考慮する企業が増えています。
(5)環境問題をめぐるビジネス化の動き
○二酸化炭素の排出権をめぐってのビジネスが本格化し始め、環境がビジネスに結びついてきております。このことは、環境問題に対応できない企業は、今後存続できなくなる時代を迎えつつあるとも言えます。
○最近の新聞や専門誌などで、ビジネス化の動きが頻繁に掲載されています。
(例)
・昨年10月、環境省が2003年度から地球温暖化防止対策の一環として自治体や家庭が削減した二酸化炭素排出量を年間百万トン程度買い上げる方針を打ち出す。(一種の社会実験として)
・昨年11月、東京都は、「都市と地球の温暖化阻止に関する基本方針」を策定し、都独自の温暖化対策として6つの挑戦を掲げた。その中の一つに、一定規模以上の事業所に対して、数値目標を定めた二酸化炭素の排出削減義務の導入の検討を始めた。
○長期的には前述の方向に行く可能性もあり、企業側としても、排出規制を新たなビジネスチャンスとしてとらえる発想の転換が求められています。
(6)グリーン経営の進め方
<グリーン経営の推進フロー>
| (拡大画面:9KB) |
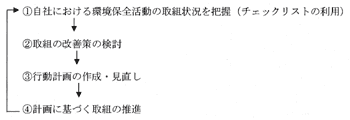 |
○グリーン経営は、チェックリストを用いて、自社の環境保全活動への取組状況を把握し、マニュアルを参考にして改善活動を進めるものであります。
○プラン、ドー、チェック、アクションのいわゆる、p−d−c−aのサイクルをまわすことによって、螺旋階段状に改善を図っていきます。
(7)グリーン経営推進マニュアルの特徴
○事業者が自主的、継続的に取り組めるもの
自己評価をもとにして取組みを見直しながら、活動を継続していく仕組みになっております。
○事業者が容易に取り組めるもの
中小規模の事業者でも容易に取組めるように、簡易でコンパクトなものとなっており、経営規模に応じた目標レベルの設定と取組みができます。
○環境改善の実効が期待できるもの
環境方針、推進体制、従業員教育等といった管理に関する項目は極力簡素化を図り、具体的に環境改善の実効が期待できるもの、取組み結果に対する客観的な評価ができるものにしてあります。
(8)グリーン経営推進項目(5つの大項目)と取組みのポイント
○環境保全のための仕組み・体制の整備
環境保全への取組みを進めるには、まず会社の方針を環境方針として示したうえで、取組みのための責任者等を明確にするとともに、従業員に対する環境教育を進めることが重要であります。
○エコドライブの実施
燃費の改善によるコスト削減や環境負荷の低減を図るためには、日頃から燃費管理を徹底して行い、それをもとに燃費の改善目標を設定することが必要であります。
更に、実際にエコドライブに取組むドライバーへの教育や指導、ドライバーがエコドライブに取組みやすいような装置や機器の導入も重要であります。
○低公害車の導入
自動車からの二酸化炭素や大気汚染物質を削減するためには、低公害車やディーゼル車の最新規制適合車を計画的に導入することが最も効果的であります。
○自動車の点検・整備
日常から車両の状況を把握し、整備を依頼する時にはその結果を伝えたり、法に定められた点検・整備の実施に加えて、会社として車両の使用状況に応じた独自の点検・整備基準を定めて整備を進めることが重要であります。
○廃車・廃棄物の排出抑制、適正処理及びリサイクルの推進
廃車に際しては、廃車自体を適切に行うとともに、廃車に伴う二次的公害の発生防止やリサイクルの推進等を図るため、廃棄物の処理やリサイクルを適切に実施している業者に委託することが重要であります。
(9)チェックリストの見方
○チェックリストには前述の大項目のもとに小項目があり、小項目の中に幾つかのチェック項目いわゆる評価項目が表示されています。
○チェック項目の後ろにカッコ付きで表示されているレベル数字は、そのチェック項目の取組みの難易度を表したものであります。レベル1からレベル3までの3段階で構成されており、チェックすることによって、自社の取組みのレベルが分かるようになっております。
<レベル設定の考え方>
| レベル1: |
法規制の遵守や一般的、基本的な取組みを意味しており、現状の把握なども含まれる。 |
| レベル2: |
積極的な取組みであり、目標の設定や計画の作成なども該当する。 |
| レベル3: |
先進的な取組みであり、取り組みの見直しを行う仕組みなども該当する。 |
○チェック結果を「チェック結果集計・評価表」に前回と今回のチェック結果を重ねて比較表示すると、今回の活動の成果が理解しやすくなります。
(10)当財団の取組支援
チェックした結果を当財団に送って頂くか、あるいは、当財団のホームページからチェック結果を入力して頂くと、改善に向けたアドバイスや情報提供等のサービスが無料で受けられます。
(11)今後の取組み
○第三者による認証制度の検討
マニュアルに基づいて環境保全の努力を行っていることを客観的に証明することによって、事業者さんの取組み意欲の向上につなげるとともに、トラック業界さんの環境問題への熱心な取組みを世に周知するツールとしても位置付けております。
現在、委員会で認証制度の仕組みや認証基準等について検討中であり、適用時期については、グリーン経営の普及の様子もみながら、全日本トラック協会とご相談して決定する予定です。
以上
|