|
評論記事 他
評論記事抜粋
(紙面の都合で、一部省略して掲載しています。)
| (拡大画面:196KB) |
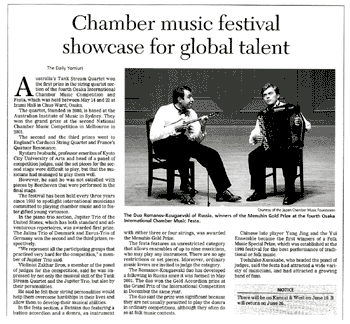 |
6月12日付 Daily Yomiuri新聞記事
大阪、中央区のいずみホールで5月14〜22日まで行われた第4回「大阪国際室内楽コンクール&フェスタ」の弦楽四重奏部門では、オーストラリアのタンク・ストリーム・クァルテットが優勝した。2000年に結成されたこのクァルテットは、シドニーのオーストラリア音楽学校に在籍している。同クァルテットは、2001年に第2回メルボルン国内室内楽コンクールでも優勝している。2位と3位は、イギリスのカルドゥッチ・ストリング・クァルテットとフランスのレゾナンス四重奏団が獲得した。
京都市立芸術大学名誉教授で、審査委員長の岩淵龍太郎教授は、2次予選の課題曲は困難なものであったが、演奏者は上手く演奏することが出来ていたとコメント。しかしながら、同氏は、本選での課題曲であった、ベートーヴェンの演奏には満足していないと敢えて注文をつけ、更に向上されることを願っているとコメントした。
この音楽祭は室内楽の演奏家と若手の演奏家を育てることにスポットライトをあてるために1993年より3年ごとに開催されている。
ピアノトリオ部門では、スタンダードでかつチャレンジングなレパートリーを得意とする、アメリカのジュピター・トリオが1位を獲得した。デンマークのジャリナ・トリオとドイツのオイルス・トリオがそれぞれ2位と3位を獲得。
ジュピター・トリオは、「私たちはコンクールに向けて、一生懸命練習した参加グループの代表です。」とコメントした。
コンクールの審査委員メンバーである、ヴァイオリン奏者のザハル・ブロン氏は、タンク・ストリーム・クァルテットとジュピター・トリオの音楽技能だけでなく、彼らの人柄に感動したと言う。同氏は、彼らの強い人柄が、彼らの人生の中での困難に打ち勝つ助けとなり、彼らの音楽の才能を発展させるだろうとも言う。
フェスタ部門では、3弦の撥弦楽器であるドームラとバヤン(ボタンアコーディオン)を演奏する、ロシアのデュオがメニューイン金賞を受賞。フェスタは、2人から9人までの編成で演奏されるグループであれば、楽器の組み合わせは自由とするというもの。年齢制限や課題曲はなく、その上、一般の音楽愛好家100名によって審査される。
デュオ・ロマノフ・クガエフスキーは、2001年5月の結成以来、ロシアで力を伸ばしてきている。同年12月、デュオは国際コンクールでゴールド・アコーディオン賞を受賞。一般のコンクールではドームラを演奏することが出来ないため、今回の賞は素晴らしいものだと言っていた。
中国の琵琶奏者、楊静と結アンサンブルは1999年に設立された団体で、特に伝統音楽・民俗音楽に優れた団体に与えられるフォークロア特別賞を受賞した。
フェスタ審査員長の日下部吉彦氏は、フェスタ部門は多岐に渡る演奏家を魅了し、また同時に増え続けるファンをも魅了したとコメントする。
大阪日日新聞5月27日
齋藤架奈枝
第四回「大阪国際室内楽コンクール&フェスタ」(日本室内楽振興財団主催)が九日間の会期を終え、二十二日に閉幕した。最終日に行われた会見では、レベルの高い演奏で腕を競い合った各部門の受賞団体が受賞の喜びを語った。
第四回となる同コンクール&フェスタは、一九九三年から三年ごとに大阪で開かれ、これまでに世界四十カ国から百八十四団体、六百五十七人が参加してきた。
今回はコンクール部門に、十カ国から十八団体六十二人、フェスタ部門に十二カ国から二十二団体七十七人が参加。予選、本選と駒を進め、特別賞も含めて計十一団体が受賞した。
コンクール第一部門(弦楽四重奏)の第一位を受賞したタンク・ストリーム・クァルテット(オーストラリア)は、A.ベルクの難曲を見事に演奏したことなどが評価された。初参加となる国際コンクールでの初受賞に、「優勝するなんて夢にも思っていなかった。日本で演奏でき、いい経験になった」と挨拶した。
コンクール第二部門(ピアノ三重奏)の第一位、ジュピター・トリオ(アメリカ)は「私たちの編成が対象になるコンクールはめずらしく貴重。熱心に練習を重ねて参加した、すべてのグループの代表という気持ちで賞をいただきました」と、謙そんしながら受賞を喜んだ。
年齢制限や課題曲、楽器の指定がない一風変わったコンクールとして注目される、フェスタ部門のメニューイン金賞は「デュオ・ロマノフ・クガエフスキー」(ロシア)。バヤン(ボタンアコーディオン)とドームラでの楽しい演奏が評価された。
日下部吉彦フェスタ審査員長は、「バラエティー豊かなグループが増え、ユニークなフェスタ部門の意味合いが正しく定着してきたという手ごたえを感じた。素直に感じるままに採点していた百人の聴衆審査が、そのまま票に表れた」と総評した。
音楽の友 7月号
渡辺和
大阪ビジネスパークを舞台に3年に1度開催される〈大阪国際室内楽コンクール〉の室内楽専門コンクールとしての最大の特徴は、〈フェスタ〉と呼ばれる世界に類例のない音楽の祭りと並行開催される点にある。若干無謀な「音楽をランク付ける」という行為を、「聴衆に与える喜び」と「専門家が判断する完成度や将来性」とに分離するこの大阪方式、世界のコンクール関係者が意義と意味を真剣に考えるに値する実験となりつつある。
コンクール第1部門弦楽四重奏
招聘された6カ国8団体から、1次予選突破5団体、本選出場は4団体。優勝タンクストリームQ(豪)、2位カルドゥッチQ(英)、3位レゾナンスQ(仏)。このジャンル、今回は応募時点から参加団体が少なく日本の団体は皆無。国際コンクールの常連や、その逆に大阪見物がてらの参加という団体もなく、フレッシュな顔ぶれが並ぶ。世界的に当ジャンルの若手が端境期である昨今、世界の音楽産業中心地からの距離の隔たりを思うに、コンクールとすれば健闘と言えよう。
上位2団体は安定した演奏を重ねた。特に優勝したオーストラリアの団体は、古典の解釈の勉強が今後の課題とはいえ、資質の良さが光る。その一方、全体のレベルは高いものの、過去3回までのような傑出した強さを発揮する団体がなかったことも事実。特に本選課題曲の内ベートーヴェンの作品では、どの団体も決して満足いく成果を示せなかった。審査委員長を兼ねる岩淵龍太郎芸術監督は、表彰式の講評で、あえて正直にベートーヴェン演奏の細部に立ち入った技術的注文を付けた。同氏によれば、それでも1位なしとしなかったのは、2次予選での「抒情組曲」の演奏がコンクール優勝レベルに達していたから、とのことである。無責任な聴衆からすれば、ファイナリストに残ったモスクワのツインズQが群を抜いて面白かった。
コンクール第2部門ピアノ三重奏
第2部門は今回から大きく規約が改定された。過去の「弦楽四重奏以外の室内楽」から、ピアノ三重奏に絞られたのである。コンクールとしては世界にも約10年に1度のミュンヘンや、4年に1度のメルボルンの他の専門コンクールがないジャンルだけに、応募団体も多く活気がある。参加が許され招聘された7カ国9団体が熱演を繰り広げる。結果、優勝はアメリカのジュピター・トリオ、2位デンマークのジャリナ・トリオ、3位にはドイツのオイルス・トリオ。優勝団体の完成度の高さ、2位のロマン派作品の把握力など、聴きどころは多い。3位団体のピアニスト、ティナティン・ガンバシゼは、室内楽奏者としての大成を予感させられた。
が、活気と大会運営は別物。この分野、やはり運営が難しい。ピアニストとすれば、本番ピアノでの練習や、ピアノ指定での試し弾きがほとんど出来ないのは、会場の都合とはいえ辛かろう。
なお、今回からは予選で敗退した団体も、その後数日は大会経費で大阪に滞在が許され、他の参加者の演奏が聴けるようになった。また、非公式ながら参加者が審査員の講評を受けるチャンスも与えられた。徐々にではあるが、イヴェントから教育機関への改良が成されつつあるのは評価すべき。
審査員として初参加した元スメタナQのシュカンパ氏が積極的に参加者に説明する姿と、それを見守る岩淵氏の好々爺ぶりが印象的だった。
|