| (拡大画面:25KB) |
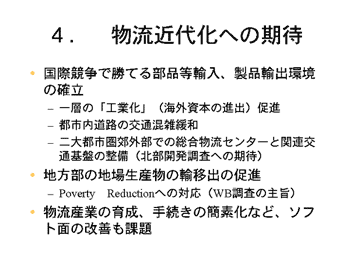 |
それから最後に、「物流近代化への期待」と書きました。国際競争で勝てる部品等の輸入、あるいは製品輸出環境の確立ということが一つ大きなテーマとして言えるのではないかと。工業化の推進のためには、やはりこういったことがないとこれ以上、海外の資本進出が進まないという認識がヴィエトナム政府にもかなりありまして、大いに関心がある。
都市内道路の交通混雑の緩和。これが私のいるTDSI、その隣にある道路標識ですが、現在、環状2号線内はこのように規制されています。2.5トン車以上は、22時から5時しか入れません。それから1.5トンから2.5トンは19時から7時まで。1.5トン車以下でも、7時から9時、夕刻4時から6時はだめということです。3段階に分けて、かつ、この時間帯は一切のトラックはだめ。中には許可を持って入っているのもあります。これをやっても混みますので、逆にすぐこちらの道路は、私の部屋の窓のすぐ外側になるんですけれども、大型車混入率がほんとに多くなっています。
二大都市圏郊外部で総合物流センターというものをつくって、あわせて関連交通基盤を整備するというのが非常に重要になってきているのではないかと、特に北部では開発調査への期待が高まっています。
それから、世銀が物流調査をしたのですが、地方部の地場生産物の輸移出を促進して、貧困撲滅に貢献しましょうということで、また後で説明します。
物流産業というのはもともとない、育成が必要です。手続の簡素化などソフト面の改善、もちろんこれは簡素化のみではなくて、税関手続に際してのいわゆるティーマネーをなくすとか、そういった費用に絡むことももちろんまだまだ不十分ですので期待されています。
これはハノイマスタープラン、2000年の交通計画ですけれども、後で時間があれば使います。
最近のトピックとして2つ。世銀の物流調査の報告会というのが4月にございました。野村総研が請け負っていろいろ提言しているのですが、その中でタイの鉄道コンテナ輸送が注目されました。内容としてはバンコクの外港ラムチャバン港、百数十キロありますけれども、そこからバンコク郊外のラットクラバンIC、この間110キロ。ラットクラバンというのは、バンコクから二、三十キロ郊外、20キロぐらいですか。大きいIC(インランドコンテナデポ)ですので、この間が保税輸送される。そのコンテナが非常に多く、ここに載せていませんけれども、最近ではバンコク港よりもはるかにこちらのラムチャバン港ほうが多い。そして海上コンテナ輸送の半分超が鉄道輸送されているのです。
| (拡大画面:157KB) |
 |
同区間内に2本の高速道路、ハイウエーとエクスプレスウエーかと思います。この鉄道はメーターゲージで一部、確か半分ぐらい単線です。新たに線路をつくったのはわずかですけれども、しっかりシステムをつくったので海上コンテナの半分ぐらいは運べているということです。
ハノイーハイフォン間が110キロです。現在は、国道5号線、4車線から6車線です。今のところはまだそんなに混んでいませんが、この国道5号線の沿線開発は非常に進んでいますし、ハノイとの間は大動脈ですから、さらに貨物、あるいは人の輸送も含めて急激に伸びていくだろう。やはり早晩かなり深刻な状態になるのではないかと。そういう意味で、鉄道のハイフォン線について、まだメーターゲージ単線ですけれども、余裕がありますので、最小限の投資で旅客、貨物とももっと輸送できるような体制をつくるのがいいのではないかと思っております。
これは日系企業、実はハノイにあるタンロン工業団地に進出した企業ですが、ここに書いてあると問題かもしれませんが、これはTOTOです。先ほど言った中国に2つ工場をつくって、3つ目にハノイを選んだ。今、もう工場をつくり始めています。進出した一つの要因としては、標準ゲージの線路が、ハノイ駅ではないですが、ハノイ市内からずっと国境まで行ってそのまま中国につながっている。今でも北京まで週に1便か2便、旅客便が何日かかけて行くのがありますけれども、その標準ゲージを使って製品輸送をしたいというのが要望でありまして、ぜひこれを工業団地の関係者も一緒になってやってくれということで話が上がっております。これは私ども TDSI の副所長が直接話を聞きたいということで、こっちに来る前に工業団地関係者と話をして、ヴィエトナムの運輸省関係者も非常に興味を持っているというところで、実現に向けた何らかの動きをして頂けるものと思っています。
| (拡大画面:29KB) |
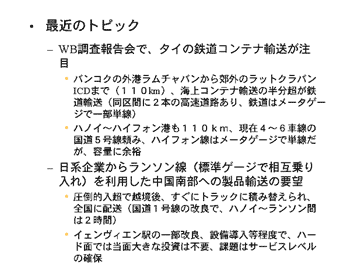 |
このランソン線というのは、国境の町はドンダンですが、圧倒的に入超で10対1ぐらいの割合でした。越境後、中国から入ってきたものはすぐそばの、ランソン駅かドンダン駅で−ランソン駅だと思いましたけれども、トラックに積みかえられてほとんどがトラック輸送されます。これは国道1号線が国境まで通りまして、ハノイ−ランソン間が乗用車で2時間切るぐらいの非常に快適な道路ができました。
鉄道は、初めハノイあたりまで来ていたのですが、トラックのほうが早くて安い、値段的にも競争にならないというので、駅長さんは嘆いていました。でも自分には打つ手がないと。ですから、鉄道がもう少し考えて何かすればいいんですが、それに対応する案がまだ組織としてできないというのです。日系企業のほうとしては、物流関係業者も一緒に見て、イエンビエン駅を一部改良して、クレーンなどを常設する程度でかなり運べるだろうと。あとはサービスレベルをちゃんと確保できる、そういった態勢ができるかどうかじゃないですかというようなお話をしていました。
まずは最小限の投資でできるのだから、中国政府、中国の国鉄にも働きかけて、そういうような輸送の手続面、あるいは何かお互いにインフラで最低限の投資をしてこれを実現させましょうというようなことを、政府がその気になってくれれば次のステップとして少し大きな投資もあり得るのかなと思います。
最後に私が最近提案していることですが、ハノイ環状線兼国道1号線、タインチ橋がございます。さっきの赤い図面は大分戻りましたか。タインチ橋がこれです。今ここをつくっていて、これが1号線バイパス兼環状3号線です。道路がここまでできていまして、今度はこちらが国道1号線のメーンになります。ここから、こういうふうに交通が入っています。今まさにこういう道路を発注しているところだと思います。国道5号線はここです。現在この道路は片側1車線ですけれども、将来は2車線が4車線になりますが、もうできております。ここを結べば、市内に入らずにそのままさっき言ったランソンまで行ける、ハイフォン港はここを通れば行けるということで、ここは今後、非常に交通の便がいい、この辺(国道5号線と1号線の交差点付近)は既に土地の値段が上がっているそうですけれども、物流拠点として大きなポテンシャルを持つことになります。
これはマスタープランですけれども、ここの黒い線、これは鉄道ですので、バイパスと同じところに鉄道が通る計画になっていまして、私もこれを見て気づいたのですけれども、幾つかあるこういう図面で全部通ることになっているのですけれども、実際この橋は6車線対応の道路橋として設計されていて、鉄道は通れません。
| (拡大画面:111KB) |
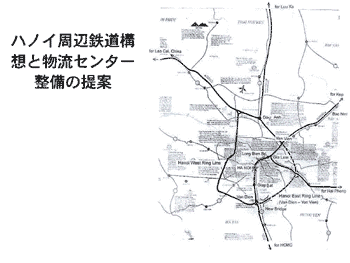 |
私が言っているのは、この紅河の外(北東)側、橋を越えたところぐらい、こちら(内側)はもう大分土地の値段が上がっているけど、この辺(外側)はまだそんなに上がっていない、田んぼが多いということ、一方こちら(内側)には貯水池もあるので、この辺(外側)に土地を確保して、物流センターをつくったらどうかというのを、いろいろなところに提案しているところです。
これがハノイ駅です。鉄道はホーチミンのほうから来て、さっき言ったラオカイにはこう行きます。こっちが八イフォンです。これがタンロンブリッジで、タンロン工業団地はこの辺です。これはかなり前にできまして、ほとんど使われていない環状線の一部(西環状線)。あと、ここの部分(イエンビエンからバンディエンまで、東側の部分)をつくれば環状線になって、これ(現在のイエンビエンからハノイ経由バンディエンまでの南北線)がちょうど(環状線を南北に)突っ切る形になるのです。最初これを考えたときは、さっきの橋(タインチ橋)に一緒に(鉄道橋を)つくれれば一番いいと思ったのですが、それはできないということでした。ハイフォンのほうから来た鉄道は、ここのロンビエン橋、フランスがつくった古い鉄道橋で、100年以上たっていますが、これを改良して、かつこの辺の民地を買収してどかして、それで複線の用地をつくってからでないと、ここを一部改良しても意味がないというのがございますので、それだったら、むしろこう来て(5号線と1号線バイパスの交差点より少し南側からハイフォン線が分岐する形で、1号線バイパスに並行して環状鉄道を整備して、ハノイ市街地へは)南から入って、南のほうに新たに駅をつくる、この辺(ハノイ駅の南のザップバット駅より南側)は道路に余裕がありますので、平面のまま複線化することもできます。
ですから、最初の発想は、こういう旅客ルートを新たにつくれば、ハイフォンから来たものはここ(ザップバット駅)にとまる、南から来てもここでとめてしまう。ここに、ザップバットという結構大きな貨物駅があって、それなりに扱っています。これの機能をもっと南、またはこの辺(東に)移す。この辺に環状3号線が走りますので、その間に貨物の駅をICDの機能と含めてつくってしまえば、ザップバット駅は旅客駅に転用できる。こっちから来た貨物もそこに運べるということで、こちらのほう(ハイフォン線からイエンビエン方面の環状鉄道)は後でもいいんです。大体これ(イエンビエンからバンビエン)が15キロ強ぐらい、これ(環状鉄道線)を1周すると90キロぐらいになります。山手線が35キロですからかなり大きいんですが、これを旅客に使うというのは遠い将来はあってもしばらくはないと思いますので、これは基本的に貨物に使う。そうすれば、ここはゆっくり都市内鉄道としても活用、転換を図れると考えました。
その後、さっき言いましたこの道路ができることと、貨物のICD機能が100キロぐらいでもハイフォンからの保税貨物を鉄道で扱って十分やっていける可能性があるということがわかりましたので、これ(物流センター候補地)は図面は載っていませんけれども、さっき言いましたように、最初は道路を利用したICD、将来はこれ(鉄道)を延ばして、これ(ICD)まで引き込み線をつくればいいわけですから、鉄道も使える。それをさらにここまで延ばせば、旅客もこう入って、ザップバットの駅あたりに本格的な旅客ターミナルをつくって、この区間は例えば都電的な利用にしてしまうとか、そうすれば、ヴィエトナム政府がなかなかできないであろう沿線住民の移転とか、そういったことも待たずして、鉄道のプロジェクトとしては可能なのではないかと思った次第です。
最後はちょっと雑駁といいますか、飛び飛びになりましたけれども、私が最近言っていることも含めてお話しさせていただきました。どうもありがとうございました。(拍手)
|