| (拡大画面:24KB) |
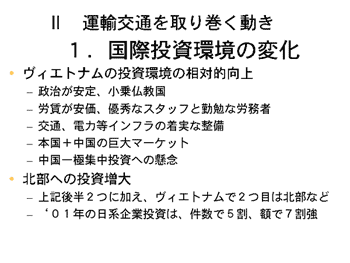 |
続きまして、運輸交通を取り巻く最近の動きということで、もうご存じの方も多いかもしれませんが、国際投資環境の変化がヴィエトナムにプラスになっているという意味でここに書かせていただいています。「ヴィエトナムの投資環境の相対的向上」、この相対的という意味は、特に去年9月11日のあの事件以降、ヴィエトナムが東南アジアの中で見直されてきているということ。政治は社会主義ですがイデオロギーというもので問題があるというわけではなくて、むしろ安定しているところが買いだと。それから小乗仏教国で、特に日本から見た場合には慣習的にも非常に共通点が多いので入っていきやすい。それから宗教心が弱いといいますか、日本と同じように、あんまり宗教心というものを感じない国でありますので、そういったことも非常になじみやすい。労働者については、労賃がまだまだ安価である。現地スタッフを採用すれば、もちろん優秀な人間を雇うことができますし、労務者も基本的には勤勉であるということ。交通関係インフラ、電力等の経済インフラ、そういったものが着実に整備されてきているということ。それからヴィエトナム本国は7,000万人強の人口ですが、それが成長しつつあるということと、隣接して10数億人の中国の巨大マーケットがあるということで、より北部のほうに言えるのですが、その点、マーケットは大きいものがある。
もう一つは、中国が巨大マーケットだということで中国に投資すればいいじゃないかということに対して、ここ二、三日、あるいはきょうの新聞でしたか、多くの企業が東南アジアを引き揚げて中国に移転すると書いてありました。あの中にはヴィエトナムは入っていませんでしたので、もっと早くから企業が進出している別の東南アジアの国が多いみたいですけれども、逆にそれだけ皆さんが行くと、中国に2つも3つも工場を持つということが果たして会社にとっていいことなのかということも考えるようになります。ある会社は初め北京に進出して、中国を全部カバーして、そのうちよくなってきたので、だんだん南に行って上海に第2工場をつくる。第3工場をもっと南につくろうかと思ったけれども、3つ目までつくるのはかえって危ないんじゃないか、もし中国が何か政策変更をしたら、会社そのものが成り立たなくなる可能性があるというような意見もあり、南を見たらハノイがあって、ハノイの工業団地を見にいったら、ハノイから中国へのルートもあるようだということで、3番目はハノイにしたというようなことを聞いております。中国に対するそういう懸念というのを、ほかの企業でも持っているということで、こういったことが重なり合ってヴィエトナムが非常に見直されつつある。相対的に苦しい中ではヴィエトナムはいいと。特に北部は今言ったこの2つの理由に、もう一つ、ヴィエトナムで南部に工場を持っていて、2つ目は北部につくりましょうという企業もあるそうです。
資料を持ってこなかったので正確な数字は持っていないのですが、JETROヴィエトナムの報告書に詳しく載っていますが、日本の企業の投資は昨年、件数で南と北が5割ずつだと。ところが、北のほうは大型案件が二、三あったので額では7割強。多分間違いないと思いますけれども、大体7割強ぐらいで北が多かったということで、これは初めてです。今までずっと南のほうが多かったですから、それだけ北が注目されているということが言えるかと思います。
| (拡大画面:29KB) |
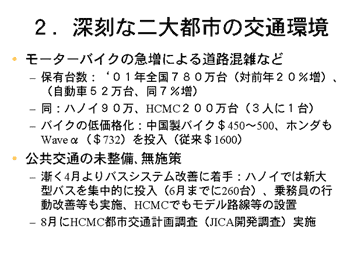 |
それから、今一番問題なのは、ハノイとホーチミンの交通環境の悪化で、一つは道路混雑、あるいは非常に排気ガスが多くなって健康問題にもなりかけているというようなこともあります。もう一つは交通事故が非常に増えている。最大原因はモーターバイクの急増で、保有台数が昨年、全国780万台、人口が七千七、八百万人ですから、ちょうど10人に1台になりました。対前年20%増えました。それに比べて自動車は52万台で7%増です。こちらのほうは非常に税金が高い。関税その他で200%を超える税金がかかると言われておりますので、カローラが大体350万円ぐらいすると言われておりますから、幸いにして自動車の値段が高いのでまだ増えていません。このままバイクが自動車にかわっていったら、もう手がつけられない状態になるだろうなというのが関係者の一致した意見であります。ですから自動車ついては、今のところは普及させようという動きはありません。
ハノイでバイクはどのくらいかというと、大体90万台と言われているわけです。100万台という声がありますけれども、統計上は90万台ぐらい。ホーチミンが200万台。この数字もはっきりしませんけれども、両市とも大体3人に1台ぐらいです。ハノイの人口が二百六、七十万人ぐらいになっています。3人に1台ということは、4人5人家族が多いですから、各家庭2台の時代に入っている。そういう意味では、人口が増加していますから今後も増えるでしょうけれども、毎年20%も増えることはもうないのではないかとは私は思っております。
ただ、まだ安いバイクがどんどん供給されていますので、まだ今後増えるだろう。これだけ急増したのは、所得の向上と同時にバイクのほうの値が下がってきた。特にこの二、三年で500ドル前後の中国製バイクが入ってきている。500ドルというのは、今、ホーチミンの1人当たりGDPが大体1,000ドルちょっとだと言われております。ハノイがどれぐらいかわかりませんけれども、全国平均が400ドルぐらいですから、ハノイはおそらく600ドルとか、700ドルぐらいでしょう。それよりも安いということで、かなりの人が買える値段になった。
ホンダは今まで1,600ドルぐらいで、多少これより安く売っているかもしれませんけれども、この1月からWAVEαという半額以下の安いバイクを始めました。これがまた非常に売れておりましてなかなか手に入らない。二、三日前の日本の新聞にも載りましたけれども、今度、これをフィリピンに輸出するということで、ノックダウン輸出だそうですけれども、注文がまだ追いついていないのに輸出するということを決めて、それだけ生産に力を入れているということだと思うのですが、110ccのバイクが今、非常に人気がある。ヤマハとかほかの会社も安いバイクを投入するということで、こういうのを見ているとかなり普及はしているのですけれども、まだ増える。
一方、バイクのおかげで今までの公共交通としてのバスがどんどん衰退していって、無策と書きましたけれども、何もしないのではなくてそれを減らしてしまうという意味では無策以下だったのかもしれません。バスが衰退して、バイクを持たない人はほとんど公共交通と呼べないようなバスを使っていたのはつい最近までの現実。
最近、バスシステムの改革に着手しまして、ハノイでは新型バスを投入し始めました。記憶に間違いがなければ、4月から6月までに260台の新型バスを入れるということで、これが新しいバスです。これはロンビエンブリッジのすぐそばのところで撮ったんですが、韓国製のバス、大分人が多かったんですけれども、大型バスでエアコンつきで、私が帰ってくる前、暑くなってきたせいもあるんでしょうけれども、乗車率も相当上がっていました。今までのおんぼろバスに比べれば、台数も増やして、大型になったのですけれども、それ以上に乗車率もよくなっていますので少し努力が実ってきたかなと思います。ちなみにこの車(ヒュンダイの小型車)が今100万円ぐらいで売っていますが、思ったより普及は遅いです。増えてはいます。
それと乗務員の行動改善と書きました。聞いていますと、バスの悪いところの一つは、どこでも客を乗せて、どこでも降ろしているのです。これはドイツ人の専門家に聞いたのですけれども、バスに乗務員と運転手が乗っていて、基本的には現金ですけれども、ひどい人は現金を半分ぐらい懐に入れているらしいのです。地元の人に聞いたのですけれども、途中で乗せた人は少なくとも全部懐に入れているといううわさでした。そういうことをしているので、非常に信頼性がない。いっぱいになると、おりる人がいなければバス停を通過するとか、要は公共バスシステムとしての体をなしていないというのに近かったのです。
そういうのをやめさせようということで、モデル的に4月より前から実施して、それを踏まえて新しいバスの導入と同時にそういうことを本格的に始めたらしく、バス停で待っていればちゃんと来るようになった、あとは、時間どおり、あるいは時間どおりに来なくても、15分とか20分ぐらい待てば来ると。ご存じのようにヴィエトナム人は、「待つ」とか「歩く」というのはあまり得意じゃない国民ですので、時間どおりに来ないとか、本数が少ないと乗車率が落ちるということを、ドイツ人の専門家は厳しく指摘したらしいです。
ホーチミンでもモデル路線というのを始めているというのを新聞で見ましたので、同じような試みをされているみたいです。ちなみにホーチミンの方が公共バスの程度はハノイよりいいようです。公共交通については、ホーチミンは8月に都市交通計画調査を、名前はこのとおりかわかりませんけれども、実施ということで、8月20日ぐらいに本格調査団が来られることが決まっています。この中でも5カ年のアクションプログラムをつくって、まずは幾つかのシステムを試みながらバスをしっかり確立していこうというのが最大の目標になっております。それが事前調査での方針で、ヴィエトナム政府も同意しておりました。それがなければ、次の地下鉄とか、ライトレールとかといっても、そもそもモーターバイクをやめてもらって公共交通に転換してもらうというところから始めなければ怖くて次の大きな投資はできない、これは間違いないだろうと言われています。それはヴィエトナムのMOTの人、それから人民委員会の人も言っておりました。同じような状況はハノイにもあります。
これはほかの発表に使ったスライドですが、何が悪いかといったら、こういう路上駐車、歩道がモーターバイク置き場になっている、そのおかげで歩行者はここを歩かなければいけないということも一つの問題ですが、それ以上に、遅い車は歩道側、早い車が中央側というキープライト、日本ですとキープレフトの原則が守られていないというのは大きな問題ということでこれを発表しました。
これはバイクが歩道をふさいでいるので、荷物を担いだおばちゃんも普通の歩行者もみんな車道を歩く。だんだんと車道が狭くなって交通困難な道になっている。まずは歩道をちゃんとあけましょうと。これは歩行者が歩いて、モーターバイクがこれでは、車はどこを通るのだろうと。これはハノイでも一番の交通混雑路線で、郊外のベッドタウンから来る人の多くはここを通ります。一応、分離帯は可変になっていますけれども、ここに基幹バスを走らせたいということで、基幹バスを走らせるにはここを整備してバイクの路線と車を分けて、こっちはバス、中央寄りをバス優先レーンにするとか、そういうことをやるのでしょうけれども道は遠い、しっかりやらないとだめですということを言うためにこれを使いました。
これは実は金を取ってモーターバイクの駐車を管理しています。もう歩道がふさがれて、これはひどいですねと。場所がないので、ある程度こういうことをやらなければいけませんが、歩行者の歩けるスペースは空けなければいけませんということです。
これは、モーターバイクを置く道路ですけれども、この奥に市があります。市場の前だけをこういうふうにしていますけれども、思い切って、市場がないところでも小さい道路をつぶして全部モーターバイク置き場にして、幹線道路がスムーズになるように、そういったことも一つの方法でしょう。この人が駐車場を管理してお金を取っている、チョークでここに書いて。こういうことは公共が自らやってはいけません、地元の人に任せて、公共はここからスペースに応じた料金を定期的に取るということに徹すればお金がかからなくて、地元の人を代表に決めて、集金させて、それは商店街とか、あるいは沿線の人たちの収入にも一部するというようなことで、公共の負担にならないようなことを考えたらどうですかと。
これは先ほど説明したとおりです。これを見ても、交通ルールというのを守らせるのはなかなか大変だなと。交差点ですけれども、この人もまさにここを渡ろうとしているんです。私も朝いつもここを通るのですけれども、ここの交差点はすごいです。とても日本人の運転では渡れません。
「交通安全対策が急務」と書きました。昨年全国死亡者が1万人を超えました。前年比40%増ということで、今一番問題になっています。7割ぐらいがバイク関連です。事故原因の6割がスピード違反と追い越し違反、要はバイクに乗っている人のモラルというか、マナー以前で、ルールを守るということが一番欠けている。簡単に免許を取れ過ぎる、自転車のつもりで乗っている、高校生は乗っちゃいけないといいますけれども、中には中学生ぐらいのバイクに乗っている人間も時々見られますので、その辺の取り締まりもしていない、などと言い出したら切りがないぐらいに、我々の目から見たらモーターバイク交通には問題があります。今、首相の一番の関心事だということで会議がたびたび開かれているようで、いろいろ対策を実施しています。
| (拡大画面:28KB) |
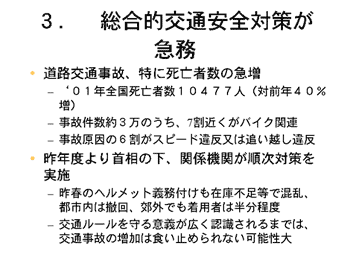 |
ちょっと前になりますけれども、ヘルメットの義務づけもしたのですけれども、うわさによると、在庫不足でヘルメットの値段が上がってどうしようもなくなったということで1カ月でやめてしまいました。その後、都市内は被らなくてもいい、郊外は着用しなければいけないようになっているけれども、郊外でも半分程度しか着用していません。市内はほとんど着用していない。ヘルメットを着用していると、格好悪いのに何でつけているのと言われるぐらいだと言われていますので、その辺からやらないとなかなか死亡者も減らないし、事故も減らないだろうなと。といっても、何かやらなければいけないので、これも非常に重要なテーマになっています。
|