|
平成14年度 運輸国際協力セミナー
第2回 (平成14年7月25日)
【司会(男竹理事)】 ただいまから第2回JTCA運輸国際協力セミナーを始めたいと思います。本日は、お忙しい中、また暑い中、参加頂きましてありがとうございます。
本日のセミナーは、昨年3月以来、国土交通省から出向してJICA専門家としてヴィエトナム運輸省に派遣されてご活躍中の大津専門家が、休暇で日本へ戻られたので、ヴィエトナムの運輸交通事情についてお話をしていただく機会を設けました。既に大津専門家とご面識のある方も多いかと思いますけれども、来年3月までハノイで引き続きご活躍の予定でございます。きょうのお話を伺って、さらにヴィエトナムの運輸事情に精通され、国際協力案件の獲得の促進に参考にしていただければと思います。
大津専門家をご紹介いたします。
【大津】 昨年3月から2年間ということでヴィエトナム国の運輸交通省交通開発戦略研究所というところにJICA専門家として派遣されております大津でございます。
今回時帰国する1週間ぐらい前に、もしできれば皆さんの前で最近のヴィエトナムの運輸交通事情といったようなテーマで少しお話をしていただきたいということがございまして、言訳をさせていただきますけれども、私も来る直前にばたばたとセミナーをやった関係で若干準備が十分でないということもございまして、資料は十分ではございませんけれども、とりあえずコンピューターの中にあるデータとか、若干の手持ちの資料、あとは私の頭の中に入っていることを本日こういう形で最近のトピック等を交えながらご紹介させていただきます。後に皆さんご質問を受けながら、私の知っている範囲でお答えして、最近の事情についてよりこ理解をいただければと思っております。
私の派遣先のTDSI、交通開発戦略研究所、Transport Development & Strategy Instituteというところは総勢70名強の組織でございまして、北にあるのですが、南にもTDSI Southという組織がございまして、今度ホーチミンの都市交通調査をやるときにTDSIがカウンターパートですが、実質的にはTDSI−Sがなります。またご存じのJICAのスタディー、VITRANSSというものが2000年7月、まとまりましたけれども、この調査のときもカウンターパートで活躍いたしましたのでご存じの方も多いかと思います。
今一番の問題なのは都市交通ということで、都市の公共交通の普及とか、あるいは一体何から始めたらいいかというようなことが議論されております。相談があればそのときにお答えし、資料等の要求があれば、関係者の皆さんに無理を言いながら、メール等を利用して情報を得て、それを提供しているということが中心の業務でございます。
| (拡大画面:27KB) |
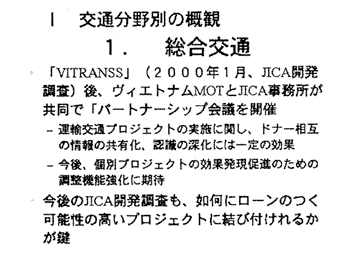 |
きょうは、最初に交通分野別の概観ということで、総合交通ということで全般的なことを申し上げます。VITRANSSがまとまった後、現在、パートナーシップ会議というのが定期的に、四半期に一度程度ということになっていますけれども、実際にはもうちょっと少なくて1年に2回から3回といったところでしょうか。JICAが費用を負担しながらMOTと開催して、出席者は各関係ドナーが出てきます。世銀、アジア開発銀行、日本、イギリス、ドイツ、フランス、カナダなど、それら七、八カ国の大使館とそれぞれの国のJICAに相当する組織が出てきております。
何をやっているかというと、ドナー相互の情報の共有化ということで、プロジェクトが重複しない、あるいは効果が短期でかつ有効に実施されるようにできるだけ連携をしましょうということが主たる目的で開催されまして、VITRANSSをまとめるときも同じようなメンバーの会議を開いて意見を取り込んでまとめたということです。
VITRANSSはJICAの開発調査としては非常に、画期的だというと怒られるかもしれませんけれども、新しい形で、各ドナーからも非常に評判がいいといいますか、まとめ方のプロセスがよかったということは言われておりまして、もちろん中身もよかったと評価されているようであります。
今はどのドナーから見ても、プロジェクトは大体基幹的なものからやらなくちゃいけないという共通認識がございますので、調整というものが必ずしも必要になってきている段階ではないですけれども、これからは、開発効果という面では、おそらくそれぞれの国のドナーで評価が違うものがだんだん出てくる時期になってきたのではないか。そういう意味でも、今後もパートナーシップ会議はしっかり続けて、より意義のあるものにしていこうというのが各国の意見でございます。
皆さんが注目されているのは、次の開発調査はどんなことをやるのかということだと思います。これはJICAの担当者がよく言うのですが、必ずしもJBICでなくてもいいのですが、各国のドナーがローンをちゃんとつけてくれる、そういうプロジェクトがしっかり入っている、それがメインにある、あるいはそういうものに結びつく、自分だけでフィージビリティーが高いと思うんじゃなくて、調査する前からドナーが、可能性が高いだろうと思うものをある程度ねらって開発調査をやるというようなことが重要になってきていると言われておりますし、私もそのように思っております。
| (拡大画面:21KB) |
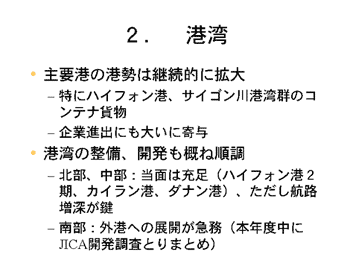 |
次に、私は港湾が長いものですから港湾からいきます。主要港の港勢は非常に拡大しております。特に、ハイフォン港の一期が終わって私が行ったときにちょうどガントリークレーンがつきました、コンテナ貨物、その他の貨物を含めて港勢は非常に増えておりまして、北部の開発に大いに貢献しているのが現状です。
サイゴン川の港湾群、幾つか管理者が違う港がありますが、河川港であるというハンディはありますけれども、お互いかなり競争しながらサービス向上に努めているということが今はいいほうに出ておりまして、問題点はあるんですが、それぞれの港が競争しながらもそれなりにコンテナ貨物等が非常に伸びているということで、港湾だけでなくて道路の整備もあってですが、最近は実際に目の当たりに港を見た企業の進出も多くなっていると聞いております。
現在の港湾の整備状況、北部ではハイフォン港の二期が決まりましたし、カイラン港も順調に進みましたし、ダナン港もこれから本格的に工事が始まるということです。おそらく問題は航路の増深であろうと考えます。ダナン港は問題ないと思いますけれども、ハイフォン二期をやるにしても、河川港の宿命で、今、浅いところは干潮時では5メートルを切るところもあると聞いています。やはり最低でも7.5メートルの水深を確保したいという声が高いです。今は足を切って入ってきておりますので、そういう意味では航路の維持浚渫の前に本来あるべき深さに戻す。9メートルぐらいまであるのが本来ですから、そこまでちゃんと水深を確保するというのが重要ですし、新しい航路の計画もございます。きょうは図面が用意できなかったのですが、新しい航路を埋没しないような形でつくるという計画でございまして、これをJBICのローンでやるという方向で今調整しておりますので、これができることがハイフォン港の発展のもとになる。
これが先ほど言いました(ハイフォン1期の)ガントリークレーンです。船は着いていないですが、こちらが新しくつくったコンテナターミナル、こちらが旧来のターミナルを改良してできた2バースです。そちらのほうに船が入って、今、既存のクレーンで荷役しているところ。つい6月に撮りました。
話がそれますけれども、問題は、折角クレーンがあるのに、ここに着いた船もクレーンを使わない、シップクレーンを使って荷役している。これはローンでやったのですけれども、使用料が若干高いということで、地元の経済が若干まだ追いついていないというんですか、そこまでコストをかけずにやったほうが多少スピードが落ちてもいいという声があります。今後もっと利用されるようになると思いますけれども、そういったことは一つの課題として言われます。もっと利用されるためには、逆に言えばもっと大型船が入ってくるためには、航路の浚渫が必要でございまして、そうすればこちらを使ってもっと効率よく荷役するということにもつながるでしょうから、航路の増深は今ある施設を使うためにも、それから二期を成功させるためにも欠くことのできないものであると感じています。
| (拡大画面:64KB) |
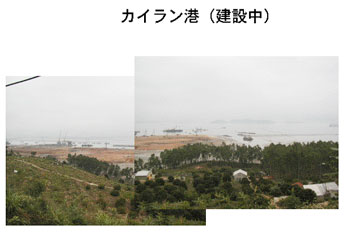 |
お手元の資料のコピーは少しずれておりますけれども、これがカイラン港です。カイラン港は来年、あと1年ちょっとで完成予定だと思いましたが、本格工事に入る前に調整に手間取ったこともございまして、ここにケーソンが並んでおります。これが3月か4月の写真です。今はもっとずっと並んでいると聞いておりますが、これが岸壁法線で、工事は若干おくれることになりそうだということですが、最初の見込み違いを除けば順調に進んでいるということです。これは埋め立てたところです。ここに小さな船があるのがポンプ船で、数十隻のポンプ船が常に浚渫をしてここに土を吹いているということです。
これは建設中のダナン港、これからつくる防波堤はこちらのほうです。岸壁法線とかは忘れましたけれども、これは現状のダナン港で、今一所懸命やっているのは道路です。こちらのほう、背後のこの辺を通るのですかね、かなりできてきていると聞いています。これはかなり古い、半年以上前の写真です。これは貨物の一つです。これが上屋です。ここは港としては非常にいい立地条件で、都心から近いですし、非常に入りやすそうな港です。ですから、あと問題は背後に港を使う企業がいかに張りつくかということではないかと私は思っております。
それから南部につきましては、今、南部港湾調査というJICA調査をOCDIがやっておりまして、本年度中に取りまとめられます。調査中ですので詳細は避けますが、どこからつくったらいいかというのは一応候補地も発表されて、今、議論しているところです。つい最近調査団が帰ってきましたので、直近のことはわからないのですけれども、14メートルのコンテナ2バースをカイメップに、それからチイバイ川の上流のほうに一般貨物バース、これも2バースを最初につくったらどうかと。詳細は忘れましたけれども、第一期、二期に分けて提案しております。いずれにしましても、サイゴン川は水深に問題がありますので、大型船の入れる港はございません。そういう意味では南部で非常に増えておりますコンテナ貨物を扱うための、そして大型船が入るためのコンテナターミナルというのは今後の港湾案件としては第一に挙がってくるのであろうと思っています。
| (拡大画面:69KB) |
 |
| (拡大画面:22KB) |
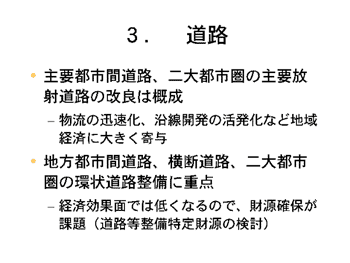 |
次に道路につきましては、一般論としては、主要都市間道路、ハノイ―サイゴンを結ぶ国道1号線、それから先ほどのハイフォン港とハノイを結ぶ5号線、あるいは国境に向かう道路、ハノイからランソンとか、ホーチミンからカンボジア国境に向かう道路、この辺はまだ供用されていない部分もありますけれども、かなり整備が進んでおりまして、見方としてはおおむね概成に近いということです。それから二大都市圏の主要の放射道路もかなり進んできたということで、これらの効果で、物流の迅速化、それから沿線開発の活発化など地域経済に大きく寄与しているということで、そういう意味では道路の整備によるヴィエトナムの経済発展の効果は絶大であると感じております。
卑近な話で言いますと、二、三年前まではハノイで漁介類といえば川物が多かったのですが、今は庶民の口にも海のものが入るようになった。もちろん高級品には違いありませんので毎日というわけにはいきませんけれども、ちょっとしたレストランに行くと、ヴィエトナム人が海の魚、魚介類を食べながらわいわい騒いでいる姿も結構見られます。もう1レベル下がった店に行ってもおいしいものが食べられるんですが、聞きましたら、5号線ができてハイフォンあたりから半日かけずに魚が入ってくるとのことで、そういう意味で庶民の口にも上るようになったというのは、やはり道路の一つの経済効果ではないかというようなことを、そういう魚を食べながら地元で時々話しております。
それから沿線開発の活発化これも写真でお見せするのがいいのですが、5号線の沿線は、ハイズンが真ん中にあります。100キロちょっとの5号線ですが、ハイズンまでの道、半分ぐらいまでは、行くたびに、あっ、こんなところにまた田んぼをつぶして、あるいは畑をつぶして工場用地にしているなという感想が持てるほど、1カ月、2カ月ぶりに行くと、必ず新しい開発が、また前に開発されたところはすでに上屋が建ち始めているというような状況が見られますので、そういう意味で、沿線開発の活発化というのは目をみはるものがあります。残念ながら、私も南のほうは度々は行きませんが、ホーチミン周辺も同様だと聞いております。
今後は、主要都市間道路から地方の都市間道路、あるいは縦の道路から横の道路、ラオス、カンボジア、あるいは中国の国境に向かうような道路、これが望まれているところとなっております。それから、二大都市圏においては、環状道路の整備、ハノイで言えば環状3号線。ホーチミンは今1号線が橋の工事があと1カ所終了していないようで、あれができるとほぼ環状が1本は通りますので、拡幅とか、もう少し内側の橋の改良とか、まだまだ不十分なところはありますけれども、今後はそういった環状道路整備に重点が置かれるだろうということが言われております。
でもそうなると、経済効果面では若干低くなる部分が出てきますので、ヴィエトナム政府としては財源確保が最大の課題であろうと。もちろんローンがつけばいいんですけれども、ローンがついたにしても自分たちの自己負担分というのが出てくるでしょうし、全部が全部、採用されませんので、必ずしも道路に限らなくて交通全般ということになるかもしれませんけれども、ちょっと前から検討されております道路特定財源というようなもの、これをMOTとしてはぜひやりたいと言っておりますけれども、やはりどこの国も財政当局としてはそういう特定財源的なものは認めたくないということがありますので、まだ俎上にのるというところまで行っておりません。
これは国道5号線のどの辺か忘れましたけれども、1年前ぐらいに撮ったものです。これは道がすいていますけれども、今一つ問題になっているのは、これを取り上げましたのは、国道5号線あたりで事故が多い。今、交通事故死亡者が1万人を越えてしまって、交通の中では最大の課題が交通安全対策になっております。そういうこともあって、一番事故が多いと言われております5号線で横断歩道橋の建設が非常に進んでおります。高さ、クリアランスが4.5メートルあると思いました。基準は4.2メートルか4.5メートルなんですが、確か実質4.5メートルは確保されているということで、普通のトラックは通れるんですが、例えば普通のトラックがコンテナ用ではないシャーシーにコンテナを積んでくると、どうも背高コンテナが通れないらしいのです。
これではちょっと見えませんけれども、不注意というか、そういうものも含めて、結構ぶつかる車があるということでこの辺に傷があるのです。今、橋をほとんど4.5メートルぐらいでつくっていて、ちょっと大型の貨物があると、この国道5号線を通れずに迂回路を通っている場合も結構あるようでございまして、そこが一つ問題だという物流業者の方もいらっしゃいました。
高さは4.5メートル以上ありますので、自転車とかがほんとに皆さんここを通ってくれれば、もちろんここにアプローチがあるわけです、かなりぐるっと回ったアプローチになりますので、モーターバイクは気にしないかもしれませんけれども、リヤカーとか自転車とか、そういったものが、歩道橋が増えたことによって道路を横断しなくなくなるのかなということは心配です。ご存じの方もいらっしゃると思いますけれども、街中に行くとこの辺(中央分離帯)を勝手につるはしで変えてしまって自転車が通れる、あるいはリヤカーが通れるくらいの幅の通路に変えてしまったところもありますので、そういったところがちゃんと取り締まれるのかということが心配ではあります。
| (拡大画面:26KB) |
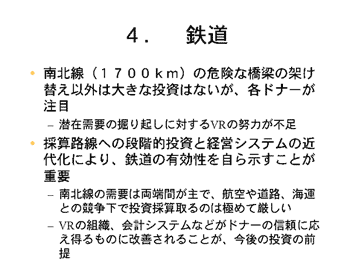 |
それから鉄道です。南北線、ハノイとホーチミンの間1,700キロについては、日本の協力で19橋の危険な橋梁の架け替えがされてまいりましたが、それ以外の大きな投資は今のところない状況です。ただ各ドナーは注目しております。潜在需要はかなりあると言われていますけれども、やはり最大の問題は、その掘り起こしに対するVR(ヴィエトナムレールウエー)だけではないですけれども、MOTも含めて、そういった国としての努力が全く不足している。今のままでは次の投資はどこもしてくれないというのが各ドナーの方共通した意見ではないかと思います。
そういう意味では、私は、後で出てきますけれども、まず採算をとれそうな路線はハイフォン線が一番だと思います。そういうところで、段階的投資というか、まず自分でできる範囲の投資から始めるということです。かつ投資とその見返りを外に対してちゃんと数字で言うことができるような会計システム、あるいは組織全体のシステム、サービス、そういったものをまず自らできる分はやるということが大事ではないか。それによって鉄道の有効性を示して、自らでもここまでできたのだから、次の投資には協力しましょうということにつなげる、そういった姿勢が一番重要なのではないかと思います。
特に南北線の需要というのは、ハノイからホーチミンの2つの間、その間に半分以下の距離で需要があればいいんでしょうが、基本的には両端間の需要が主ですから、そうなると旅客は航空やバス、貨物は海運、あるいはトラックとの競争にさらされます。橋のかけかえで少し、スピードをあげて通れるようになったということが一番大きいのでしょうが、やっと旅客が30時間で行けるようになりましたけれども、料金的にもそんなに安くないですから、このぐらいの時間ではとてもこれらとの競争で勝てない。貨物にしてもなかなか海運と競争できるほどにはなりません。貨物はもっと時間がかかります、3日ぐらいかかるではないでしょうか。極めて難しい状況です。ですからこの南北線で勝負するというのはあまり賢くないのではないかと、時々VRの方とか、MOTの方にもお話ししたりしますが、おそらく多くの方もそう思っていると思います。
先ほども言いましたけれども、VRの組織というものが非常に弱いと言われております。弱いというのは、個人個人の能力というよりは、組織として今のままでは経営の近代化を進めるに耐えられないということ、それから先ほど言いましたように、ハイフォンーハノイ間が、今、どのくらいの金がかかって、どのくらいの収入があるかというような個別路線の採算がだれもわかっていない、もしかしたらわかるのかもしれないけれども、計算しようと思ってデータを求めても、VITRANSSのときにも出てこなかったと聞いております。そういうところをしっかりさせることがドナーの信頼にこたえることになるんだろうと思います。
先ほどパートナーシップ会議について申し上げましたけれども、そのときに世銀の方が発表した資料の中で、鉄道については“only focus on upgrading”ということで、改良ばかりに目が行っている、“less management improvements/privatization or other”ということで、民営化とか、マネジメントの向上についてはほとんど努力がなされていないと指摘されております。これは前々から指摘しているそうですが、やはりそんなところがないとどのドナーももう一歩突っ込んではくれないという状況です。ということで、既存インフラの最小限の改良でサービス向上を図ることが大事ではないかと思います。
| (拡大画面:17KB) |
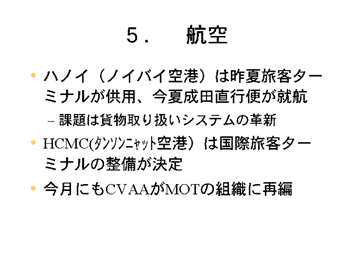 |
航空に関しまして、もうご存じだと思いますけれども、ノイバイ空港は昨夏、旅客ターミナルが供用されまして、この6月末からJALとヴィエトナム航空の共同運航で成田直行便が週4便就航しています。最近聞いた話では、貨物取り扱いシステムが非常に古いといいますか、設備は必ずしも古くないけれどもシステムが古い。また全体の連携がとれていないというか、設備がばらばらに導入されていて、とてもあれでは取り扱いを増やそうと思っても増やせないし、迅速な取り扱いもできない。貨物につきましては、週末は税関が休みということもあるのですけれども、例えば月曜日の便で来て、それを月曜日中に受け取ろうと思ったら、月曜の朝から空港に行って、運がよければその日のうちに受け取れるというぐらいに、月曜日は貨物が混みますということでした。それほど国際貨物便が多いわけではないのにそういう状況ですから、やはりシステム全体の革新というのは急務だろうなと。今、旧旅客ターミナルビルを改良して貨物ターミナルにという話がありますけれども、それよりもいっそ全体をもう少し考えたほうがいいのではないかという意見もあります。
それから、ホーチミンのタンソンニャット空港です。JBICのローンで、国際旅客ターミナルの整備が決定いたしましたので、一つ課題がクリアされて、貨物がどうなっているのかは、私はハノイと同じような問題があるのかどうかわかりませんが、とりあえず一歩前進。
来る直前に聞いたのですが、今度CVAAはMOTの組織に再編されるということです。VITRANSSでも指摘されていますが、運輸省の中に航空部門がないというのは総合交通の観点からおかしいという指摘があって、それを踏まえて決めたんだと聞いております。もう再編されたかもしれませんし、まだかもしれませんけれども、7月にはという話を聞いておりました。
|