|
(4)道路交通について
(1)道路の現状
佐賀県では、人やモノの移動を自動車に頼る割合が大きいにもかかわらず、国県道の整備率は45%と全国平均(53%)を下回っている。
特に、4車線以上の道路が少なく、幹線道路の整備が遅れている状況であり、道路網の整備は緊急の課題となっている。
(2)「県内主要都市間55分圏」の確立
佐賀県は、平坦部が多いため(可住地面積割合56%)、小さな都市が分散して県土を形成しており、これらの地域間の連携を強化することが、県政発展には不可欠である。
このため本県では、「安全でうるおいのある暮らしを支える道づくり」を目指して、県民の日常生活に密着した道路の歩道設置や渋滞対策を進めるとともに、「県内主要都市間55分圏」の確立を基本目標に、地域の産業や経済活動を支える基盤となる幹線道路網の整備を進めている。
| (拡大画面:130KB) |
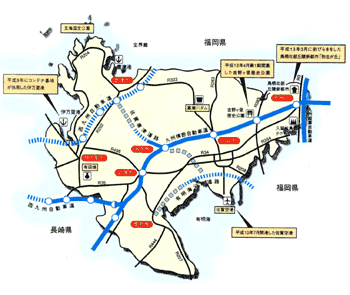 |
県内の幹線道路網は、平成2年に開通した「九州横断自動車道」を基軸として、玄界灘側の東西軸となる「西九州自動車道」(高規格幹線道路)や、有明海側の東西軸となる「有明海沿岸道路」(地域高規格道路)、これら3本の東西軸を連結する「佐賀唐津道路」(地域高規格道路)を骨格としているが、このうち開通しているのはごく一部区間で、整備に着手していない区間も多く残っている。
また、九州最大の集積圏である福岡都市圏との連携強化も重要な課題であり、福岡県境付近の国道385号東脊振トンネルの整備を、平成14年度から有料道路事業で行うこととしている。
(3)空港・港湾アクセス道路
広域的な交流・物流拠点となる空港・港湾へのアクセス道路も幹線道路網と一体となって整備を進める必要がある。
「有明佐賀空港」と福岡県南西部地域などを連絡する有明海沿岸道路(大川市から福富間約20km)については、環境影響評価法の手続きに早々に着手する予定である。
「伊万里港」と九州横断自動車道を連絡する国道498号については、開通した松浦バイパス(5.2km)に引き続き大坪バイパス(4.2km)を平成12年度より事業化している。「唐津港」と西九州自動車道を連絡する国道204号については、佐志バイパス(5.3km)の整備を進めている。
(4)路線バス・タクシーの概況
県内の乗合バス事業は、自家用車の普及等により輸送人員が年々減少しており、平成12年度の輸送人員は千二百五十二万人と、ピーク時の昭和42年度の約6分の1に減少している。
しかしながら、乗合バスは地域住民、とりわけ高齢者や学童等の交通弱者にとって最も身近な公共交通機関として重要な役割を果たしており、県は、国及び市町村と連携して路線バス運行費補助の財政支援措置を講じてきたところである。
道路運送法の改正(施行は平成14年2月)により、乗合バス事業に係る需給調整規制が廃止され、事業の参入・退出が自由化されたことに伴い、平成13年4月から、国において、運行費補助に関する制度の見直しが行われ、広域的幹線的路線の維持を図るための措置が講じられている。
県においても、国の補助対象外となる路線等のうち一定の輸送量のある準幹線的な区間について、新たに市町村との協調補助により運行費補助を講じている。
乗合バス輸送人員の推移
タクシーについては、ドア・ツー・ドアの機動的、個別的輸送機関として県民生活に定着しているものの、輸送人員については減少が続いている。
そのため、各事業者においては、高齢化社会の到来や障害者の社会参加等の多様化するニーズに対応するための介護タクシー導入や、高齢者に対する割引運賃の設定など利用促進に向けた創意工夫とサービス向上により利用者の増加が図られているところである。
(5)鉄道について
(1)概況
佐賀県内の鹿児島本線、長崎本線をはじめとするJR5路線(197km、59駅)の利用者は、年間約3千4百万人を数え、またその半数以上が通勤・通学者であり、交通手段が多様化した今日においても、最も重要かつ日常生活に密着した公共交通機関となっている。
また、この他に第三セクター鉄道の甘木鉄道と松浦鉄道の2路線があるが、両方とも全国で数少ない黒字経営の路線として注目されている。
(2)今後の鉄道整備
鉄道は、大量輸送や定時性、安全性とともに、省エネルギーや環境負荷の低減の面でも優れており、こうした特性を活かしながら、地域間交流の促進と県土の均衡ある発展を図るため、今後とも、利便性の向上、複線化や電化による高速化、輸送量の増大の実現を目指していくこととしている。
また、九州と本州を結ぶ背骨の重要な部分である九州新幹線鹿児島ルートにおいて、本県区間を含む博多・船小屋間が平成13年6月に着工した。これにより鹿児島ルート全線がフル規格で整備されることになった。
全線整備後は、九州地域の産業・文化・生活の一体的発展や広域的な交流の促進に寄与し、さらには新鳥栖駅が設置されることで、本県を取り巻く交通の利便性が向上することにより、本県の立地条件が高まることが期待される。
|