|
表2.3 観測プロジェクト別の情報抽出件数
| プロジェクト・調査・研究名 |
件数 |
| 西太平洋海域共同調査(WESTPAC) |
353 |
| 黒潮及び隣接海域共同調査(CSK) |
54 |
| 第一次GARP全地球実験(FGGE) |
53 |
| 黒潮開発利用調査研究(KER) |
53 |
| 全世界海洋汚染監視ネットワーク(MARPOLMON) |
51 |
| 全世界海洋情報サービスシステム(IGOSS) |
51 |
| 日中黒潮共同調査(JRK) |
27 |
| 第II期東アジア縁辺海循環調査研究(CREAMSII) |
13 |
| 東アジア縁辺海循環調査研究(CREAMS) |
8 |
| 海洋汚染監視パイロット計画(MAPMOPP) |
7 |
| 北東アジア地域世界海洋観測システム(NEAR−GOOS) |
5 |
| 世界海洋観測システム(GOOS) |
4 |
| 海洋気象業務(MMS) |
4 |
| 縁辺海の海況予報のための海洋環境モニタリングの研究(NEAR−GOOS) |
4 |
| 長崎大学・釜慶大学校(前釜山水産大学校)東シナ海共同調査 |
4 |
| 全世界海洋環境汚染調査(GIPME) |
3 |
| ISTC協定下の日本海共同観測 |
3 |
| 国際深海掘削計画(ODP) |
2 |
| 海面高度観測衛星(TOPEX/POSEIDON) |
2 |
| 日ロ海洋環境共同調査 |
2 |
| Argo計画 |
2 |
| 国際生物学事業計画(IBP) |
1 |
| 北太平洋海洋科学機構(PICES) |
1 |
| 世界海洋循環実験(WOCE) |
1 |
| 海流断面観測システム(PEGASUS) |
1 |
| しんかい2000潜水調査 |
1 |
| 海洋生命系のダイナミクス(DOBIS) |
1 |
| 合 計 |
711 |
|
2.1.2 国内の観測情報
(1)国内行政機関の定期観測
海上保安庁、気象庁、水産庁、防衛庁、環境庁(現在は環境省)や各県水産試験場などの国内の行政機関では、定期観測を実施している。これらの概要について、「海洋環境調査法」(1985年)より引用し、日本海海洋調査の概要一覧とインベントリー情報の資料収集状況を 表2.4に示した。このうち定線観測線図を図2.1に示した。なお、図2.1は1985年時点の資料であり、観測測線が変更されている場合や、観測が行われていない時期も存在している。 表2.4のNo.1〜10までは、各関係省庁より印刷物として海洋観測資料あるいは報告書が作成されている。しかしながら、これらの資料は膨大な数となる。関係官庁及び県においては、海洋観測の連携及び情報交換を図るため、海洋調査技術連絡会を設置している。この連絡会においては、気象庁舞鶴海洋気象台、海上保安庁第二、第八、第九管区海上保安本部、防衛庁舞鶴地方総監部、水産庁日本海区水産研究所(現在、独立法人水産総合研究センター日本海区水産研究所)及び各県水産試験場の毎年の観測実施状況等が報告されている。この連絡会の議事録(「日本海海洋調査技術連絡会議事録」;1970〜2001年)から日本海における定線観測及び各機関の目的別の観測情報を収集した。なお、各県水産試験場の定線観測は、継続年数、1年間に行う観測頻度、観測測線数とも、どの定期観測よりも多い。これらの観測については、今年度は観測情報の収集までにとどめた。一方、各機関が行った随時観測、国内外のプロジェクトに関する観測については、上記資料より属性情報を第3章に後述する方法でデジタルデータ化した。
環境庁の海洋汚染調査 (表2.4のNo.6)については、「日本近海海洋汚染実態調査報告書」より観測情報を収集し、データ化した。 国土地理院による沿岸海域基礎調査 (表2.4のNo.9)に関しては、不定期に日本周辺海域の50m以浅の浅海域の測量調査時に物理及び水質調査を行っているようであるが、報告書を見ると必ずしも海洋観測は行っていないので、必要な調査報告書を抜粋する必要があり、今年度は情報収集は行わなかった。 気象庁ブイロボット (表2.4のNo.10)は、2000年5月に観測を終了し、代わりに漂流型ブイロボット (表2.4のNo.11)の観測が2000年2月から行われている。漂流型ブイロボットについては、舞鶴海洋気象台によると、常時、最低1機は日本海に存在するようにブイを漂流させるように設置を図っているとのことである。漂流型ブイロボットの観測結果は、舞鶴海洋気象台のホームページにおいて公開されている。
A
| (拡大画面:58KB) |
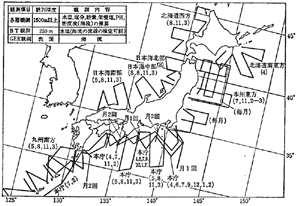 |
図14・4 海上保安庁の海洋観測定線概要図(観測資料は表14・2の(1)に収録)
B
| (拡大画面:53KB) |
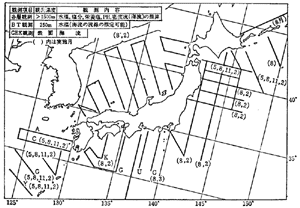 |
図14・5 気象庁の海洋観測定線概要図(観測資料は表14・2の(2)に収録)
C
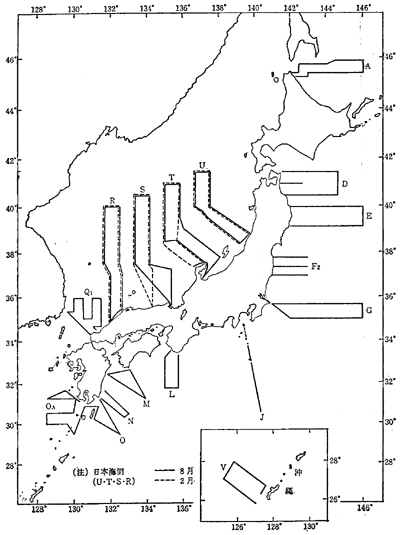 |
|
「海洋環境調査法」(1985)より引用
|
図14・6 都道府県水産試験場の沖合定線概要図5)(表14・3参照)
図2.1(1)行政が実施する定期調査測線
D
| (拡大画面:47KB) |
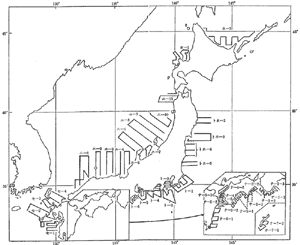 |
「海洋環境調査法」(1985)より引用 |
図14・7 都道府県水産試験場の沿岸定線概要図5)(表14・4参照)
図2.1(2)行政が実施する定期調査測線
E
| (拡大画面:39KB) |
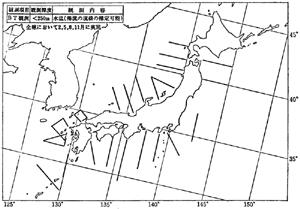
|
図14・9 防衛庁の海洋観測定線概要図(観測資料は表14・2の(4)に収録)
表14・6 海洋汚染調査資料の定期刊行物
| 番号 |
資料名(資料作成機関) |
内容 |
備考 |
| 1 |
日本近海海洋汚染実態調査報告書
(環境庁水質保全局) |
調査項目は、水質調査(表層から水深4000mまでのCOD、SS、栄養塩類、重金属、PCB、油分等)、底質調査(水深3000m以浅の底質の強熱減量、硫化物、重金属、PCB、油分等)、生物調査(クロレラ等のプランクトン)であり、これらの分析結果表、平面分布図、鉛直断面図等が掲載されている。 |
年刊
非売品 |
| 2 |
海洋汚染調査報告
(海上保安庁水路部) |
測定項目は、石油、PCB、総水銀、カドミウム、クロム、COD、底質の鉱物組成等であり、これらの調査結果(汚染の概況、測定値表、調査地点位置図、汚染地図、分析法の検討等)が掲載されている。 |
年刊
非売品 |
| 3 |
廃油ボール汚染の実態について
(海上保安庁警備救難部) |
調査手法の概要、調査結果及び考察、並びに関係資料(調査測定値、調査状況図、汚染指数ランク状況図等)が掲載されている。 |
年刊
非売品 |
| 4 |
気象庁海洋汚染観測速報
(気象庁海洋気象部
大気・海洋汚染分析センター) |
内容は、海況(海流、水温、塩分)、化学成分(溶在酸素、硝酸塩等)プランクトンに関する期別、観測線別の観測結果、及び海水中のカドミウム、総水銀に関する季別の観測結果の解説を主体とし、関係図表が添付されている。また、付録として綾里における降水の月ごとの化学分析結果が掲載されている。なお、観測データは「気象庁海洋気象観測資料」にまとめて掲載されている。 |
年2回刊行
非売品 |
|
F
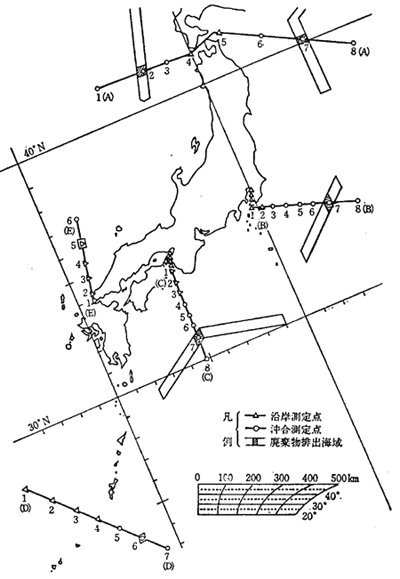 |
「海洋環境調査法」(1985)より引用 |
図14・10 環境庁の海洋汚染調査地点
(環境庁「昭和50年度日本近海海洋汚染実態調査報告書」による)
図2.1(3)行政が実施する定期調査測線
G
図14・11 海洋汚染・廃油ボール調査図
H
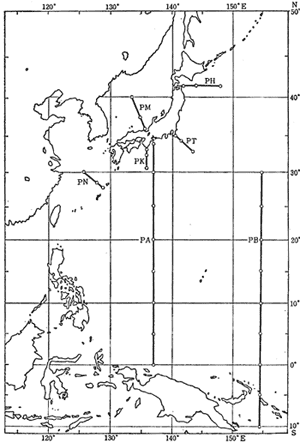 |
「海洋環境調査法」(1985)より引用 |
図14・12 気象庁の日本近海・西太平洋海域海洋汚染標準観測線および観測点
(気象庁海洋気象部「気象庁海洋汚染観測速報」による)
図2.1(4)行政が実施する定期調査測線
|