|
第2章 国内外の資料収集・整理
2.1 観測・研究プロジェクトの調査
日本海に関わる観測・研究プロジェクトについて観測情報を収集するにあたり、国際的なプロジェクトの観測、国内の観測、国外の観測に区分を行い、観測情報の収集を行った。
2.1.1 国際的なプロジェクトの観測情報
日本海の観測について、国際的なプロジェクトとして行われた観測情報の概要について表2.1にまとめた。国際的なプロジェクトについては、データの所有、管理体制が異なっていることが多い。従って、観測情報を収集するにあたり、政府間海洋学委員会(IOC)及び世界気象機関(WMO)において承認または推進された国際観測プロジェクトと、それ以外の国際研究プロジェクトにより実施された観測の2つに分類し、プロジェクトの整理を行った。
国際観測プロジェクトでは、計8件のプロジェクトを抽出した。政府間海洋学委員会において承認された国際観測プロジェクトでは、周辺諸国と協力して観測を行っており、そのうち日本海において観測を行っているものは7件であった。また、第一次GARP全地球実験は、世界気象機関により推進されている。
国際観測プロジェクトで最も古いものは、1965年から行われた黒潮及び隣接海域共同調査(CSK)で、1979年から西太平洋海域共同調査(WESTPAC)が開始されるまで継続された。また、現在も継続して観測が行われているのは、1980年からの全世界海洋汚染監視計画(MARPOLMON)、1982年からの全世界海洋情報サービスシステム(IGOSS)、北東アジア地域世界海洋観測計画(NEAR−GOOS)である。このうち、IGOSS及びNEAR−GOOSに関しては、国際的なデータ交換や海洋環境の把握・監視のための海洋観測システムの構築などを目的としているため、これらのプロジェクトによる観測自体は少ないものと考えられるが、データの迅速な公開は最も進んでいる。
一方、この他の研究プロジェクトに関しては、官公庁または大学、研究所などが明確な研究目的を提示して行った研究観測であり、厳密には上述の国際プロジェクトと区分しにくいものがある。最も古いものは、1977年からの黒潮開発共同利用調査研究(KER)があり、主として科学技術庁が中心となって観測研究を行った。
1990年代以降は、ロシアを含んだ研究プロジェクトが多く組織されるようになった。そのうち最も代表的なものは、東アジア縁辺海循環海洋研究(CREAMS)である。CREAMSは、日本海全体を対象とする大規模な国際的なプロジェクトであり、多くの新しい知見が得られている。CREAMSの第1期(1993年〜1996年)は、主としてロシアの観測船による観測が行われ、日本では九州大学応用力学研究所を中心として、長崎大学鶴洋丸における日本、韓国、ロシアの共同観測が行われた。また、1999年にはこれにアメリカが参加し、CREAMS第II期の観測が開始され、主としてアメリカ及びロシアの観測船による観測が実施された。
上記の各観測プロジェクトについて、観測情報のインベントリー情報の所在、データの所在等の調査を行い、その結果を表2.2にまとめた。
各観測プロジェクトのうち、日本が行った観測情報については、そのほとんどはJODCに存在していた。一方、韓国、ロシアの外国の観測情報については、主として韓国国立海洋データセンター(KODC)やロシアのNODC、ロシア極東水理気象研究所(FERFRI)、ロシア太平洋研究所(POI)などのホームページから情報を収集した。
また、研究プロジェクトについては、そのプロジェクト毎にデータレポート、ニュースレター、シンポジウム要旨集、報告書などの印刷物、または、そのプロジェクトのホームページ等から情報を収集した。
収集したインベントリー情報の入力・整理を行った結果、国際プロジェクト別の観測情報件数については表2.3のとおりで、計711件の観測情報を収集した。整理した観測情報の中には、表2.2に示したプロジェクト以外の情報も含まれていたが、いずれもプロジェクト毎のインベントリー情報の数は10件と少なく計11件であった。
表2.1(1) 日本海に関わる観測プロジェクトの概要
(1)国際観測プロジェクト(IOC、WMOによるプロジェクト)
| (拡大画面:58KB) |
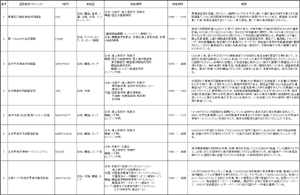 |
表2.1(2)日本海に関わる観測プロジェクトの概要
(2)研究プロジェクト((1)以外)
| (拡大画面:59KB) |
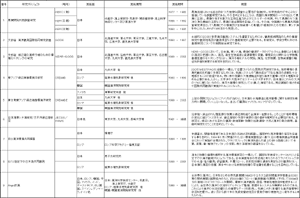 |
表2.2(1)プロジェクト別観測情報の調査状況
| (拡大画面:33KB) |
 |
表2.2(2)プロジェクト別観測情報の調査状況
| (拡大画面:33KB) |
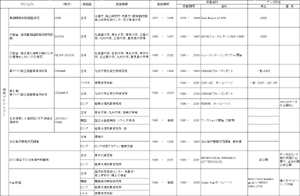 |
|