|
(3)データ整理
a)基準点の設置とその測量
KGPS測位は、収録したデータを後で解析する後処理方式である。今治と魚島に設置した陸上基準点の位置をスタティック測量により求めた後、移動点の緯度、経度、楕円体高を算出した。今回の作業でも陸上基準点の設置場所は、上空の視界が開け、周囲に反射物などがなくマルチパスの影響が少ない場所を選定した。陸上基準点及び測量の概要を表9に示す。
9 K-GPS測位のための陸上基準点の概要のまとめ
| 測量場所 |
今治港 |
魚島 |
| 期間 |
自:10月10日8時55分 至:10月10日18時分 |
自:10月9日17時00分 至:10月10日18時00分 |
| 測量時間 |
9時間05分 |
25時間 |
| 測量間隔 |
0.5秒 |
0.5秒 |
| 受信機 |
Trimble社製4000SSI(2周波) |
Trimble社製4000SSE(2周波) |
| アンテナ |
グランドプレーン付きコンパクトL1/l2アンテナ |
グランドプレーン付きコンパクトL1/l2アンテナ |
|
b)陸上基準点の位置の解析
陸上基準点の位置は、国土地理院の電子基準点データをもとに算出した。基準として使用した電子基準点は、陸上基準点に近く、標高差が50m未満のものを3点選定した。解析に使用した電子基準点の概要を表10に示す。
表10 陸上基準点の位置解析に使用した電子基準点の概要
| 電子基準点 |
設置場所 |
機種
アンテナ |
緯度・経度
(WGS-84) |
楕円体高
(m) |
データ間隔 |
950430
今治 |
愛媛県今治市大新田公園 |
TRIMBLE4000SSI-RC
Permanent-L1/L2 |
34-04'40.395200"N
132-59'24.830400"E |
41.883 |
1秒 |
950432
西条 |
愛媛県西条市玉津小学校 |
TRIMBLE4000SSI-RC
Permanent-L1/L2 |
33-55'16.338800"N
133-12'04.727100"E |
43.164 |
1秒 |
960678
弓削 |
愛媛県佐島小学校 |
ASHTECHZ-XII3
Rev.D(70718) |
34-15'08.806100"N
133-11'20.7514001"E |
58.432 |
1秒 |
|
また、各電子基準点及び陸上基準点の位置関係を図11に示す。図の円は、基準点を中心とした半径20kmを示す。
図11 KGPS基準点と移動点の関係(平成14年10月10日)
解析は、GPSurvey2.35ソフトウェアを使用した。基準とした電子基準点ごとに陸上基準点の緯度・経度・楕円体高を算出し、それぞれの値の平均値を決定値とした。陸上基準点の解析結点果を表11に示す。
表11 陸上基準点の解析結果
| 陸上基準点 |
緯度 |
経度 |
楕円体高 |
| 魚島 |
34-10' 46.403937" |
133-19' 17.906286" |
39.128 |
| 今治 |
34-04' 06.185098" |
133-00' 24.884617" |
38.601 |
|
c)K−GPS測位
K−GPS測位の概要を表12に示す。
表12 測量船のK-GPS測位の概要
| 測量船名 |
くるしま |
| 測量日時及び海域 |
平成14年10月10日9時57分〜15時47分 今治東方燧灘付 |
| 平成14年10月11日9時32分〜15時01分 今治港より宇品 |
| 収録データ間隔 |
0.5秒 |
| 受信機 |
Trimble社製4000SSE(2周波) |
| アンテナ |
グランドプレーン付きコンパクトL1/l2アンテナ |
|
d)K−GPSデータ解析
ア)今治東方燧灘海域データ
KGPS測位データの後処理は、前項で求めた陸上基準点を基準とし、GPSurvey2.35ソフトウェアを使用して実施した。移動点のデータは、測量開始から魚島付近に到着した13時までと、12時から測量終了までのデータに分けて解析した。それぞれの基準点による結果を図12に示す。
| (拡大画面:39KB) |
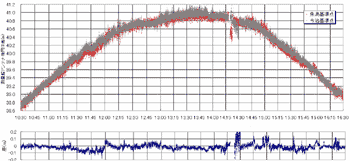 |
| 図12 |
魚島及び今治陸上基準点を基準として解析したK−GPS測位結果(高さ成分)の比較 |
これを見ると、魚島、今治ともほぼ同じ結果を示しているが、今治港を基準とした方がややばらつきが少ないように見える。
このデータに測量船の動揺データを加え海面高に換算して求めたものが図13および図14である。計算結果には、今回設置した魚島、今治の基準点のほかに当該海域に隣接する西条および今治の国土地理院電子基準点データを使用したものも示す。データ取得間隔は本研究で設置した陸上基準点は0.5秒ごとであるのに対し電子基準点は1秒ごとのデータである。測量点からほぼ同一の距離にある陸上基準点と電子基準点の結果が同様であったことは、現地観測を実施する時に、計算上は子基準点が測量海域近傍に存在すれば、特に陸上基準点を設置する必要はない。ただし、電子基準点データは最短1秒データであり、GPSurvey等では、1秒間隔の測位結果しか得られない。
これらのデータに共通して見られる14時前後の測位解の欠損、および14時20分および14時50分頃の異常なばらつきは、この頃に衛星の数が少なかったことに加え、ひとつの衛星(6番衛星)がマストの影になりノイズが大きく安定したデータを取得できなかったことが大きな影響を与えていると見られる。14:00〜14:45は南北測線で常に測量船が南進し、アンテナとマストの関係から受信できていない衛星が存在した。この影響を取り除くため、該当6番衛星をはずして計算しなおすと、計算に必要な衛星の個数を確保できず、計算不能となる。また、今治の電子基準点は、他の陸上基準点と多少、取得衛星の組み合わせが異なり、6番衛星および26番衛星が捕捉されていない。このため、今治電子基準点を基準とした結果は、14時を挟んで1時間ほど測位ができない。図17に測量時の衛星捕捉状況を示す。
| (拡大画面:46KB) |
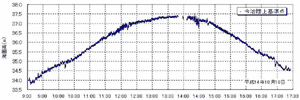 |
| (拡大画面:42KB) |
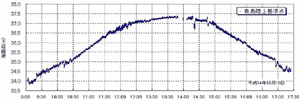 |
| 図13 |
陸上基準点をもとに測量船のK−GPS測位で求めた海面の楕円体高 |
| (拡大画面:39KB) |
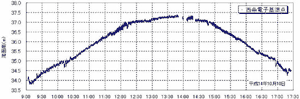 |
| (拡大画面:35KB) |
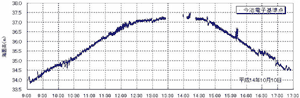 |
| 図14 |
電子基準点をもとに測量船のK−GPS測位で求めた海面の楕円体高 |
これに対し、別の解析方法として、米国NASAのColombo教授の作成したプログラムIT(Interferometric Trajectory)を用いた解析を実施した(Colombo,1998)。今治、魚島の両基準点データをもとに解析した結果を図15に示す。解析にあたっては、Multi Pathに関するデータの質のチェック(Quality Check)を行いくつかの異常データを削除している。これは、米国UNAVCO(University NAVSTAR Consortium)のRocken博士ほかのスタッフにより開発された方法(UNAVCO 1994)によった。14時付近から15時付近までデータが欠損しているのは、Quality Checkの結果、この時間帯のデータが削除されてしまったためである。
| (拡大画面:43KB) |
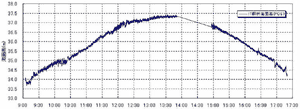 |
| 図15 |
今治、魚島基準点をもとにプログラムIT解析で求めた測量船のK−GPS測位から得た海面の楕円体高 |
また、これらの計算結果を比較するため、各データを重ね合わせて表示したものが図16である。これを見ると、プログラムITによる結果の方がGPSurvey2.35より高い傾向を示している。しかしながら、IT解析では、欠損の後の15時以降は、安定した解析はできず、解析条件(どの程度までデータを削除するか)によってかなり結果が変動することとなった。これは、後に述べるように、IT解析が、ノイズに弱く、逆にGPSurveyの解析がノイズに比較的強いことが理由として考えられる。
| (拡大画面:85KB) |
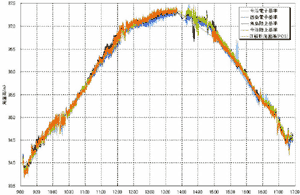 |
図16 解析結果の比較
プログラムITは、L1L2の2周波の観測からL3と呼ばれる距離(LCと呼ばれることもある)を合成しそれを用いる。具体的には、L3(長さの単位)は
L3=L1+1.5457(L1−L2)
で計算され、左辺のL1、L2は、それぞれの周波数の位相で求めた疑似距離(長さ)であり、いわゆる整数値不確定を含んでいる。L3は、電離層の影響が取り除かれた位相で求めた距離である。この方法では、短基線で可能な、位相の整数不確定を整数として解くことをしないために、データノイズに弱く、その影響を受けやすい。その代わり、ノイズに汚染されないデータであれば、長基線では精度は確保できる。
今回の場合、基準点から30km程度の距離であるが、安定した結果が、GPSurveyで得られていることから、むしろ、整数不確定を整数として解くGPSurveyの結果のほうが、ノイズデータの除去を効率的にできていることが考えられる。
|