|
3.5 ケーブル布設要領
3.5.1 一般
(1)ケーブルの布設順序
ケーブルの布設順序は、船舶の大きさ、船舶の種類及び工作法により異なるが、一般的には下記のような順序で行う。
なお、DC24V系などの低電圧回路においては、あらかじめ陸上でワイヤーハーネス(組電線)を作成しておくと、作業が容易になる場合がある。
(a)区画別
機関室→居住区→フライブリッジ又は暴露甲板
(b)電路別
主電路→枝電路
(c)線種別
長尺のもの、太いもの→短尺のもの、細いもの
(d)装置別
大型機器→小型機器
実際の作業における要領を下記に列挙する。
(a)布設場所の整備、確認
足場、照明の整備を確認する。配管工事など他職種の状況を確認する。
(b)ケーブルの布設方法が指示されている図面や、電路系統図の内容を確認する。
(c)ケーブルの両端に、誤接続を防止するため、接続先を書いたビニルテープを巻き付けておくとよい。
(d)フライブリッジなどサブ組立を行う場合は、そのときに布設を終わらせておくと作業性がよい。
(e)電路の分岐
(イ)主電路の場合、途中より分岐するケーブルは、できるかぎり電路の上側より分岐する。(図3.3.24参照)
図3.3.24 電路の分岐
(ロ)ケーブルはできる限り交差をさけ、やむを得ず交差するときは、人目につき難い場所で交差させる。(図3.3.25参照)
| (拡大画面:11KB) |
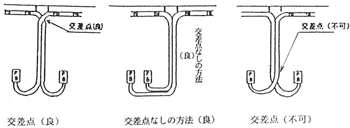 |
図3.3.25 ケーブルの交差
(f)ケーブル貫通部の防水処理は、布設工事の終了を確認したのち行う。
(防水処理を一度で終わらせるため)
(g)安全上の注意事項
(イ)ケーブルの短絡を防止するため、タッピングする場
所から半径50mm以内には、ケーブルを通さないこと。
(ケーブル通し面からのタッピングは良い。)
(ロ)ケーブルの被覆がこすれて磨耗するので、可動部にはクランプしないこと。また、可動部の摺動範囲にケーブルを通さないこと。
(ハ)ケーブルの被覆を傷つけるので、足を踏みつける恐れのあるところに、ケーブルを通さないこと。
(ニ)火災防止のため、蓄電池+(プラス)端子〜メインブレーカー間のケーブルとオイル又はガソリンなどのパイプ及びタンクとは、100mm以上離すこと。
(ホ)火災防止のため、蓄電池+(プラス)端子〜メインブレーカー間のケーブルは、物入れなど紙や布を入れる可能性のあるところには通さないこと。やむをえない場合は物入れの上部を通し、ケーブルに、紙や布が被らないようにすること。
機関室におけるケーブル布設の一例を図3.3.26〜図3.3.28に示す。
図3.3.26 作業灯へのケーブル布設例
| (拡大画面:21KB) |
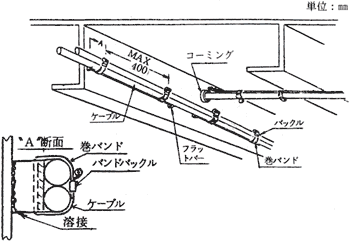 |
図3.3.27 フラットバー(FB)電路の布設例
図3.3.28 カッティングダクトによるケーブル布設例
|