|
3・2 艤装設計
機器の装備場所については、規則上では規定されていないが、以下のように配置するとよい。
(1)空中線部は、他からの妨害を減少させるため以下の点に注意して配置する。
(A)MF/HF用空中線からできるだけ離す。
(B)他のVHF用空中線からできるだけ離す。
(C)レーダー空中線の送信ビーム範囲を避ける。
(D)GPS用空中線はインマルサットの空中線から3m以上離し、かつ、その送信ビーム範囲を避ける。
(2)制御部(含む電源装置、接続箱)は、他の船の動向の情報を得る目的から海図スペースなど通常操船する場所とする。
(3)磁気コンパスとの関係
磁気コンパスとの距離は、機器に記載してある安全距離以上離す。
各種の情報を自動的に送信するために、空中線部及び制御部は次のような航海機器との接続が必要になる。
(1)GPSからのデータ:協定世界時(UTC)、対地針路(COG)、対地速力(SOG)等の情報
(2)ジャイロ/磁気コンパスからのデータ:船首方位、回頭率等の情報
図3・8にGPS受信機とジャイロコンパスと組み合わせた基本構成例を示し、図3・9に、基本構成における結線例を示す。
また、図3・10に、AISから自船位置、他船位置、各船舶の針路、速力等の情報を、ECDIS、レーダー・ARPAへ出力表示し、更にAIS情報をインマルサットで遠距離に伝送できるシステム拡張例を示す。
| (拡大画面:63KB) |
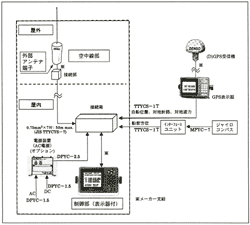 |
図3・8 基本構成(例)
(GPS受信機とジャイロコンパスとの組み合わせ)
| (拡大画面:183KB) |
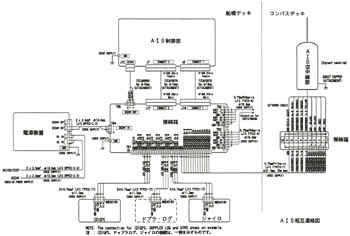 |
図3・9 基本構成における結線例
| (拡大画面:76KB) |
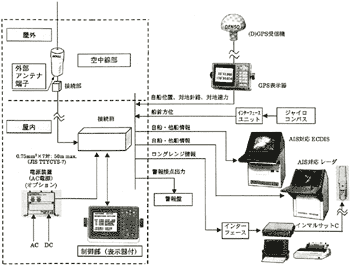 |
図3・10 システム拡張例
(GPS受信機とジャイロコンパスを基本とした拡張例)
|