|
2.2 冷夏・旱魃年の決定
冷夏・旱魃との関連性を調べるためにまずどの冷夏・旱魃年を対象とするか決定する。冷夏といっても北冷西暑というように東北以北だけ冷夏ということも頻繁にある。また旱魃も必ずしも全国一律で起こるわけではない。まずどのような冷夏・旱魃が発生しやすいか調査する。
本研究では夏の気温の経年変化傾向の全国的な分布を調査するため、全国の気象官署のうち1900〜1999年に欠測が1回以下であった地点(58地点)の夏季平均日最高気温を、また降水量を調査するため夏季積算雨量を用いる。日平均気温は1日に数回(時代によって異なる)観測した値の平均値であるが、日最高気温は1回の観測値であるので統計的に均質なデータが得られると考えられる。また降水は間欠的な現象なので短い期間の平均値にすると確率分布が正規分布に従わない可能性があるため、季節毎に積算した。これらの時系列に対し経験的直交関数解析(以下EOFと呼ぶ、多変量解析では主成分解析という)を行った。
図3に夏季平均日最高気温のEOF第1モードのパターンと時係数を示す。第1モードの寄与率は0.681でパターンは南西諸島を除いたほぼ全国で−0.1である。また時係数の上位5番目までを抽出すると、1902、1905、1954、1980、1993年である。この年は表1のような一般の冷害年表でも全国的な冷夏年とされていることから、このモードの時係数が大きいときは全国的に冷夏であったといえる。
同様に夏季積算雨量の時系列に対して行ったEOF解析の結果を図4に示す。寄与率は0.333であり気温変動に比べて低い値である。パターンは西日本を中心に−0.15〜−0.05の値が全国的に広がっている。上位5番目までは1924、1929、1939、1973、1994年である。表1の年表では西日本において旱魃年となっていて、このモードの時係数が大きいときは西日本を中心として全国的な旱魃であったといえる。
以下の調査ではそれぞれの第1モードを中心に解析をする。
表1 冷害・干害年表(気象ハンドブック、1995より抜粋)
| 年 |
冷害/干害 |
| 1900(明治33)年 |
干害(北九州、山陰:5〜7月) |
| 1902(明治35)年 |
冷害(北日本:4〜8月、とくに7〜8月) |
| 1903(明治36)年 |
冷害(北日本:5〜8月)、干害(西日本、東海:7〜9月) |
| 1904(明治37)年 |
干害(西日本、東海:7〜9月) |
| 1905(明治38)年 |
冷害(中部地方以北:4、7〜9月、とくに8月) |
| 1906(明治39)年 |
冷害(東北全般:とくに6、8〜9月) |
| 1908(明治41)年 |
冷害(北海道:4〜8月、9月、とくに5、7、9月) |
| 1909(明治42)年 |
干害(和歌山、愛知、岐阜:6〜8月) |
| 1910(明治43)年 |
冷害(中部〜東北南部:7〜9月) |
| 1913(大正2)年 |
冷害(北海道、東北:5〜9月)、干害(西日本、東海:6〜8月) |
| 1917(大正6)年 |
干害(西日本:6〜7月) |
| 1922(大正11)年 |
干害(西日本、中部日本:6〜9月) |
| 1923(大正12)年 |
干害(近畿、中部日本:5〜8月) |
| 1924(大正13)年 |
干害(西日本、中部日本:6〜8月) |
| 1926(大正15)年 |
冷害(北海道、東北北部:4〜8月)、干害(西日本、中部日本:7〜8月) |
| 1927(昭和2)年 |
干害(近畿、中部日本:5〜8月) |
| 1928(昭和3)年 |
干害(新潟、山形:7〜9月) |
| 1929(昭和4)年 |
冷害(関東北部以北:4〜6、9月)、干害(西日本、東日本:5〜9月) |
| 1931(昭和6)年 |
冷害(東北、北海道:4〜7月、とくに7月) |
| 1932(昭和7)年 |
冷害(北日本:7〜9月、東日本:6月) |
| 1933(昭和8)年 |
干害(西日本:7〜8月) |
| 1934(昭和9)年 |
冷害(北日本:7〜9月)、干害(西日本:6〜8月) |
| 1935(昭和10)年 |
冷害(北日本:5〜9月、とくに7月、東日本:5、7〜9月) |
| 1939(昭和14)年 |
干害(西日本、中部日本:5〜9月) |
| 1940(昭和15)年 |
冷害(北日本:4、6、9月、東日本:4月、8〜9月) |
| 1941(昭和16)年 |
冷害(北日本:4〜9月、とくに7〜9月) |
| 1942(昭和17)年 |
干害(全国:7〜8月) |
| 1943(昭和18)年 |
干害(東北:7〜8月) |
| 1944(昭和19)年 |
干害(西日本:6〜8月) |
| 1945(昭和20)年 |
冷害(北日本:5、7〜9月、とくに7月) |
| 1947(昭和22)年 |
冷害(東日本:5〜6月、北海道:6月)、干害(西日本:7〜8月) |
| 1951(昭和26)年 |
干害(西日本、中部日本:7〜8月) |
| 1953(昭和28)年 |
早冷・いもち病(中部地方以北:とくに8月下旬〜9月) |
| 1954(昭和29)年 |
冷害(北日本:5〜8月、本州:6〜7月) |
| 1956(昭和31)年 |
冷害(北海道:7〜8月) |
| 1958(昭和33)年 |
干害(西日本、中部日本:3〜7月) |
| 1960(昭和35)年 |
干害(西日本、中部日本:7〜8月) |
| 1964(昭和39)年 |
冷害(北海道、青森:6〜9月) |
| 1964(昭和39)年 |
東京都(主要河川・多摩川):給水制限7月10日〜10月1日84日間、東京五輪渇水 |
| 1965(昭和40)年 |
冷害(北海道:4、7月) |
| 1966(昭和41)年 |
冷害(北日本:4,6〜8月、東日本:6〜7月) |
| 1967(昭和42)年 |
干害(西日本:7〜10月) |
| 1969(昭和44)年 |
冷害(北海道:8〜9月) |
| 1971(昭和46)年 |
冷害(北海道:5〜9月、東日本:9月) |
| 1973(昭和48)年 |
全国、中国、四国:昭和14年以来、東北、北陸:昭和17年以来 |
| 1976(昭和51)年 |
冷害(中部地方以北、四国・九州:7〜9月) |
| 1978(昭和53)年 |
干害(全国:5〜9月) |
| 1980(昭和55)年 |
冷害(全国(除沖縄):7〜9月) |
| 1981(昭和56)年 |
冷害(北日本:8〜9月) |
| 1982(昭和57)年 |
冷害(東日本:6〜9月) |
| 1983(昭和58)年 |
冷害(北日本:6〜7月) |
| 1984(昭和59)年 |
干害(山形:6〜9月) |
| 1985(昭和60)年 |
干害(中国〜東北:7〜9月) |
| 1987(昭和62)年 |
東京都ほか(主要河川・利根川、荒川):給水制限6月16日〜8月25日71日間、首都圏渇水 |
| 1988(昭和63)年 |
冷害(東日本:7月) |
| 1991(平成3)年 |
冷害(東日本:8〜9月) |
| 1992(平成4)年 |
冷害(北日本:6〜8月) |
| 1993(平成5)年 |
冷害(全国(除沖縄):6〜9月) |
| 1994(平成6)年 |
干害(ほぼ全国:4〜10月) |
|
| (拡大画面:48KB) |
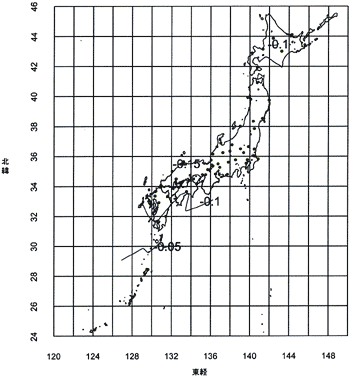 |
(a)重みの分布
| (拡大画面:13KB) |
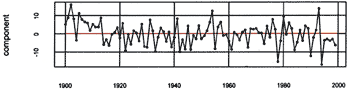 |
(b)時係数
|
図3
|
全国気象官署58地点の夏季平均日最高気温の1900〜1999年の時系列におけるEOF第1モードの(a)パターンと(b)時係数
|
| (拡大画面:46KB) |
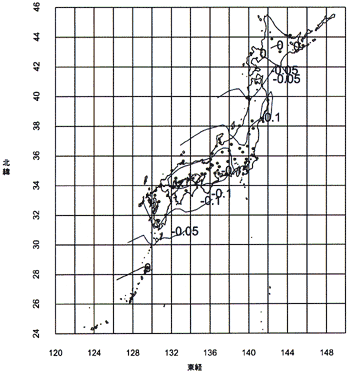 |
(a)重みの分布
| (拡大画面:14KB) |
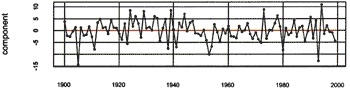 |
(b)時係数
|
図4
|
気象官署58地点の夏季積算雨量のEOF第1モードの(a)パターンと(b)時係数
|
|