|
第2部 海洋変動による冷害・旱魃の調査
近年地球温暖化による気候変動と関連して、気象の変動性の増加が懸念されており気象官署などの長期間観測されたデータを用いた解析が進んでいる。また海洋でも数十年スケールの海洋変動についても研究が進んでいる。
東北地方の冷夏と日本近海との関係はよく調査されている。力石ら(1991)は1970〜1989年の北日本周辺海域の海面水温と八戸における気温の旬平均値を解析して気温変動に海水温が応答しているという結果を得ている(図1参照)。しかし高井ら(1996)はヤマセの発生源はベーリング海からオホーツク海にかけての海洋性極気団であると推測している。したがって日本の冷夏に対してこれらの海域が影響を与えている可能性は依然としてある。またエルニーニョとの関連なども考慮するために更に広い範囲との関連性を調査する必要がある。
図1 ヤマセに対する近海の海上水温の応答
|
八戸の気温偏差と時間をずらした1度格子毎の海面水温偏差との相関を示す。色が濃いほど正の相関が高く、LAGO(同時時間)およびLAG10(10日後)で相関係数が大きい。
|
東北地方では冷夏がよく問題となるが、西日本では旱魃が問題となることが多い。昨年の研究では降水現象の変動性も増加傾向にあることが示され、今後旱魃の発生が多くなる可能性もある。
本調査では、まず調査対象とする冷害年・旱魃年を決定し、それに従って条件抽出法により冷害・旱魃と関連のある海域を選択し調査することとする。図2は研究の流れを示す。
| (拡大画面:50KB) |
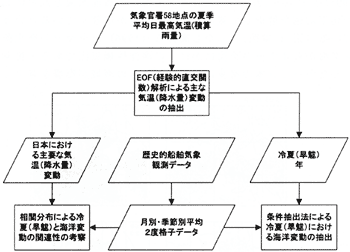 |
図2 研究の流れ
|