|
2.3 海洋変動との関係
2度格子データセットとして平成9年度事業「全球の船舶観測データセットの整備とそれを用いた海洋気候の長期変動の解明」で作成したデータセットに気象庁船舶観測データ(1998〜1999年)から作成した2度格子データを加え、1899年〜1999年の101年2度格子データセットとした。
前章で決定した夏季平均日最高気温のEOF第1モードの上位25年を条件として条件抽出法により1900〜1999年の冷夏年における海面水温偏差を抽出した。冷夏年における海面水温偏差分布の月毎の時間発展を図5に示す。正偏差(負偏差)の海域は日本で全国的に冷夏である時に海面水温が平年より高い(低い)ことを示している。またt−検定により有意水準95%で有意な差をもつ格子を○で示した。赤道から南半球にかけて等値線がないが、これはデータが少なすぎるためである。
全国的に冷夏となっている時期と同じ時期である夏季の偏差分布は、日本近海から北緯40°線にそって日付変更線まで有意な負偏差が伸びている。同じ北緯40°線上で日付変更線から西経160°まで正偏差(有意でない)があり、アラスカ沖に有意な負偏差がある。また8月になると台湾近海に有意な正偏差が現れている。北太平洋における冷夏前年の9月からの時間発展は次の通りである。すなわち、前年9月の日本の東沖にある正偏差海域が北緯40°線に沿って次第に東に伸びていく。これに対応してアラスカ南沖にあった負偏差が次第に小さくなっていくが、春になって北緯50〜60°付近で西に伸びて千島列島近辺に到達する。6月にはこの負偏差が南下して7、8月に日本近海をおおう。8月に台湾近海で発生した正偏差が秋になると北上し、日本〜日付変更線近辺の負偏差を押し上げる。ただし有意な差を示すのは6〜8月だけである。
図5 冷夏年前後(前年9月〜当年12月)の海面水温偏差の時間発展(A〜P)。
偏差分布は隣接した格子の値を平均して平滑化した。
| (拡大画面:64KB) |
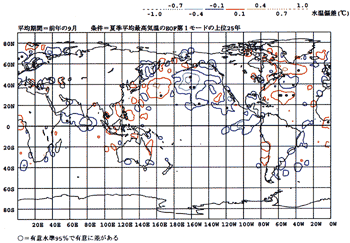 |
(A)前年9月
| (拡大画面:65KB) |
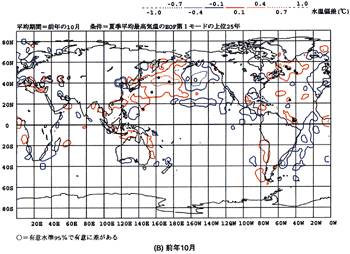 |
(B)前年10月
| (拡大画面:62KB) |
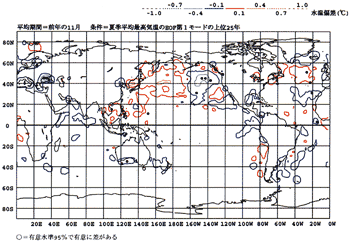 |
(C)前年11月
| (拡大画面:62KB) |
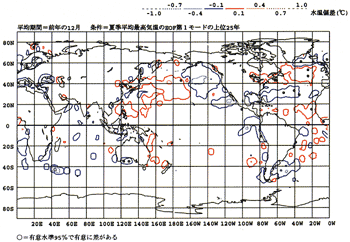 |
(D)前年12月
|