|
3.3 艤装作業における作業要件書
(1)作業要件としての公的資格・免許
前節で触れたように艤装作業では職種やその作業内容が、船殻、修繕船作業同様、以前と比べ大きく変化している。最も大きな変化は、作業の複合化、それに伴う作業者の多能工化である。作業者に多能が要求されれば、当然のことながら、作業遂行に必要な公的資格、必要知識、技能などの作業要件も異なってくる。
造船業に関係の深い資格・免許は、前年度の調査報告書に記載しているので省略するが、実地に調査した結果では、殆どの造船所で絶対に必要とされる安全衛生法上の資格・免許しか取得していないのが実情である。
中には機関整備士、船舶電装士などの民間資格を取得させ、取得者の技能評価に反映させている造船所も見られたが、取得しなくても作業遂行に支障がない限り、取得を積極的に奨励している造船所はほかには見当たらなかった。
国家技能検定には、造船業の技能の伝承、向上に大いに貢献しそうなものもあるが、艤装作業必要資格・技能(試案)には、実情を踏まえて、最低限、必要な資格・免許を公的資格欄に記述した。
艤装作業必要資格・技能(試案)を表3.4に示す。なお、船殻、修繕を含めた詳細は添付資料3に一括して掲載するので参照されたい。
(2)作業要件書
艤装作業はグループ作業が多い。つまり一人では単位作業を遂行することができず、それぞれ異なる作業を複数の作業者が、同時もしくは作業の順序に従って遂行する場合が多い。
また、単位作業の中の具体的な手順の一つ一つを見ると、それぞれ必要とする技能程度が異なる場合が多い。つまり単位作業名だけで技能ランクを特定しにくい面がある。したがい、この単位作業の手順を全部できる作業者がAランクで、その中の手順のこれとこれができる作業者がBランク、補助的な作業しかできない作業者がCランク、といった表現にならざるを得ない。 例を前出(表3.2)の「軸系据付及び付着品取付」で採りあげてみると、
2 軸心整合の 1 中間軸受の
b 中間軸受台板頂部の前後左右取付のネジジャッキと上下ジャッキを使用して推進軸カップリングを基準に船尾側、船首側カップリング外周及び面間の軸心整合を行う。
この作業では、まず船尾側の軸心整合のために、船尾側のダイヤルゲージの位置に1名、中間軸受の位置にそれぞれ1名の作業員が配置につく。
ダイヤルゲージの位置の作業者は、計測技術及び指揮者としての信頼性あるAランクの作業者が必要で、彼の指示に従って中間軸受に配置された作業者が作業する。
中間軸受に配置された作業者の作業は、指示に従ってスパナで8個のジャッキを回すだけであるが、回す量でどの程度中間軸の位置が変化するか、ある程度予想できなければならない。従って、この作業者のランクはBである。
表3.4 艤装作業必要技能・資格一覧
| 職種区分 |
単位作業 |
公的資格 |
図面読解力 |
安全諸規則 |
重量重心算出 |
必要知識使用工器具・装置取扱方 |
作業手順 |
試験手順 |
作業量の推定 |
必要技能(コメント) |
| 鉄艤装品製作 |
鉄艤装品罫書き・切断 |
AW |
ガス |
床ク |
玉掛 |
|
A |
B |
C |
A |
B |
C |
B |
・加工外注傾向、工事の山谷調整で社内で製作する。 |
| 鉄艤装品曲げ |
床ク |
ガス |
玉掛 |
|
|
A |
A |
C |
B |
B |
C |
B |
|
| 鉄艤装品組立 |
AW |
ガス |
床ク |
玉掛 |
|
A |
B |
C |
B |
A |
C |
B |
|
| 鉄艤装品溶接 |
|
|
|
|
|
B |
B |
C |
B |
B |
C |
B |
|
| 鉄艤装品歪取り |
ガス |
床ク |
玉掛 |
|
|
B |
B |
C |
C |
A |
C |
B |
|
| 鉄艤装品取付 |
鉄艤装品取付(ブロック・船体) |
AW |
ガス |
玉掛 |
|
|
B |
A |
B |
B |
B |
B |
B |
|
| 鉄艤装品溶接(ブロック・船体) |
|
|
|
|
|
B |
B |
C |
B |
B |
C |
B |
|
| 鉄艤装品検査準備及び受験 |
玉掛 |
|
|
|
|
A |
B |
C |
A |
A |
A |
B |
|
| 甲板仕上げ |
係留・係船装置据付、調整、運転 |
AW |
ガス |
玉掛 |
|
|
A |
A |
B |
B |
A |
A |
B |
|
| 荷役機械据付、調整、運転 |
|
|
|
|
|
A |
A |
B |
B |
A |
A |
B |
|
| 交通装置、消火装置取付 |
|
|
|
|
|
B |
B |
B |
C |
C |
C |
B |
|
| 通風・空調装置据付、調整、運転 |
|
|
|
|
|
A |
B |
B |
B |
B |
A |
B |
|
| 救命艤装置据付、調整、運転 |
|
|
|
|
|
A |
A |
B |
B |
A |
A |
B |
|
| 冷蔵装置据付、調整、運転 |
|
|
|
|
|
A |
B |
B |
B |
A |
A |
B |
|
| 塗装 |
掃除及び磨き(パワーツール) |
玉掛 |
フォ |
高所 |
|
|
B |
B |
C |
B |
B |
B |
B |
・造船所の規模を問わず全面的に、業者委託 |
| 養生・シンナー拭き |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 塗装準備・塗料撹拌 |
玉掛 |
フォ |
|
|
|
B |
A |
C |
B |
B |
B |
B |
|
| 塗装(エアレス、ローラ、刷毛塗り) |
|
|
高所 |
|
|
A |
A |
C |
B |
B |
B |
B |
|
| 乾燥及び通気機材配置 |
|
|
|
|
|
B |
A |
C |
B |
B |
B |
B |
|
| 塗膜検査、手直し、ガス検知 |
|
|
|
|
|
A |
B |
C |
B |
B |
A |
B |
|
|
| 管製作 |
管罫書き、切断(含自動機械操作) |
ガス |
床ク |
玉掛 |
|
|
A |
B |
C |
A |
A |
B |
B |
・中大手造船所では、機内で専門職施工 ・中小造船所では、加工外注傾向 |
| 管曲げ加工(パイプベンダ操作) |
床ク |
玉掛 |
|
|
|
A |
B |
C |
A |
B |
C |
B |
|
| 管組立 |
|
|
|
|
|
A |
B |
C |
B |
B |
C |
B |
|
| 管溶接 |
NK |
AW |
玉掛 |
|
|
A |
B |
C |
B |
B |
C |
B |
|
| 管仕上げ |
床ク |
玉掛 |
|
|
|
B |
B |
C |
B |
C |
C |
B |
|
| 管検査 |
ガス |
玉掛 |
床ク |
|
|
B |
B |
C |
C |
B |
B |
B |
|
| 配管 |
加工済み管の船内取付(含溶接) |
ガス |
玉掛 |
AW |
|
|
A |
B |
B |
B |
A |
B |
A |
|
| 管支持(バンド)位置決め |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 管型取り |
|
|
|
|
|
B |
B |
C |
B |
B |
C |
B |
|
| 管漏れテスト受験 |
|
|
|
|
|
A |
B |
C |
B |
A |
A |
B |
|
| 通水・通気の確認 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 木艤装 |
船倉内木艤装 |
玉掛 |
|
|
|
|
A |
B |
C |
B |
A |
C |
B |
・規模の大小を問わず、全面業者委託傾向 ・造船所構内での木工職消滅傾向 |
| 居住区木艤装 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 保温・防熱工事 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 防火構造工事 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 床舗装 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 機関仕上げ |
軸系・舵関係見通し・据付 |
AW |
ガス |
玉掛 |
フォ |
高所 |
A |
A |
B |
A |
A |
B |
A |
|
| 主機関積込・組立・据付・運転 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 補助機器台据付・溶接 |
|
|
|
|
|
A |
B |
B |
B |
B |
C |
B |
|
| 補助機器据付・運転調整 |
|
|
|
|
高所 |
A |
A |
B |
A |
A |
B |
A |
|
| 各検査準備及び受験 |
|
|
|
|
|
A |
C |
C |
B |
A |
A |
B |
|
| 予行・公試運転 |
|
|
|
|
|
A |
B |
C |
B |
A |
A |
B |
|
| 製缶 |
製缶罫書き・切断 |
AW |
ガス |
床ク |
玉掛 |
|
A |
B |
C |
A |
B |
C |
B |
・加工外注が一般的で製缶専門消滅 |
| 製缶曲げ |
床ク |
ガス |
玉掛 |
|
|
A |
A |
C |
B |
B |
C |
B |
|
| 製缶組立 |
AW |
ガス |
床ク |
玉掛 |
|
A |
B |
C |
B |
A |
C |
B |
|
| 製缶溶接 |
|
|
|
|
|
B |
B |
C |
B |
B |
C |
B |
|
| 製缶歪取り |
ガス |
床ク |
玉掛 |
|
|
B |
B |
C |
C |
A |
C |
B |
|
| 機械加工 |
機器台表面仕上げ加工 |
玉掛 |
|
|
|
|
A |
B |
C |
A |
A |
A |
B |
・加工外注が一般的になり、構内での機械加工の専門職は消滅傾向 |
| 推進軸切削加工 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 推進軸路ボーリング |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他機械加工 |
|
|
|
|
|
|
|
|
B |
B |
B |
B |
|
| 電気艤装 |
電路取付・溶接 |
AW |
ガス |
玉掛 |
フォ |
高所 |
B |
B |
C |
B |
B |
B |
B |
・中大手造船所では、専門職存在するも、中小造船所では全面的に業者委託傾向にあり、専門職消滅傾向 |
| 電線敷設 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 航海計器据付・調整・試運転 |
|
|
|
|
|
A |
B |
C |
A |
A |
A |
B |
|
| 制御機器・盤据付・調整・試運転 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 船具・操船 |
進水準備 |
玉掛 |
フォ |
高所 |
|
|
B |
A |
B |
B |
B |
C |
B |
|
| 曵船作業 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注水・排水作業 |
|
|
|
|
|
|
B |
C |
C |
C |
C |
B |
|
| 霧具加工 |
|
|
|
|
|
|
B |
C |
B |
B |
C |
B |
|
| 保温・防熱 |
倉内防熱 |
玉掛 |
フォ |
|
|
|
A |
A |
C |
B |
B |
C |
B |
|
| 管保温・防熱 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 機器類防熱 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【略号】王掛:玉掛技能者 有機:有機溶剤作業主任者 ガス:ガス溶接技能者 プレ:金属プレス加工技能者 鉄工:鉄工技能者 はい:はい作業主任者
高所:高所作業車運転技能者 フォ:フォークリフト運転技能者 足場:とび技能者 床ク:床上操作式クレーン運転技能者
小ク:小型移動式クレーン運転技能者 NK:NK溶接資格者 AW:アーク溶接特別教育修了者 配管:配管技能士 塗装:塗装技能士 ぎ装:船舶艤装技能士 |
| 【注】図面読解力:船舶構造図や施工要領書が正確に読み取れる |
| 安全諸規則:造船所における基本的な安全衛生遵守事項を知っている(全船安 H6.7「安全衛生相互点検チェックリスト」 |
| 重量・重心算出:単品部材や組立ブロックの重量、重心が推定できる |
| 工器具・装置取扱法:使用する工器具、機械、設備の特徴と危険性および取扱方法を知っている |
|
また、造船所の設備、船種の違いによる作業内容の相違、必要技能の難しさの差異が出る。例えば機関仕上げで、主機関を一体搭載するか、分割搭載をするかで必要とする技能が異なる。一体搭載の場合は搭載後すぐ据付作業に入れるが、分割搭載の場合は据付作業の前に組立作業を必要とし、組立作業完了後据付作業の順序になる。組立作業の場合は、主機関に関する相当の知識を必要とし、決められた組立の手順、方法を熟知し、相当の熟練も必要とする。
据付作業も主機や発電機、揚錨機に鋳鉄のライナーの代わりに使用されるようになった合成樹脂を使用すると、ライナーのマイクロメータによる寸法計測、陸揚げして工作機械による切削、船内におけるグラインダーやヤスリによるすり合せの作業が、堰作り、合成樹脂の流し込みだけの作業で、さして高度の技能を必要としなくなる。
船種の違いによる差は、例えば船体艤装の場合でハッチカバーをとりあげてもバルクキャリアと冷凍船では要求される品質が異なるため、必要とする技能も当然差が出てくる。
配管では、ケミカル船の場合、ステンレスに対する技能が要求される。
さらに設備や治工具の違いも考慮しなければならない。
造船所の訪問調査で設備や過去のやり方で差が見られたものは、例えば船尾管のボーリングで造船所の機関仕上げの作業者が施工する場合や、専門業者に一括請け負わせるところもあった。
特に顕著な差が見られたのは配管で、管系統図だけで、管配置図や一品図なしで管を加工し、取り付けを行う場合、頭の中に管の配置を描き、管の寸法を決定してパイプベンダーを使用して曲げ加工を行い、フランジ、ピース類を溶接し、仕上げを行う。これらの作業で、型棒、金型、スケッチで寸法をとるのが標準作業となっている造船所があった。これは、今日貴重な技能で、特に複雑な機関室の配管では得がたい技能である。管配置図や管一品図を作成する設計のコストを削減できるので、ある程度の小型船では相当のコストダウンが期待できる。
修繕船の場合は、主機関の解放・点検・修理・組立が主体となるので、主機関の据付、軸系工事や機器の運転の技能は殆ど必要はない。新造船の場合はその逆となる。
以上のことから作業要件書は、種々の条件により異なる必要技能を詳細に、全部網羅することは必ずしも一般的でないので、ある程度共通する単位作業についてのみ記述するのが妥当と思われる(表3.5 機関仕上げの作業要件(部分)。詳細は、添付資料1「機関仕上げ」参照)。
表3.5 機関仕上げの作業要件(部分)
| (拡大画面:119KB) |
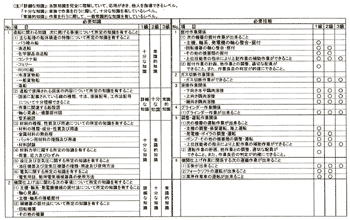 |
|