| (拡大画面:78KB) |
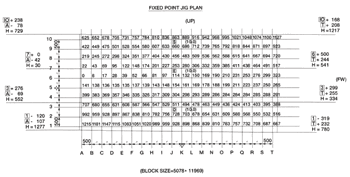 |
図5.1.6 定点治具図
並べる板継枚数はD×E×Sの3枚で、板厚はいずれも10.0([図5.1.4 ピン治具上端]の図のHがA点なので、この量で治具高さを近似的に補正する)。
シームとバットの交点は、□内に記された最短位置定点からの±シフト値で示され、その点の高さ=Hで与えられている。
ピン治具を採用せず、つど支持材を準備するのであれま、配置を定点とする意義はなく、直接シーム位置支持とする方がよい。
この在来方式を[図5.1.7 シーム治具]に示す。
縦位置(イ)(ハ)(ホ)がシームで、(ロ)(ニ)は板央の補助位置、(ロ)位置は治具定盤の基線を兼ねている。横位置はフレーム線が選ばれ、支持点は基線からの追い寸法で指示される。
支持高さは、その近傍に( )内に示され、その数値を眺めてみると、組立姿勢は首端が低く尾端が高い。いわゆる「正面ナリ」、つまり  に平行の定盤面で採寸しているのが判る。 このように外板全体の傾きが均されていず、組立サイドに立てば、いささか不都合であるが、フレーム面が定盤に鉛直で解りやすく、手作業現図では、この程度が実際的であろうか。
ちなみにブロック建造法初期の曲り外板板継支持は、どうしていたか。
ブロック板継全体を一枚の外板と見做した見透曲型に相当する大きな治具型を組付けていた。外板面は削り合わせでなく、当然に角出し(つのだし)だった。
| (拡大画面:53KB) |
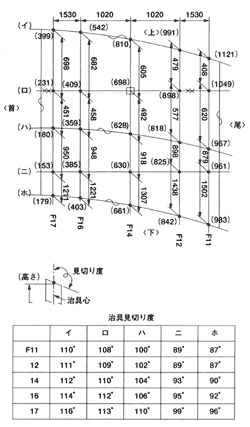 |
図5.1.7 シーム治具
この型を組立定盤上に立揃えて、空間に外板面を仮想できるようにし、それに合わせる適当な支持材を整備したものである。
|