|
4. 定規
定規は、一次元[線]実寸法の指示表現に用いるのに便利であり、精度が高い。
また「一部型」を援用したり、マーキン手順の約束事:曲り外板の基線展開・形鋼肋骨の逆直線曲げ・幅/長さ兼用・平行二本基線による内構の「当り位置」設定・・・などを確立すれば、複雑な形状も与えることができる。したがって型と重なる役割を持つ。
定規そのものは一般に型に比べ、作成や取扱いが簡単であるが、マーキンには一見判り難いのは確かで、単純な形状や長尺・大型のものに適する。
次ページ見開きの[図4.0 平行二本基線によるマーキン]は、その実例で、長さ7m余×幅約1.4mの曲り外板付きトランス・ウェブが、[表4.0 二本基線寸法表]を押さえることで、その形状を正確に表現できる。このような大きさでは、木型・紙型にしろ、型マーキンは誤差が出やすい。
つまりNCマーキン切断機がなくても、プロッターとラインプリンターの出力で、高精度の数値現図が適用できたのである。
定規作成の作業は、定規を机高さの架台(定規定盤ともいう)に載せて、椅子掛けの姿勢で、記入用具だけでできる。椅子には、横移動と回転できる機能が好ましい。
| (拡大画面:67KB) |
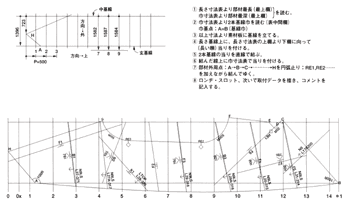 |
図4.0 平行二本基線によるマーキン
| (拡大画面:130KB) |
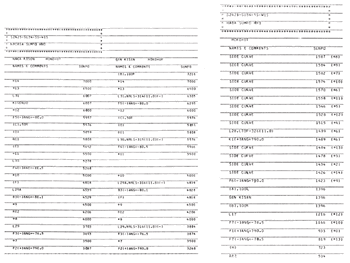 |
表4.0 二本基線寸法表
4.1 角定木、平定木、テープ
この呼称は、定規の素材形態の区分である。
定規書き込みの事例を[写真4.1.1 スティール・テープ]に示す。
写真4.1.1スティール・テープ
直線上の距離寸法は、帯状のものならいずれでもよく、同じマーキンとなるが、曲線の表現では、厳密には異なる。
すなわち、バッテンとして撓む定木は、カーブ形状とガース長を同時に与えることができるが、巻き取れるように軟らかいテープでは、曲線近似の折線を点列として「当り」が付けられるだけで、あと別途「当り」を連ねるカーブを付加することになる。もっとも点列のトレランスが小さければ差異は無視できる。
また定木でのガース寸法拾いは、[図4.1 定木による採寸]のように、凹面で当りを付けるのが、マナーとされてきた。
拾った時より定木の撓みが減ると、ガースは若干長くなる。この現象は板厚中性軸や加工収縮を考え合わせると都合がよい。ちなみに定木厚を8ミリで、この要領でガース長を拾うと、10ミリ厚鋼板のプレス曲中性軸を求めたことになる。(NA:中性軸については、別冊『現図展開』参照)
図4.1 定木による採寸
平定木は素材上から長さが限られるが、幅がテープより広く書き込みがしやすい。
4.2 金取、仕上
こちらは定規表現の目的区分である。
一般には部品仕上がり形状を与えるのであるが、曲加工後やブロック板継後に再マーキンする場合を「仕上げ」、最初の取材マーキン用を「金取」、と冠して区別している。
仕上げ定規を金取に兼用してもよく、その場合は色を変えた記述にすると判りやすい。
組立工程でのマーキン用を、「アセンブリ定規」と称することもある。
展開や加工ならびに組立収縮の精度を高めて、この二重手間は減らしていきたい。
|