|
3 国際標準化事業
我が国の船舶関係工業が、これまでどおり世界において重要な地位を保つために、積極的に国際規格を国内規格に受け入れていくとともに、戦略的見地に立って、また、国際貢献の立場から我が国の技術を国際規格に反映させていくことが重要であります。そこで本会では、次のような国際標準化活動を行っております(TC8幹事国業務につきましては、 8、10〜11ページを参照して下さい)。
| (拡大画面:162KB) |
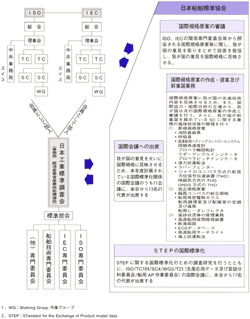
|
ISO(国際標準化機構)における船舶関係の国際標準化に関する審議並びにTC8「船舶及び海洋技術」専門分科会、TC8/AG(諮問グループ)、TC8/SC6「航海」及びTC8/SC9「一般要件」の各分科委員会の幹事国業務は、本会が行っております。本会に関係のある委員会の組織図は次のとおりです。
| (拡大画面:254KB) |
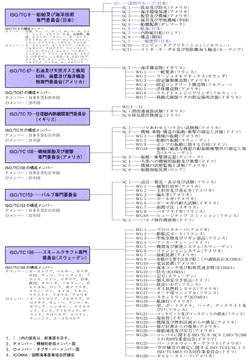 |
IEC(国際電気標準会議)における船舶関係の国際標準化に関する審議等の業務は、本会が行っております。本会に関係のある委員会の組織図は次のとおりです。
| (拡大画面:111KB) |
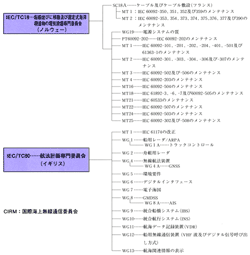 |
IOSでなくISO?
ISOの英語名フルネームは、International Organization for Standardizationです。そこで何故IOSでなくISOなのかという疑問がわくと思います。実は、ISOは、ギリシャ語の‘isos’からとられたもので、「相等しい」という意味があります。このギリシャ語の由来する‘iso-’の接頭語をもつ英語もかなりあり、例えば、isotope(同位元素)、isobar(等圧線)などがあります。
むかし、国際標準化を推進した先人たち(ISOは1947年に発足)が、‘ISO’を選択したことには、「相等しい」、「平等の」などの概念をとおして、「標準」あるいは「標準化の推進」を考えていきたいという思いが込められていたということです。ISOの三つの公用語である英語、フランス語、ロシア語のイニシャルから「国際標準化機構」の略称をとった場合の混乱を避けることも念頭にあったようです。
|