|
2.2 学習指導要領及び同解説における海洋の扱い
次に、教科書の分析に当たって重要な『学習指導要領』について若干の分析を試みる。ここで対象にしているのは次のもので、小中高校までを取り上げた。
| −小学校 |
生活科 |
|
| −小学校 |
社会 |
第3学年及び第4学年 |
| −〃 |
〃 |
第5学年 |
| −〃 |
〃 |
第6学年 |
| −小学校 |
理科 |
第4学年 |
| −〃 |
〃 |
第5学年 |
| −〃 |
〃 |
第6学年 |
| −中学校 |
社会 |
地理的分野 |
| −〃 |
〃 |
歴史的分野 |
| −〃 |
〃 |
公民的分野 |
| −中学校 |
理科 |
第1分野 |
| −〃 |
〃 |
第2分野 |
| −高等学校 |
地理歴史 |
世界史A |
| −〃 |
〃 |
世界史B |
| −〃 |
〃 |
日本史A |
| −〃 |
〃 |
日本史B |
| −〃 |
〃 |
地理A |
| −〃 |
〃 |
地理B |
| −〃 |
公民 |
現代社会 |
| −〃 |
〃 |
政治・経済 |
| −〃 |
理科 |
理科基礎 |
| −〃 |
〃 |
理科総合A |
| −〃 |
〃 |
理科総合B |
| −〃 |
〃 |
物理I |
| −〃 |
〃 |
化学I |
| −〃 |
〃 |
生物II |
| −〃 |
〃 |
地学I |
| −〃 |
〃 |
地学II |
|
表3は、左欄が「学習指導要領」に記載されている項目等で、中欄が「学習指導要領の解説」に記載されている内容である。それに対して、右欄は本調査の実施側で考えた、“触れられるのが望ましい内容”を記載したものである。
したがって、右欄はとりあえず書き込みをした状態であって、本来ならば、この部分についての関係方面からの英知の結集が必要な部分である。
表3 学習指導要領及び同解説に含まれる海洋(あるいは水域関係)関連事項・記述と望ましい内容
| 学習指導要領の項目等 |
解説 |
触れられるのが望ましい内容 |
| (5)身近な自然の観察、季節や地域の行事にかかわる活動 |
・身近な自然の例−海 |
・海、魚 |
|
| 小学校 社会 第3学年及び第4学年 |
| (拡大画面:23KB) |
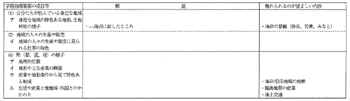 |
| 小学校 社会 第5学年 |
| (拡大画面:22KB) |
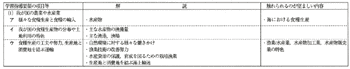 |
| (拡大画面:15KB) |
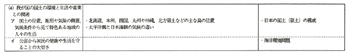 |
| 学習指導要領の項目等 |
解説 |
触れられるのが望ましい内容 |
(1)我が国の歴史上の主な事象−(遺跡や文化財、資料などの活用)
ア 農耕の始まり、大和朝廷による国土の統一 |
|
・農耕のみでなく漁労も
・貝塚と古海岸線
・生活文化の海を介した伝播 |
(3)世界の中の日本の役割
イ 我が国の国際交流や国際協力の様子及び平和な国際社会の実現に努力している国際連合の働き |
|
・海洋法条約をはじめ、海洋汚染防止、海洋資源保護などに関する国際的な取り決め |
|
| 学習指導要領の項目等 |
解説 |
触れられるのが望ましい内容 |
(2)水が水蒸気や水になる様子の観察、水の状態変化
イ 水面や地面などからの水の蒸発 |
|
・海面からの水の蒸発 |
|
| 学習指導要領の項目等 |
解説 |
触れられるのが望ましい内容 |
A(2)魚を育てたり人の発生−動物の発生や成長
ア 魚には雌雄があり、生まれた卵は日がたつにつれて中の様子が変化してかえること。 |
|
・魚の一生の例示 |
B(1)物を水に溶かし、水の温度や量による溶け方の違いを調べ、物の溶け方の規則性についての考えをもつ。
イ 物が水に溶ける量は水の量や温度、溶ける物によって違うこと。また、この性質を利用して、溶けている物を取り出すことができること。 |
・水を蒸発させて水の量が減ると、溶けていた物が出てくることなどをとらえるようにする。 |
・海水からの塩分の抽出(製塩法) |
|
| 学習指導要領の項目等 |
解説 |
触れられるのが望ましい内容 |
C(1)土地のつくりや土地のき方−土地のつくりと変化
イ 地層は、流れる水の働きや火山の噴火によってでき、化石が含まれているものがあること。
・化石は地層が水の作用でできたことを示す程度 |
・貝などの化石 |
・海にたまる土砂→地層
・海にすんでいる動物の化石 |
|
|