|
船とカレンダー
われわれの仲間は上陸したとき、今日は何曜日かとたずねた。ポルトガル人の答えは、木曜日だということだった。われわれはひどく驚いた。われわれにとっては、その日は水曜日だったからである。どうして間違ってしまったのか、われわれにはわからない。とにかく、水先案内人のアルボと私は一日も欠かさずに航海日誌と日記を付けていたのである。
上の文章は、マゼラン海峡を発見し、世界一周航海を成し遂げた、マゼラン(フェルデン=デ=マガインリャス)の一行が、最後の寄港地、アフリカ西端のサンチャゴ島へ上陸したときのことです。(1522年7月)
スペインを出港し、西へ西へと進んでいくうちに、どういうわけかカレンダーから一日が消えてしまったのです。
なぜなのでしょう。
あなたにはわかりますか?
答えは、“日付変更線(ひづけへんこうせん)を通ったから”、なのです。
今では、すっかり海外旅行もおなじみになって、時差(じさ)や日付変更線を、経験している人も多いと思いますが、この航海によって初めて、地球が球体であることが証明され、日付変更線が必要であることが実感されました。
夏場に飛行機の直行便で日本からニューヨークヘ行きました。
東京を正午に出発し、13時間も空を飛びました。ニューヨークに着いたのは同じ日の正午でした!
他にも、タ方にテレビで生中継を見ているはずがテレビの向こうは次の日の朝だったり・・・
なんとも不思議な感じがしますね。
私たちが現在、通常の生活で意識している時刻は、皆さんの時計が示している時刻、ただ1つです。
ところが、左の例のように、場所によって時間が違うことがあります。
太陽は東から昇って西へ沈む
地球は、西から東へ自転しているために、夜明けは地球上で、東にある土地ほど早くなります。そこで、各地点で固有の時刻というものを、考えることができます。これを地方時(ちほうじ)といいます。
各地点によって地方時を使用すれば、それぞれの時間も変わってしまい、混乱してしまうので、国や地域で、代表の子午線(しごせん)を基準にして時を考えます。この基準となる時を、その国や地域の標準時(ひょうじゅんじ)といいます。日本では、兵庫県明石市を通る東経135度を標準子午線(ひょうじゅんしごせん)とし、この子午線上の地方時を、日本標準時(JST)としています。
・子午線(しごせん)・
地球の両極、北極と南極を通る線のこと。経度を測る基準となる。
世界共通の基準は、イギリスのグリニジを通る子午線としました。グリニジ子午線(経度0)における地方時をグリニジ時といい、これを世界時(せかいじ)(UT)としました。
地方標準時(ちほうひょうじゅんじ)は、グリニジから東(東経)へ向かう時は(+)、西(西経)へ向かう時は(−)、というようにグリニジ子午線から15度ごとに世界時を1時間加減しています。(日本標準時は世界時より9時間早い)
するとグリニジの地球の裏側、つまり東経・西経ともに180度の子午線で、1日のずれができてしまうので、ここを基準に日付変更線(International date line)としました。
| (拡大画面:53KB) |
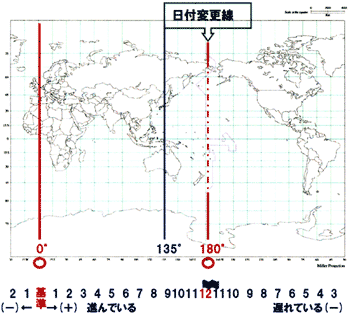
|
そのため日付変更線の西側と東側では一般に日付が一日違い、西側が東側より一日進んだ日付となっています。
マゼランの一行のように、太平洋を航行してこの線を東から西へ横切った時、その船の使用日付を西側の日付と一致させるためには、日付を一日進めなければなりません。そのため、マゼラン達のカレンダーから一日消えてしまったのです。
(逆に西から東へ横切る場合は日付を一日後戻りさせる必要があります。)
|