|
船の時間
飛行機で海外へ行くと、突然時間が変わってしまい、時差ぼけになってしまいますが、船の場合はどうでしょうか。
何日も大洋の真中を航行している船の中でも、時間は確実に流れています。船には船の時間があり、これを、船舶使用時(せんぱくしようじ)といいます。
しかし、マゼランの一行が、カレンダーから一日消えてしまったことに全く気付かないように、船の場合、ゆっくりと時刻が修正されていくので、時差ぼけになることはありません。
船の時間は、多くても1日に1時間程度しか修正されません。修正の仕方には、(1)時間帯に合わせる方法、(2)毎日一定時刻に修正する方法の2種類があります.
(1)海の上でも、船がそれぞれ勝手な時を使っていると、不使な事がおきてきます。そこで、15度ごとの子午線で区分した時間帯を使って、船が経度で東に15度進めば「船内時を1時間進める」という方法をとります。
15度ごとの子午線を通るのは、夜だったり昼だったり、何日も通らなかったり・・・というように修正する時刻もバラバラになってしまうので、船の中での生活が混乱してしまいます。
(2)そこで、現在船が走っている経度や、次の港までの距離や日数も考えて、毎日同じ時刻に30分単位(30分か1時間)で変更することにします。皆が起きていて、生活や仕事に支障の少ない9時頃修正するのが一般的です。船内で混乱も起きないし、細かく修正もできます。
正確な時間は船のためにつくられた
大海原に乗り出したとき、船で安全に航海をするためには、現在の位置をだすことが必要です。自船の位置を測るには、六分儀などを使って、太陽や月、星などの天体の高度を測定し、観測時刻とその天体の予報位置とから、計算によって求めます。(こうやって観測点の経度、緯度を求めて、進路を定めることを天文航法という)
時計の少しのずれが、現在地の大幅なずれとなり、多くの海難事故につながりました。このため正確な時計が絶対必要でした。そこで完成したのが、航海用の高精度の時計「マリンクロノメーター」です。
(イギリス人ジョン・ハリソン1759年)
それまでの時計
(1)振り子時計→船が揺れると使えない
(2)ゼンマイ時計→気温の寒暖が精度に影響
(3)したがって船の時計には砂時計が使われていました。
ところが→見張りに疲れた船員の中には、交代時間を早めるために、砂時計を意図的に早めに反転させる不心得者がいた。この時計もあまりあてになりませんね・・・。
昔、船の上で時間を測る時計として使われていたのは30分計の砂時計で、30分計をひっくりかえす度にタィムベルを打ち鳴らして時間を船内に知らせていました。
タイムベルの打ち方
| 12時半 4時半 8時半 |
1点鐘「カン」 |
| 1時 5時 9時 |
2点鐘「カンカン」 |
| 1時半 5時半 9時半 |
3点鐘「カンカン カン」 |
| 4時 8時 12時 |
8点鐘「カンカン カンカン カンカン カンカン」 |
というように、12時、4時、8時には2つずつ4回の8回鐘を打ち、それから30分経ったとき(12時半、4時半、8時半)から1点鐘となり、以後30分経つごとに1つずつ教を増やしていきます。
ところがタ方は海坊主が出てくるので、海坊主をだます為に不規則に打ちます。(6時半は本来5点鐘となるが1点鐘となります)昔の言い伝えからきていますが、今でも受け継がれています。
私たちはカレンダーで一日一日を数えていますが、一体一日って何なのでしょうか
私たちは太陽の動きをみて生活しています。
| (拡大画面:15KB) |
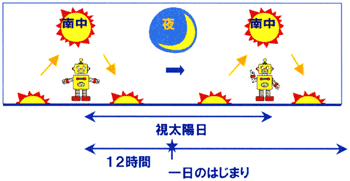
|
昔の人は、太陽が頭上に最も高く昇ったとき(太陽が真南にくる瞬間で、南中(なんちゅう)という)をもって、一日の中心である正午を定め、次の日、再び太陽が頭上にくるまでのひとめぐりを、一日として計りました。つまり、太陽の南中から南中までで、この時間を視太陽日(したいようび)といいます。
すると、日付が昼間変わってしまうことになり、生活しにくくなってしまいます。そこで、太陽が南中したときを昼12時とし、一日のはじまりは、そこから12時間足したところとしました。視太陽時は日時計の示す時刻です。
ところが地球の軌道は楕円で、しかも軌道の速度は一定でない!太陽も天の赤道に対して23°26’傾いた黄道上を一年かかって移動しているので速度も一定でない!
そのため視太陽日の一日の長さは一年を通してみて実は一定ではありません。一日の時間が日によって違ってしまうのでは困ってしまいます。
そこで仮想(かそう)の太陽(たいよう)を考えました。(視太陽時の一日の長さを平均した。)
常に一定の速度で動く仮想太陽を平均太陽(へいきんたいよう)と呼ぶことに決め、この平均太陽が南中してから次に南中するまでの時間を平均太陽日としました。一日の始まりは平均太陽が南中してから+12時間経過したところからで、平均太陽日をもとに決められた時刻を平均太陽時といいます。
今、私たちが生活している一日は平均太陽日です。
|