|
2.エンジンの構造・機能
エンジンはそれぞれの用途によって各種各様の構造を持っているが、その基本原理はいずれも同じであり、その構成も大体似た部分から成り立っている。2・40図及び2・41図に機関の断面図の一例と部品名称をしめす。本書は機関の主要構成部品を下記の如く分類し、構造と機能を主に整備や取扱上のポイントについて記した。
1. エンジン本体部
2. エンジン運動部
3. 動弁装置
4. 潤滑装置
5. 冷却装置
6. 燃料装置
7. 調速装置
8. 点火装置
9. 始動装置
10. 過給機
11. 逆転装置
12. リモートコントロール装置
13. 計器および警報装置
| (拡大画面:80KB) |
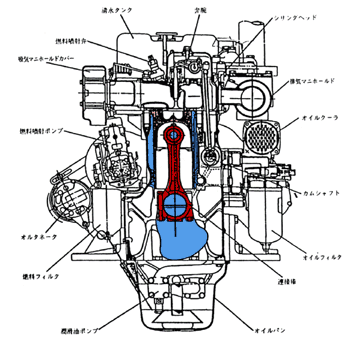 |
2・40図 機関横断面
| (拡大画面:172KB) |
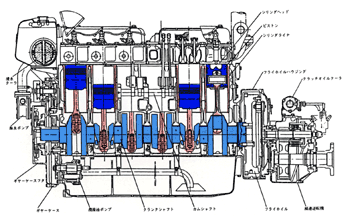 |
2・41図 機関縦断面
2.1 エンジン本体部
エンジン本体部はシリンダ、クランクケース、シリンダライナ、シリンダヘッド等で構成されている。
1)シリンダとクランクケース
シリンダとクランクケースはエンジン構成のベースであり、部品としては最も大きなものであり、大型ディーゼルエンジンでは別々に造られるが、小中型ディーゼル及び4サイクルガソリンエンジンでは一体で造られるものが一般的である。又、2サイクルエンジンでは一般に各シリンダ別体形である。
ディーゼル及び4サイクルガソリンエンジンのクランク軸の支持方法としては、台板式とハンガタイプとがある。台板式の場合はシリンダをシリンダブロック又はシリンダ架構と呼び、クランクを支えているクランクケースを台板又はベッドと呼んでいる。ハンガタイプの場合はシリンダにクランク軸を吊り下げた構造になっているため、シリンダをクランクケース又はシリンダブロックと呼び、下部のオイル溜まりをオイルパンと呼んでいる。
シリンダブロックの材質は般的に鋳鉄や特殊鋳鉄であるが、ガソリンエンジンでは最近軽量化及び冷却効率向上のためにアルミニュウム合金として鋳鉄製シリンダライナを使用したブロックが増えている。
シリンダの構造を2・42図に示す。
| (拡大画面:31KB) |
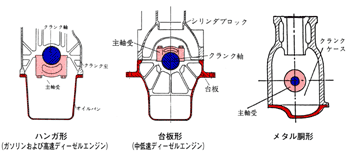 |
2・42図 シリンダの構造
2)シリンダライナ
シリンダライナは、シリンダヘッド、ピストン、ピストンリング等とともに燃焼室を形成する部品の一つで、機能面、耐久性の面からも非常に重要な部品である。
シリンダライナの摩耗は、機関性能の低下、潤滑油消費量の増加等、分解整備の間隔に大きく影響するので、耐摩耗性に優れたパーライト鋳鉄や、ボロン、燐、などを含んだ合金鋳鉄が使用されている。
シリンダライナには2・43図に示すように、ライナの外周を直接水で冷却する湿式ライナ(ウエットライナ)と間接的に冷却する乾式ライナ(ドライライナ)およびシリンダー体形とがある。
2・43図 シリンダライナの種類
(1)シリンダー体形
シリンダー体形は2サイクル及び4サイクルガソリンエンジンで多く用いられているが、耐摩耗性ではライナ形より劣る。
(2)乾式ライナ
乾式ライナは、炭素鋼製の薄い円筒状のもので一般にはスリーブと呼ばれており、このスリーブとシリンダブロックとの嵌合にルーズとタイトの2種類がある。ルーズタイプのスリーブは手で挿入できるが、タイトタイプのスリーブは油圧プレス等でシリンダブロックに圧入後ホーニング研磨して仕上げる。
乾式ライナは冷却水への熱伝導が湿式ライナに比べ悪いという欠点があるが、水漏れの恐れが無くシリンダの剛性も高くなるので、小形高速ディーゼルエンジンに多く用いられている。又ガソリンエンジンのアルミニウム合金ブロックに用いられている。
(3)湿式ライナ
湿式ライナはシリンダライナの交換が容易に行え、ライナの冷却も良好であるため舶用ディーゼルエンジンにはこの構造が多く採用されている。又ガソリンエンジンでは、アルミニウム合金製ブロックに採用されている。
シリンダライナの内壁はピストン及びピストンリングが円滑に摺動出来るように精密な加工(ホーニング研磨)がなされ、上部は燃焼ガスのもれを完全に防止するため、シリンダヘッドとの間にガスケット又は銅パッキンを介してヘッドボルトで締め付けられ、燃焼室の気密性を保持すると共にシリンダブロックのインロ部でしっかりと支えられている。スカート部は冷却水がクランクケース内へ漏れぬように2〜3本のOリングが入れられ、スカート部は下方へ自由に熱膨張しうるような構造となっている。(2・44図参照)
2・44図 湿式ライナの水密構造
(ライナの摩耗について)
ライナの一番摩耗しやすい位置は、ピストンが上死点にある時のトップリング位置であり、つぎはピストンが下死点位置にある時のトップリング位置である。
従ってライナの内径計測は、前記2点及び中間位置を、クランク軸方向及びこれと直角方向をシリンダゲージで計測する。(2・45図参照)
2・45図 ライナの摩耗と計測位置
|