8月8日(水)
本日のスケジュール・内容
1) 地方保健省への表敬訪問・講義
2) ホセ・ロドリゲス記念病院見学
3) フィリピン保健省(Department of Health)訪問
4) Lanuza Health Center訪問
1) 地方保健省への表敬訪問・講義
はじめに、OIC-DirectorのDr. Rosario H. Famaranより講義を受けることができた。
フィリピンの国家形態、医療、Region 4 (フィリピンでは地域を数字で標識する)での近年の健康情勢、使命、目標、公約などについての講義だったが、それ以上にDr. Famaranは愛情あふれるスマイルと眼差しで、講義で得る知識に大きな意味のあることを一同に教えてくださった。
フィリピンでは、地方自治体の力が強く、各地方に多くを任せている。フィリピンの全人口は約1,302万人で、11州の中に10都市、213地方自治体、5,610バランガイ(村落)を持つ。その中での医療従事者は約3万人であるが、Barangay Health Workerと助産婦の数は桁はずれに多く、この国の医療において大きな役割を果たしていることが伺えた。そして、これらの成果として、Region 4では、死亡率・幼児死亡率・低体重児率とも徐々に減少している。罹患率の高い疾患としては呼吸器感染症が非常に多く、次いで下痢症が挙げられていた。死亡率の高い疾患としては循環器疾患、肺炎が多く、幼児では肺炎、母体では分娩後出血が多いようだ。Region 4での目標は健康情勢の向上であるが、特に(1)伝染性疾患流行の制御、(2)退行性疾患の発生減少、(3)栄養不良児の減少、に力を入れている。また、組織の能力の向上、公衆の健康への自覚、認識の向上などが挙げられた。日本と比べて伝染性疾患が多く、確かに旅行中もデング熱や狂犬病に対する注意が必要だった。
2) ホセ・ロドリゲス記念病院(ハンセン病病院)見学
a) 講義・病棟見学
b) 研究室見学・人形作成販売所見学
a) 講義・病棟見学
到着後、ハンセン病に関するパネルが展示されている部屋でしばしの休憩を頂き、Dr. Dave Elvin G Sanchezによる講義を受けた。ハンセン病の病態生理、治療、患者に必要とされるサービスなどについてお話しいただいた。フィリピンでは1985年にMDT(Multidrug Therapy)のキャンペーンが開始され、その時点では38,000人の登録患者がいたが、1997年の終わりには治療中の患者が8,000人となり、また新たな強力なキャンペーンも始まり、今後有病率のさらなる減少も期待される所である。ホセ・ロドリゲス記念病院では患者への精神的サービスとして、シャペロンと修道女の方に住み込んでもらい、また、いつでも近くの教会から牧師さんに来てもらう事ができるようになっている。フィリピンの人々の精神面において宗教はとても大きなものと思われた。
講義終了後、Dr. Remigio B. Reyesに病棟を案内して頂いた。病院の敷地内には緑があふれ、建物はゆとりをもって建てられたと思われ、とてもゆっくり時間が流れているように感じた。病棟は一般病院としての機能も持ち、形成外科・皮膚科に加えて、産科・婦人科・内科・眼科・救命救急科があった。多くの患者が隔たりなく入院しており、あまり閉鎖された空間とは感じられなかった。また、ホセ・ロドリゲス病院の名前に、Dr. Jose N Rodriguezという著名人の名前を拝借することで、認知度を上げる目的があるという話も聞いた。
その後、一同は理学療法科・作業療法科に案内され、牽引療法・温熱療法・リハビリ療法などの説明を受けた。それぞれの療法に使う装具の使い方、作り方など細かく教えて頂く事ができた。この病院での作業療法のスケジュールは、午前を主な医療的行為に、午後を患者のレクリエーションの時間に当てている。レクリエーションは患者の長期入院による社会性喪失を避け、QOLの向上を目的として行われている。ハンセン病患者は疾病の社会的特殊性より、必要以上の長期入院を強いられる場合がまだ多いのが現状であるが、社会に向けてのアプローチは勿論の事、患者自身の社会性へのアプローチの重要性についても考える経験となった。
b) 研究室見学・人形作成販売所見学
渡り廊下を通り研究室へ移動した。ちょうど患者の皮膚生検が行われており、見学させていただいた。生検は両耳・顎・腎部背側より皮膚の一部を採取し、染色回数の少ないkiyoun carbol染色にて顕微鏡下でらい菌を観察するものだった。好酸菌の染 色には通常、チール・二一ルセン染色が使われるが、染色回数が2回ということから使われていないらしい。
人形制作場にて
インド、ブラジルやアフリカ諸国ではまだ羅患率が高いが、日本では発症はほとんどなく、らい菌の生検を見ることは、おそらくなかったであろう。ハンセン病は感染経路など、まだはっきりと解明されてはいない部分が多い。この経験はとても貴重なものとなった。
人形作成販売所見学では、職員の方が人形の説明をして下さった。この人形は、患者、家族、職員の方々が作成されている物で、非常に人気があり注文の入っている商品が山積みにされていた。手品の様に変身する人形がとても楽しく、購入にとても迷ってしまった。一同はそれぞれいくつか購入したが、とても魅力的なものばかりで生産性が高く、このことは素晴らしく、患者の社会復帰の大きな力になっているようだった。
(担当:橋本恵子)
3) フィリピン保健省(Department of Health:DOH)訪問
フィリピン保健省(DOH)は日本の厚生労働省に相当する機関である。現在、DOHの下に16のRegional Health Office,76のProvincial Health Office, 1,606のCity Health OfficeまたはMunicipal Health Office, 2,368のRural Health Unit, 11,498のBarangay Health Unitがあり、これらによりフィリピンの地方衛生行政が成り立っている。
まず、City Health OfficerのDr. Florante Baltazarを表敬訪問し、お話を伺った。中でも”Heavens for Angels”が一番印象に残った。”Heavens for Angels”とは日本で言えば、こけしや、水子の霊を弔う場所のようなものであり、そういう子供達のcemeteryとして存在しているとのことであった。中絶などがやむを得ない環境が存在することに、母子保健の難しさを感じさせられた。
Dr. Baltazar 表敬訪問の様子
Dr.Baltazarは、同じく表敬訪問を予定していたマニラ市長のHon. Lito Atienzaにお会いできないことを残念がる我々に、壁掛けの写真にて市長を紹介するなどのユーモアも持ち合わせる方であった。また、まだ慣れていない表敬訪問に、終始顔がこわばっていた我々に対して、リラックスさせようとするDr. Baltazarの優しさも伝わってきた。
続いて、Assistant City Health Officerである女医のDr. Sanchezにお会いした。女性の立場からみた女医の活躍ぶりについてお話し下さった。また、過去に会った日本のドクターが大変有能であったとおっしゃり、将来我々もこのように活躍できるようになって欲しいと期待されているように感じた。
4) Lanuza Health Center (LHC)訪問
現在、マニラ市は6つのdistrictに分けられ、897のBarangayが存在する。私たちが訪れたLanuza Health Center (LHC)は、人口242,000人、Barangay 132カ所を有する第3 districtにある。LHCは、このdistrictにある7つのHealth Centerの中で中核的役目を果たしていると同時に、人口45,000人、Barangay 36カ所を担当している。このうち6つのBarangayは貧窮地区にある。LHCには、Nurse 25人、Nurse Supervisor 2人、Midwife 17人、Dentist 7人、Physician 21人、Barangay Health Worker 6人のスタッフがいるそうである。
ここでは、District Health OfficerであるDr. Paz Manriqueが主にdistrict全体の保健行政について、LHCのDr. Rosine M. De Leonがセンターでの業務内容について詳しく説明してくださった。
LHCは母子保健に特に力を注いでおり、具体的には、BCG, Hepatitis B, DPTなどのワクチン接種、Barangayごとに週1回行っている栄養・授乳に関する講義、CDD (control of diarrhea)、STD対策、子宮頚癌・乳癌の検診、ハンセン病や腸チフス対策、デング熱に関する教育、家族計画などがあげられる。他のセンターと違い、LHCでは患者を待つばかりでなく、自分たちがフィールドに出ることを重視し、6人のBarangay Health Workerが中心となり、様々な理由でセンターに来られない人々に対し、訪問によるアドバイスもしている。このような日々の絶え問ない努力が、Most Active Health Center 1st Prizeを授与された理由であるだろう。
LHCの2階は産院になっており、一般的に20,000ペソかかる出産がここでは無料で行われ、1か月に50〜70人の新生児が誕生している。通常24時間で退院することになっているが、異常がある場合には最長3日間入院することができる。
第3 districtには他のdistrictにはないホスピスケアを扱う施設もある。また、幼児虐待や家庭内暴力対策やDrug Rehabilitation Centerもあり、様々な面で母子保健をサポートしている様子を垣間見ることができた。
Dr. Paz Manriqueの話の中で、マニラ市長には実子が6人、自閉症と完全盲目の養子がいることを聞いた。フィリピンでは日本で見られがちな養子に対する偏見がないことに驚かされたとともに、表敬訪問の予定であった市長に会えなかったことが残念でならなかった。
Dr.Paz Manriqueは穏やかな口調だが説得力のある話し方をする方で、我々学生に対して、優しさと暖かさを感じさせてくださるお母さんのような女性であった。女子学生の中には将来Dr.Paz Manriqueのような女医になりたいと言う人もいた。また、Dr. Paz Manriqueが、バルア先生と同じ時期にレイテ島で学んでいたことがわかり、お互いに驚いていらっしゃった。国際保健に関わる様々な方に出会った今回のフィールドワークを象徴するような、人との出会いの大切さ・不思議さを改めて感じた。
(担当:佐藤弘之)
8月8日 今日の一言 〜ホセ・ロドリゲスハンセン病病院、保健省訪問〜
| 飯田: |
日本に比べ、フィリピンはすごく地方分権が進んでいると感じた。 |
| 五十嵐: |
ホセ・ロドリゲス病院でハンセン病患者さんと一般の人達が人形を作り、売っていることに感動。人形はオススメ! |
| 植木: |
ハンセン病患者がバイオプシーされていたのは痛ましかった。 |
| 岸 : |
日本よりも、一般社会との壁が低かった。保健所のドクターの母なる笑顔と暖かい手。私はああいう人になりたい。 |
| 後 藤: |
ハンセン病の患者さんと一般の患者さんが一緒に病棟内を自由に往き来できている開放的空間が印象的であった。 |
| 佐々木: |
ホセ・ロドリゲス病院にて、Dr. Sanchezのハンセン病に対する熱意が十分に伝わりました。初めて患者さんに接し、医療とは患者さんから教えられるものと思いました。 |
| 佐 藤: |
入居者数が減っていると聞いた。ハンセン病患者について対応すべきだと思ったことは、これから他の疾患にも応用できるような人間になりたい。 |
| 清水: |
ホセ・ロドリゲス病院でもHealth Centerでも、コミュニティーや人々に正しい知識を広めることの大切さを実感できた。 |
| 高 岡: |
太陽になりたい |
| 田 村: |
ハンセン病の患者さんの手を握ったり、患部を触らせてもらった。正直最初は少し緊張したけど、とても大切な経験ができたと思う。 |
| 豊川: |
ホセ・ロドリゲス病院では患者さんと周辺住民が一緒に工房を運営していた。人の逞しさを感じ、心強く思った。 |
| 橋 口: |
ヘルスセンターのドクトールに抱き締められてキスされた時、私もこんなに愛情いっぱいの人になりたいと思った。 |
| 橋 本: |
ハンセン病の患者さんにいろいろ教えられました。 |
| 山 田: |
女医さんの笑顔が優しかった。あんな笑顔を俺も見せたい |
8月9日(木)
本日のスケジュール・内容
1) ManilaからNueva Ecija州へ
2) Nueva Ecija州母子保健センター(無償資金協力援助)見学
3) Zaragoza町にて保健所見学と州保健局による学校での啓発活動見学
4) Tarlac州保健局への表敬
1) ManilaからNueva Ecija州へ
陸路で4時間近くかかった。中部ルソンのNueva Ecija州は、水田や畑の広がる穀倉地帯で、農地改革により自作農が増えたことで農民の収入が増えた州である。マニラよりものどかで、自分にとっては馴染みやすそうであった。
2) Nueva Ecija州母子保健センター見学
本日の初めの活動は、JICA家族計画・母子保健プロジェクト(II)見学である。このプロジェクトは、1992年より、ターラック州にて実施されたプロジェクト方式技術協力から得られた成果をモデルとして、Region 3の全ての州に広めるためのものである。
以下の3つの機軸からなる。
*統合母子保健プログラム(母子保健センター支援、保健ボランティア育成、保健所職員訓練、妊産婦・乳幼児健診推進)
*リプロダクティブヘルス推進(思春期教育、男性のリプロダクティブヘルスヘの参加推進等)
*住民組織活動支援プログラム(NGO連合体育成、村落共同薬局運営支援、Teatro99プログラム、洋裁生計向上プログラム、簡易トイレ製作等)
これらの3つの機軸のうち、母子保健プログラムについての見学を主な目的にして、母子保健センターを訪れた。
母子保健センター(Maternal and Child Health Center:MCHC)では、まず、JICA専門職員の柴田貴子さんから、8月9、10日の2日間についての説明を受けた。この2日間では、州保健局がどのような活動を行っているのかを知り、また1次、2次、3次の医療機関それぞれのレベルによる活動の違いを認識して見学をすることが大切である、等の説明があった。
Nueva Ecija州のMCHCでは、Doctor1名、Nurse1名、Midwife 6名、Educator3名、Secretary 1名の計12名の職員が働いていて、Under Five Clinic Program (UFC Program)等の業務を行なっている。
Under Five Clinic Programとは、5歳以下の乳幼児を対象に、体重測定を中心とした包括的なヘルスケアを行なうプログラムで、このプログラムは、1970年代からバギオ総合病院でDr. クスバノの指導のもと、行なわれているシステムである。1979年には、国家プログラムに指定され、前述の統合母子保健プログラムの目的の一つは、これを推進することである。ここでは、UFC Programの包括的システムの中でも体重測定と予防接種等について取り上げる。
体重測定、予防接種、栄養状態等については、グラフや表が母子健康手帳に一括して記載されている。母子健康手帳は、母親用のピンク、出生児の成長記録用の黄色とUnder Five Clinicでの治療カードのグリーンの3種類のカードで一組となっており(地域によっては、これらの3つが1つになった母子手帳もある)、配布されている。
MCHCでは、この母子手帳により、妊娠・出産時から5歳までをモニターしている。子供の体重測定は、正確に測るために裸にして、天井からぶら下がっているゆりかごで測定し、母親が自分で子どもの体重をグラフにプロットすることにより、そのグラフの意味と子どもの栄養状態についての知識を定着させている。栄養に関しては、母子手帳には、母乳栄養の重要性について記載されている。Vitamin Aは、麻疹ワクチンと一緒に注射されているそうだ。この他に、yellow cardには、下痢症に対する経口補水液 の作り方(ORSパケットを用いた方法と家庭で作る方法)が記載されている。予防接種に関しては、BCG, B型肝炎、百日咳・ジフテリア・破傷風混合、経口ポリオ生ワクチン、麻疹が行なわれている。また、全ての妊婦に対しては、貧血の検査が行なわれており、この検査法は、患者血液を試験管の中でHCI、蒸留水と混合し、サンプルと同じ濃さの色になったときの値をヘモグロビン値(g/dl)とするもので、初めて見る方法だったのでとても興味深かった。
MCHCの職員は、みんな自信を持って生き生きと働いていて、とても活気があるので、JICAが医療従事者を教育し、更に彼らが母親たちを教育すること、そして母親達が保健指導を受け母子手帳を持つことで、母親が主体となり家族の健康を管理することがうまくいっていることを窺い知ることができた。
なお、母子手帳に関しては、フィリピンの他にインドネシアでもJICAによる普及が行なわれており、1948年から日本で実施されてきたこの制度が他の国々でも普及している現場を見ることができたのは、日本の母子保健を再発見する体験であったといえるのではないだろうか。
カチャーシーを披露する私達
3) Zaragoza町にて保健所見学と州保健局による学校での啓発活動見学次に、Zaragoza町に移動し、Rural Health Unit II (RHUII)を見学した。このエリアには、3つのBarangay Health Station (BHS)があり、それぞれのBHSには、一人のMidwifeが働いていることやその役割について、また、これから見学するpuppet showについて等の説明を受けた。この人形劇は、前述の住民組織活動支援プログラムの一つで、人形劇を通じて子供たちに保健の知識を教えて、子供が家に帰ったら家族にこのことを教えることで知識が広がることを目的としている。保健所が隣接している学校の広場に行くと、そこにはすでにたくさんの子供たちが集まっており、人形劇の準備が行われていた。劇が始まる前に、日本からのゲストとして私達が紹介された。出し物として、急きょ、カチャーシーを踊ることになったが、子供達も壇上に上がり、一緒に踊ってくれた。子供達は、とてもノリが良く、僕達を熱烈に歓迎してくれた。そして劇が始まった。まず、導入としてモデレーターの方が壇上から子供達にデング熱に関することを問いかけ、それに子供達が答えるのだが、子供達は物凄く元気に答え、モデレーターの方もそれに負けじと勢いよく問い掛けるという見事なまでのコール&レスポンスだった。(問いかけの内容は、デング熱は、何が媒介するのかやデング熱の際は、非アスピリン系を使うことなどについてであった。)導入で場がかなり盛り上がった所で人形劇が始まった。人形劇は、大音量のダンスミュージックで子供達を引き付け、その間にデング熱に関する劇を少しずつ挿入する形で進んでいった。
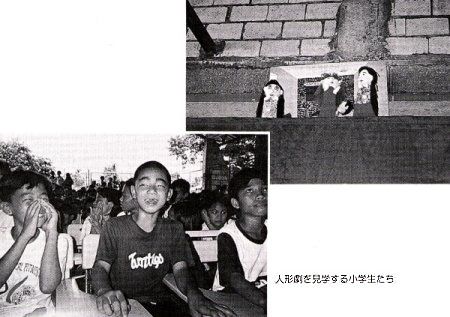
人形劇のあらすじは次のようなものであった。2人の児童が外で遊んでおり、蚊に刺されデング熱に罹り、病気の児童の両親と近所の人達が病気について話す。そこに保健ワーカーが指導にきて病気の説明をして、病院受診をすすめ、児童は救急車で運ばれ病院に行く。途中に、環境の整備(用水路など、水の溜り場を中心に蚊が生息しづらいようにするなど)についての歌が入り、最後に、環境が整備され、住みにくくなった蚊が別の土地に移動していく、というものである。人形劇以外にデング熱に関するパンフレットも配られていた。その内容は、蚊の繁殖しやすい場所と環境の整備や、デング熱の症状についてであった。
人形劇見学は、子供に対しての保健知識普及の方法を学ぶことができ、子供達からたくさんの元気と笑顔をもらえた、とても有意義なものだった。
4) Tarlac州保健局への表敬
本日最後の活動となる中部ルソンのTarlac州保健局への表敬だったが、Zaragoza町から保健局に向かう前に急遽Zaragoza町の町長の計らいで表敬することとなった。
1991年の地方分権化法により、家族計画や母子保健を含む基本的な保健サービスの供給は保健省から地方政府に権限と責任が委譲され、それによりRHUは、市長や町長により運営が指示されている。そのため、市や町における長の考えによって保健サービスの供給に格差が生じてしまうのではと思われるが、このZaragoza町長への表敬は、保健に対して積極的な関心を持つ町長の取り計らいによるもので、地方分権化の成功例を見られた気がする。
Tarlac州保健局長への表敬は、Tarlac Provincial Hospital内にあるJICA事務局で行なわれた。保健局長のDr. Ramosから、学生一人一人に、なぜ医師の道を選んだのかや、WHOの健康の定義についてなどを問いかけられ、私達の答えに先生の考えやアドバイスを付け足していただく講義を受けた。ここでは、Dr. Ramosのお話の中で、印象に残った言葉を2つ挙げたい。
*専門の狭い見方で見ないで社会学的に物を見れるようになることが大切である。
*Never miss the opportunity to talk with people from other countries.
これらの言葉は、国際保健協力において大切であるばかりでなく、人生においてもとても重要な言葉だと思った。また、Dr.Ramosは、インテリジェンスとユーモアにあふれた素晴らしい人で、とても幅の広い見方をしていることが話の端々から窺えた。Dr.Ramosの話を聞いた後、僕が高校のときに習った“Think Globally, Act Locally.”という言葉が、ぽっと頭に浮かび、その言葉の意味を改めて教えて頂いた講義であった。
(担当:清水寛之)
Dr. Ramos 表敬訪問
8月9日 今日の一言 〜小学校にて〜
| 飯 田: |
子供達の積極性、無限の好奇心の大切さを改めて感じました。 |
| 五十嵐: |
子供の笑顔が一番、印象的。なにか大切なものを得た気がする。 |
| 植 木: |
子供達の熱狂振りがすごかった。子供達に元気をもらった。日本の子供達はどうしてあそこまで元気がないのだろう。 |
| 岸 : |
人生最初で最後のアイドル気分!?子供の声、目の輝き、五感で感じたpowerをずっと忘れないでいきたい。 |
| 後 藤: |
ギュッと握りしめてきた小さな手の感覚をいつまでも忘れたくない...。 |
| 佐々木: |
南の島で、熱気に溢れ、両手を高くあげ、最高の歓迎をしてくれた子供達。彼ら、彼女の目の輝きを生涯忘れることはないでしょう。これから医者になろうとするものへの大切なメッセージを子供達は伝えてくれたと思います。ありがとう。 |
| 佐 藤: |
我々外国人に対してなんの抵抗もなく子供達は無邪気に接してくれた。性別、年齢、国籍、民族、人種、障害などに対して偏見を持たないようにするためには、子供の頃から接することが一番いいと思った。 |
| 清 水: |
目が輝いて、めちゃくちゃ元気な子供達から元気を沢山もらった一日でした。 |
| 高 岡: |
energy!!! |
| 田 村: |
貧しくても心までは貧しくならないで明るく元気に過ごしている子供達を見て、幸せのカテゴリーって一体なんだろう?と思った。 |
| 豊 川: |
三線を引いたら生まれて初めてサインと握手を求められた。ウレシカッタ...。 |
| 橋 口: |
子供達の笑顔が大人になっても続くような社会になるといいなあ。 |
| 橋 本: |
子供の笑顔があれば世界平和も夢じゃないかも。 |
| 山 田: |
ンー、サイコー! |