宝永地震は東海地震と南海地震がほぼ同時に発生したものと解釈されているが、それが起きて147年後の1854年(安政元年)に安政東海地震が起きた。このときの賀田湾内の各集落での津波の高さを図15の右上図に示すが、このときも、西側枝湾奥の賀田で津波の高さがもっとも高くなった。
1944年(昭和19年)に起きた東南海地震による津波の集落別浸水高さを同図左下図として示す。やはり、賀田での津波浸水高さがもっとも大きく、ここで5.7mに達した。その2年後の1946年(昭和21年)南海道地震は紀伊水道から四国沖の海域に生じた地震であったため、賀田湾を含む熊野海岸での津波の被害は大きくはなかったが、このときも、賀田湾では賀田集落のある西枝湾でのみ津波による市街地浸水が記録されている。
以上のように、賀田湾は歴史上4回の津波を経験しているが、4回とも西枝湾の奥の賀田集落でもっとも大きな浸水高さを示した。
このような事例から推測すると、どうやら賀田集落は津波の特異点であるようにみえる。賀田が津波特異点になった理由は何であろうか?賀田は内湾の海岸線上にあるので、北海道南西沖地震津波の初松前や茂津多岬、あるいはSissaano潟湖で見たような、津波エネルギーの集中による「焦点効果」ではない。
賀田湾の賀田集落が津波の特異点になったのは、そこが湾内基本固有振動の「腹」の当たる点であったからなのである。
2. 内湾の固有振動の理論
湾内水面の面積が大きい割りに湾口の小さい、閉鎖性の強い湾の場合には、その湾内の海面には固有振動と呼ばれる振動パターンが存在し、外洋から津波などが押し寄せてきた場合には、湾内では固有振動が卓越して、外洋から入射してくる波の特性はわきに引っ込んでしまうのがふつうである。このことは、お寺の釣り鐘は、突き方にはほとんど依らず、同じ音階の同じ音色の音がする、という事実になぞらえることができる。
(1) 1次元の湾
湾が長方形で細長く、かつ水深一定の単純なものであれば、高校生の物理学にもでてくるような、湾口で節、湾奥で腹の定常波は発達し、その第1基本振動は、湾内に1/4波長のみが存在する振動モードになる。その周期T(秒)は、湾の長さをL(m)、水深をD(m)とすると、
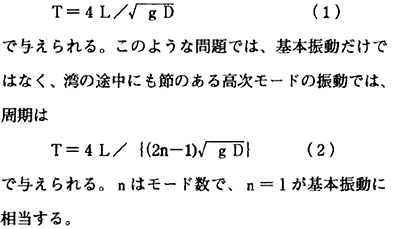
(2) 一般の湾
内湾を1次元の湾と近似できるのはきわめて特殊なケースに限られる。一般には2次元の湾として固有値問題を解かなければならない。湾内の海底地形図を与えて、固有振動を求めるにはLoomis(1975)の方法による。
すなわち、微小振幅の長波近似を仮定すると、内湾の任意の1点(x、y)での海表面の水位ζはつぎのLaplaceの方程式を満たしている。
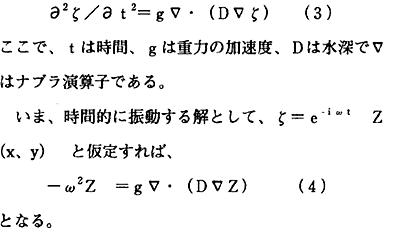
湾の地図全体を格子(メッシュ)で覆い、海面のある格子目を拾いだして、たとえば北西角から東向きに格子目の番号(i)をつける。