畑中:ミステリーですね、現代の。何か信じられないような、でもそういう場合、オーケストラのインスペクターなんかが気をつかっているはずですよね?
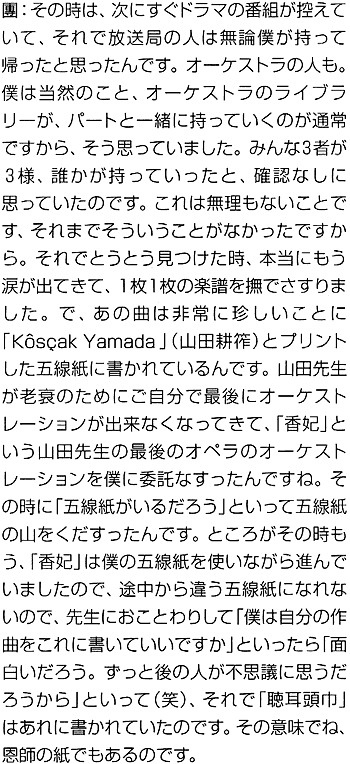
畑中:初演は大阪のサンケイホールでしたね?
團:そうそう、大阪労音の盛んな時代です。
畑中:相当長くやりましたんでね。
團:ひと月位やりましたね。
畑中:最後の「でんでらでん」のコーラスもみんな、聴衆も歌えるようになりましたし。まあそうやって出てきて、東京で再演の時にやっと陽の目を見て。
團:いや、その時、東京の初演は都民劇場がやってくれたんです。
畑中:あ、そうでしたね。
團:それは「初演シリーズ」ですね。それから再演は畑中先生方の手によって…
畑中:ええ、新宿の文化センターだっと思うのですが、この作品は、聴いていて血が騒ぐんですね。日本人でしょうか、やはりこう、聴いているうちに本当に血が騒いでくる。それと團さんがそれを意識なすったか僕は全くわからないんですけれども、手法がヤナーチェクを先取りしちゃったようなオーケストレーションのように聞こえたんですね、この新宿でやった時には。僕の耳がやはりヤナーチェクに開かれたのかもしれないけれど。何かそういうところを先取りしていったような技法が、同じ民話を使っても「夕鶴」とはまた全然違う音楽の世界を團さんが開拓したな、という気持ちがありました。
日下部:後はいかがでしたか?
畑中:その次のオペラは、僕は聴いていないものですからわからないんですけど「楊貴妃」、これは大変なグランドオペラなんです、本当の。
團:大変大きな、大がかりな、登場人員も数百人に及ぶようなものです。藤原歌劇団の創立20周年です。その時に、藤原さんがお出になることは当然として、藤原歌劇団の動かせる人数全部を使おうっていうことでした。僕は前から「楊貴妃」をやりたかったもんですから、まあ悲劇の女性として、それから民衆の蜂起ということもやはりあの中にはありますから。