8/11(金)
地域伝統芸能公演
常磐公園特設舞台
●恵山太鼓<北海道> ●小樽松前神楽<北海道> ●鬼剣舞<岩手県> ●余市町正調ソーラン沖揚げ音頭<北海道> ●琉球民謡・舞踊<沖縄県> ●猩々獅子五段くずし舞<北海道> ●坂津の獅子舞<富山県> ●因幡の傘踊り<鳥取県> ●北海道御神乗太鼓<北海道> ●池田町傘踊り<北海道> ●しゃんしゃん傘踊<鳥取県> ●深川しゃんしゃん傘踊り<北海道> ●秋田竿燈<秋田県>
18:00〜21:10
恵山(えさん)太鼓
北海道恵山町
出演/恵山太鼓保存会

恵山は南北海道の太平洋と津軽海峡の交わる亀田半島に位置する漁業の町。そして荒々しいむき出しの山肌、漂う白煙、恵山は活火山である。この環境のなかで生まれたのが「プロローグ」「恵山大漁太鼓」「恵山山太鼓」と、三つの表現で太鼓を打ち鳴らす「恵山太鼓」である。
小樽松前(おたるまつまえ)神楽
北海道小樽市
出演/小樽松前神楽保存会
国選択無形民俗文化財
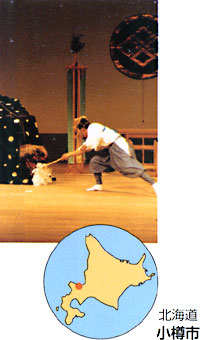
松前神楽は東北地方に多く分布している山伏神楽、番楽(ばんかく)、霜月(しもずき)神楽の影響を受けているといわれ神事、儀礼を重んじる祈り目正しい格調の高い神楽である。十二の手獅子舞は、舞い始から納めまで十二回手振りが変わる時間の長い勇壮な舞で悪魔退散、天下太平、福徳円満を表現した舞である。
鬼剣舞(おにけんばい)
岩手県北上市
出演/鬼柳鬼剣舞保存会

北上市の周辺に伝わる「鬼剣舞」は、憤怒の形相のような面をつけ、手に太刀を持ち激しく踊る芸能。大宝年間(七〇一〜七〇四年)修験(しゅげん)の祖が念仏を広めるために、念仏を唱えながら踊ったのが始まりといわれる。修験道の呪法の一として知られる特殊な足踏み「へんばい」で悪霊を踏み鎮める。
余市町正調(せいちょう)ソーラン沖揚(おきあ)げ音頭
北海道余市町
出演/余市町正調ソーラン沖揚げ音頭保存会
町指定無形民俗文化財

りんごと美しい海岸線を持つ積丹(しゃこたん)半島の拠点、余市町の歴史は鮭(さけ)と鰊(にしん)漁によって開けて来た。アイヌ民族の漁場ユナイコタンに初めて和人が漁場をひらいたのは天明(てんめい)五年、今から約百七十年前のことである。今、江差追分とならび全国で唄われるソーラン節は北海の怒濤(どとう)と戦う漁師の汗からにじみでた仕事唄である。ソーラン太鼓、ソーラン踊りと共に発祥地の意気込みが聞こえてくる。
琉球(りゅうきゅう)民謡・舞踊
沖縄県那覇市
出演/琉球芸能公演団

「民謡の宝庫」と呼ばれる沖縄の人々は、喜び、哀しみ、苦しみといった人生のすべてを民謡と舞踊に託し、古くから伝承してきた。八重山地方でよく唄われている「六調子(六調節)」は、黒潮に乗って日本中に伝えられた「ハイヤ節」をルーツに持つ民謡である。十七世紀頃に三線(サンシン)と呼ばれる楽器が普及し、琉球古典音楽が発展するとともに、庶民の民謡にも三線の伴奏が使われるようになり、人々の暮らしの中に溶け込むようになった。三線の特徴は、日本の民謡や中国音階とは違う、独特の琉球音階の調べである。
猩々獅子五段(しょうじょうししごだん)くずし舞(まい)
北海道深川市
出演/狸々獅子五段くずし舞保存会
市指定無形民俗文化財
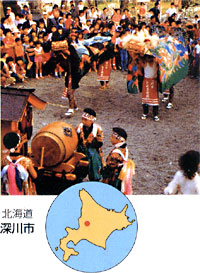
明治時代に、深川市一己(いっこ)地区に入植した屯田兵が出身地香川県の獅子舞を正確に伝承している。例年九月大国神社の例大祭で奉納され、獅子の誕生から没(ぼっ)するまでの一生を舞、演じる。
前ページ 目次へ 次ページ