承句からは一転して幻想となり(深く礼拝した形でたすきをかける)今川義元の霊がかつての姿で立ち上がり、直ちに抜刀して勝ちいく戦(いく)さの驕った様子を攻めの刀法で演じる。
転句からは再び急転、先ず暴風雨の激しさを二枚扇を使って強調し、途中から織田軍の奇襲を受けた今川軍の負け戦を見せ、悲惨な受け身の振りで修羅の苦しみを表現する。
結句は前句からの引き続きで、倒れても更に舞台を転がりながら攻撃の姿勢を見せ、結句の後半では空からの敵を迎え撃つポーズで終り後奏では形を整えて退場する。「夢幻能」の様式ではないので、最後に再び登場の役柄に戻る必要はない
◎衣装・持ち道具
男女ともに地味な、黒・茶・紺の紋付に袴を着用し、たすきは承句以降で使いたい。扇は全体に共通して使えるものとして茶系の無地か目立たない柄を選ぶ。
詩舞
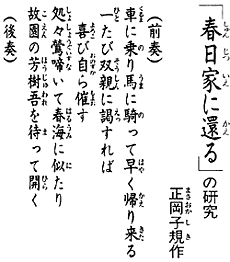
◎詩文解釈
作者の正岡子規(一八六七〜一九〇二)は明治期の俳人として良く知られているが、七・八歳頃から大原観山、土屋久明に漢学を習い、十一歳で漢詩を作るようになった。この詩は松山中学在学中の子規十二歳の作である。詩の内容は『久し振りに故郷に帰る私は、車や馬を乗り継いで急いだ。我が家に着き両親の顔を見ると、ひとりでに喜びが湧いてきた。家の回りの到る所では鶯がなき、春の草花が一面に海のように広く咲き乱れていて、また我が家の樹々も、自分の帰宅を待っていたように花開いた』というもの。
◎構成・振付のポイント
ふるさとと、両親に対する慕情が春の情景に溶けあって、多感な少年の心を見ごとに描いている。ところでこの作品は作者が松山中学の寄宿舎生活から久し振りに我が家に帰って来たことを詠んだと考えてもよいが、子規は五歳の折に父を亡くしているので、子規自身のこととせず少年の一般的心情を詠んだものとしたい。また詩舞として表現する場合も、演者が小学生高学年以上(少年)と以下(幼年)では、そのニュアンスも大分違ってくるので、特に承句の喜びの表現などは、演者にふさわしい振付を考えて欲しい。
次に一例として、まず前奏から起句にかけては、わくわくしながら帰省する様子を、例えば扇を使って荷物に見立て、車に乗り込んだら、扇を車輪に見立てて使い分ける。幼年の場合は馬に乗る振りは避けて馬車と解釈した方がよい。承句も前述の如く演者にふさわしい表現で、遠くから眺めた我が家、両親への挨拶、土産ばなしなどの手順を決める。転句は詩文は三人称だが、例えば鶯の声を聞く振りは一人称、また花が咲き乱れた様子は二枚扇の振付もよい。結句は前句の流れを受けて、再び一人称で我が家の満開の樹々を讃え、枝を折って(扇の見立)後奏でそれをかざして(女児なら花占いでもよい)退場する。
◎衣装・持ち道具
学生のイメージで男女とも薄い色目の衣装で春の雰囲気を出す。扇も同様だが、見立て振りを十分に配慮し、二枚扇の活用も計算に入れて置く。