'01剣詩舞の研究 幼少年の部
石川健次郎
剣舞「桶狭間を過ぐ」
詩舞「春日家に還る」
平成十三年度「剣詩舞コンクール」の指定吟題が発表され、今月からはそれらの表現研究について述べることにする。新年度は西暦二〇〇一年、つまりは新しい二十一世紀の始まりの年に当るわけだから、剣詩舞にも新しい息吹(いぶき)が感じられるような作品の研究を目指して行きたいと思う。
剣舞
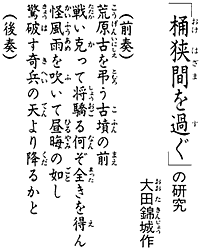
◎詩文解釈
この詩は江戸時代の儒者、大田錦城(一七六五〜一八二五)が、桶狭間の古戦場(現在の愛知県中央部で、豊明(とよあけ)市内の国道一号線沿いにある)で、今川義元が戦死したと伝えられる小高い丘を訪れ、その感慨を述べたものである。
桶狭間の合戦とは、永禄三年(一五六〇)五月に、天下統一を夢みた東海の武将・今川義元が、京都に三万の大軍を進めようとしたとき、織田信長が桶狭間で奇襲攻撃をかけて今川軍を壊滅した戦国時代の代表的合戦である。
この合戦の様子をもう少し詳しく述べると、五月十七日に駿河より尾張領に大軍を進めた今川義元は、十九日には織田方の丸根城と鷲津城を落し、尾張侵攻作戦は成功したかに見えた。この勝利に酔った今川軍は桶狭間の東北で、通称田楽(でんがく)狭間と呼ばれる谷間に休息していた。一方織田信長は、今川軍の本陣が桶狭間にあると察知して、折からの暴風雨をついて攻め込んだ。織田勢はわずか三千余りだったが、勝利に酔って警備を怠っていた今川軍は不意をつかれて大混乱に落ち入り、今川義元は織田軍の毛利新助と服部小平太によってあっけなく討たれてしまった。
ところでこの漢詩は、以上述べた合戦の故事と、承句に述べられている『史記』の「戦い勝ちて将驕(おご)り卒惰(おこた)る者は敗る」を引用して構成されているが、詩文を直訳すれば次のようになる。
『荒れ果てた古戦場の丘で昔を忍ぶと、今川軍は勝利に酔い、武将たちは驕(おご)りにふけっていたということだが、そんなことでは本当に勝利を得ることはできまい。あの合戦では、思わぬ天候異変で陣営は闇につつまれ、それに乗じた織田軍の奇襲が天から降って来たのかと驚くうちに今川軍は敗北したのである』
◎構成・振付のポイント
この作品は今迄も「一般の部」の指定吟題として取上げられたが、幼少年の部では今度が初めてである。特に子供向きの内容と云うわけではないだけに、指導者は舞踊構成の上で演技者を十分納得させることが大切である。この詩文構成では作者の大田錦城が、遠路はるばると桶狭間の古戦場跡を訪れて、その昔(当時から約二五〇年前)この地の合戦で戦死した将兵の霊を弔うことに始まるわけだが、この人物(作者)に幼少年が扮するよりも、最初から演者の年頃にふさわしい役作りで、荒れはてた古戦場跡を訪れさせた方がはるかに自然さが表現出来ると思う。
まず前奏から起句にかけては、古戦場に向う道中振りを、扇で笠や杖に見立てて、また近くの山景や、雲の流れ、飛ぶ鳥の行方などを演じながら、古墳(塚)の前に刀を置いて、たすきの紐(ひも)を数珠(じゅず)に見立てて礼拝する。