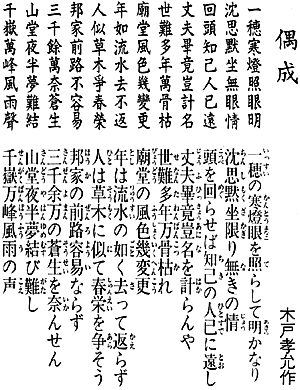勤王芸者幾松が桂小五郎をかくまって見事な態度で新選組の人々を迎えている姿
或る時桂小五郎が三本木の幾松の所へ来て睦まじく話をしている時、新選組の三浦左近の一派が幾松の家を襲って来た。幾松は咄嵯に桂小五郎を押入れの中へかくしてから表戸を開けた。ドヤドヤと新選組の隊士達が入って来て長州の桂がかくれているであろう小五郎を出せと抜身を突きつけてつめ寄る。幾松は顔色一つ変えずして知らぬ存ぜぬの一点張りで言い交わすが、どうしても家探しをすると上がりこんで来たので、幾松はこの画の如くキリッとなって『芸者とあなどって土足で座敷へ踏み込むとは言語道断、御見受けすれば新選組の錚々(そうそう)たる方々と思います。若し小五郎様が居れば妾の一命差し上げますが、万一居ない場合こま何となされますか。妾の前で腹かき切って頂きましょう。さあ如何になされますか、しかと御返事承ってから何処なりと家探ししていただきましょう』と滔々臆せず捲(まく)し立てた。新選組の者供も腹をと言われて驚き其の其のまま引き上げてしまったという笑い話が伝えられている。やがて木戸孝允が明治の大政治家になられた時、芸者幾松は木戸孝允夫人として内助の功を全うした賢夫人になっている。
孝允が木戸という姓になったのは慶應元年で、昔桂の先祖が各所の木戸を守って勇名を轟ろかしたと言うことで藩主敬親公の命で木戸準一郎と改称してからである。勿論、長州であるので高杉晋作、大村益次郎などと親しく交わり、土佐の坂本龍馬、中岡慎太郎などと結んで薩長連合にも力を尽している。江戸では斉藤弥九郎の門に入って剣の道を学び、奥義を極めて師範代をもつとめており、又江川太郎左衛門の門に入って蘭学を研究し世界の大勢に通じ、海防の必要性を痛感し、たまたま江川太郎左衛門が品川へ砲台を築いたので木戸孝允も実際にその砲台を見学し度く思い、木戸は一策を案じ自ら人夫に変装して毎日人夫と一緒に工事の手伝いをして幸いに砲台の概況を知ることが出来た。
明治になってからは大政官出仕、総裁局顧問官となり、明治三年に参議、明治四年には岩倉具視に従って欧米を視察し、七年には文部卿となり、十年西南の役には自から戦地へ行こうとしたが、陛下が『卿一日も朕が側を離るるべからす』と仰せられたので感泣して西南の役は遠くから見るだけであった。而しその間に病を得て明治十年五月二十六日急に逝去してしまった。年は四十五歳であった。
西郷隆盛、大久保利通と共に明治の三傑と呼ばれた一人である。
孝允の詩で一番有名なのは偶成(一穂の寒燈)と言う俳律である。