しかし、市街地に該当しない地域における消防需要に対応するため、署所、救急分遣所等が設置されている実態に鑑み、「新基準」では基準の中に明確に位置づけました。
また、弾力対象についても署所、消防艇等を新たに加え、市町村の裁量を大きくしました。
別図1 改正前の基準(答申では「現状」と表記)
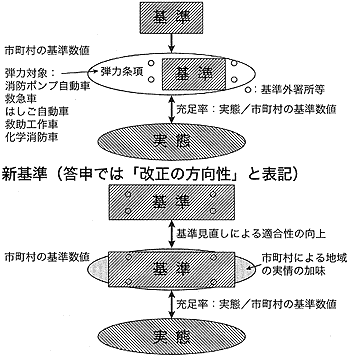
四 改正の概要
改正の概要について以下に述べるとともに、主な消防施設の配置基準、管理区分等について別表1に、改正前の基準と新基準の比較について別表2に整理します。
(1) 改正前の基準は、市町村が火災の予防、警戒及び鎮圧並びに救急業務等を行うために必要な最小限度の施設、人員を定めることを目的としていましたが、今回の改正により、需要の増加している人命の救助を明文化するとともに、基準の持つ本来の性格から最小限度という表現を改め、市町村が適正な規模の消防力を整備するにあたっての指針となるものとして位置づけています。(第一条)
(2) 「市街地」の定義において、平均建ぺい率おおむね一〇%以上の区域は街区の連続性がなくても、近接している場合は市街地に含めるとともに、「密集地」を「準市街地」という用語に改め、人口規模の下限値を千以上に改めています。(第二条第一号及び第二号)(別図2)
別図2 市街地、準市街地の概念図
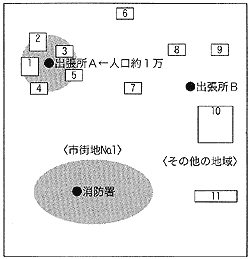
(注) 出張所A、出張所Bについて、改正前の基準では基準外とされていたが、今回の改正では基準に位置づけられた。□:準市街地
(3) 署所の設置数は、人口規模によって規定される数値を基準とし、これをもとに地域における、地勢、道路事情、建築物の構造等の諸事情を勘案した数とするとしています。条文中の例示の他に「諸事情」としては、交通事情、市街地等の形状、市街地等の面積、集落の分布状況等の地域ごとに固有な所与の条件が該当します。今回の改正によって署所の他に、動力消防ポンプ、消防艇についても、市町村が必要な数を決定するにあたっては、国の示す基準をもとに、諸事情を勘案した数とするという規定にしています。
なお、改正前の基準は、風速条件によって消防力の加重を行っていましたが、これを諸事情に含めて考慮するとしています。(第三条第一項別表第一、第二項別表第二、第三項別表第三、第四項別表第四、第四条第四項別表第五、第一三条)(別図3)
別図3 市街地における署所数の算定式
A:市街地面積(km2)
P:市街地人口(万人)
p:DID人口密度(人/km2)
V:消防ポンプ自動車走行速度(km/分)
a:署所担当面積(km2)
R1:市街地をカバーするのに必要な署所数(署・所)
A=104P/p
V=−(2×10-5) p+0.64
a=40.5V2×0.5=40.5{−(2×10-5) p+0.64}2×0.5
R1=A/a=104P/40.5{−(2×10-5) p+0.64}2×0.5×p
(注) 第3条別表第1は、これらの式によっている。
(4) 消防ポンプ自動車の配置台数は、消防活動の実態調査から導かれた消防活動モデルをもとに配置数を規定した別表に改め、改正前の配置数より減じています。(第三条第三項別表第三及び第四項別表第四)
前ページ 目次へ 次ページ