図2.1.11は、陸奥湾のCOD(化学的酸素要求量)で、有機物の指標となります。CODが高いと有機物が多いという感があります。
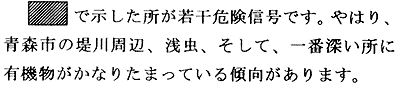
この有機物が夏場、酸素をたくさん消費し、また、この辺はたまり水になるので、無酸素状態になります。陸奥湾では夏場、無酸素状態になると、カレイが死んで刺し網にかかる話をよく聞きます。
陸奥湾における硫化物(硫化水素が発生しやすいかどうか)は、やはり青森市とむつ市、都市部の沖に結構あります。しかし、ホタテが養殖されている海域ではそれほど陸奥湾は汚れていないということです。
西田先生もおっしゃったように、トータルとして水質的には陸奥湾はかなりきれいです。
瀬戸内海は富栄養化していると言われていますが、陸奥湾では逆に貧栄養、栄養がないと言われています。プランクトン量や生産量で、全般的に他の南の海よりも栄養が少ないと言われています。
その中でホタテ養殖は、限られたプランクトン生産量をいかに効率的に使って養殖していくか、それがこれから問題になっていくかと思います。
我々増殖センターの自動観測ブイ(通称:ブイロボット)は毎時間、水温、塩分、流向・流速など、貴重なデータを送ってきます。このブイロボットは、平舘、西湾の奥の青森の久栗坂沖、川内沖の東湾の真ん中、この3か所に設置され、無線でセンターにデータを送ってきます。データを見ると、水温と塩分は、ホタテ貝の生産、ひいてはプランクトンの生産にかなり関わってきています。
平舘の水温は、津軽暖流系の影響で、冬場でも8℃くらいまでしか下がらず、夏場も上下の差がなく、23〜24℃まで上がります。
東側の川内沖は、気象の影響をかなり受けるので、冬場の水温は4℃以下になり、たまり水ですので、夏場は日照の影響を受けて表層だけがかなり上がり、底の方はそれほど上がりません。
青森はその中間を示します。
塩辛いか、甘いか、微妙な差がありますが、大体海水は3.3〜3.4%くらい、漬物にちょうどいい塩分量で、暖流系は一般に塩分が高いです。
津軽暖流系が強い平舘では3.4%、かなり塩分が高くなっています。しかし、表面は雨などの影響で、春から夏にかけては低くなります。
一方、東湾の方は全般的に3.4%より低い傾向があり、上下の差はそれほどありません。
青森は河川の影響、雪解けの影響がかなりあり、底層はそれほどでもないのですが、表層はグッと下がります。夏場は3.2〜3.3%まで下がります。
図2.1.12は、陸奥湾の密度の変化を示してます。
先程「水温と塩分がプランクトンの生産にかなり関わってくる」と言いましたが、密度は水温と塩分から計算できます。お風呂の場合、温かい水は上に来て、冷たい水は下に行きます。それに塩分が入ると、塩分が高いと重いので下に行き、塩分が低いと上に行きます。このように塩分と水温の状況で密度が違ってきます。
全般的に陸奥湾は、冬場は密度が上がって、夏場は下がっていくという傾向があります。
冬は密度が上がって、上下の差がほとんどなくなります。これがプランクトンの生産に最も重要になってきます。気象によって上の水が冷やされてどんどん重くなって下に行くのですが、今度は下の水が上に来ます。それが上がってくるときに一緒に栄養塩の窒素、リンを持ってきます。
栄養塩が上に来て、春先の日照時間が増えて温度が上がると、植物プランクトンがどんどん増え、「春のブルーミング」が起こります。下からの栄養の供給があって初めて植物プランクトンが、ホタテがいかに成長できるかが決まってきます。
夏は全般的に上下の差が大きくなります。上と下の水が混ざらないので、下から栄養が全く来ません。そのため、植物プランクトンは増えません。
このように、植物プランクトンの生産は、陸奥湾の塩分、水温、海洋構造にかなり影響されます。