次に循環状態ですが、これは脈拍があるかないかをみるものですが、この前の段階で呼吸が止まっており、簡単に脈拍が取れない弱い時は、この確認に時間を割かずに脈拍がないと思ってすぐに心臓マッサージを行なって下さい。弱い脈拍を正確につかむのは、医療関係者でもとても難しいものですから、脈拍の確認に手間取る必要はありません。
その実際の方法手順ですが、最初に気道内に異物等が詰まっていて呼吸が止まっていないか見る必要があります。気道内に異物がある場合の取り方ですけれど、指を突っ込んで取る方法、背中を叩く方法、ハイムリック法と言う、お腹を圧迫して吐き出させる、胸の空気を押し出させて吐き出させる方法が、一般的な方法です(図5)。
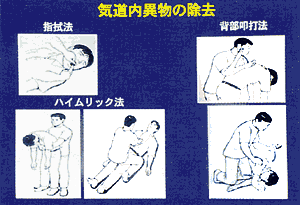
図5
異物がある場合はこれをまず除去し空気が肺に通るようにする必要があります。異物が無かったり、除去したにも関わらず呼吸をしていない状態であれば、下顎を引っ張り挙げる気道確保というのが必要となります(図6)。
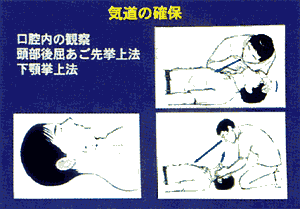
図6
通常物を飲み込んだときは食道の方に入り、気管の方に物が行かないように蓋をする喉頭蓋というのがあります。この喉頭蓋が垂れ下がると空気が通り難くなります。また舌の根部も垂れ下がってしまうと空気の通りが悪くなります。そこで少し後頚気味にし、軽く下顎を引っ張り上げる下顎挙上を行います。これにより喉頭蓋や舌の根部が垂れ下がるのを防ぎ、口から肺までの空気の通り道を確保します。
次に、心臓マッサージですが、胸の正中に胸骨があります、その下のほう、やや左胸の方に手をあてまして、その上からもう一方の手を当て体重を乗せるようにして押していきます(図7)。
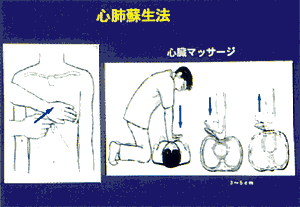
図7
垂直に押していただき胸骨が3〜5cm沈むように押せればいいと思います。1分間に100回のペースで行うとつぎの人工呼吸をその間に行いますので実際には1分間に60〜80回心臓マッサージを行っているという状態が必要になります。
人工呼吸ですが、口対口の人工呼吸というのは、空気を送るという意味では、いちばんよろしいのですが、身内でない人に対し口と口が直接触れる人工呼吸をいざ実際に行えるかというと、躊躇われる問題があります。しかし口と口の人工呼吸が行い難い場合でも、心臓マッサージだけは行って下さい。気道さえ確保できていれば、3〜5cm胸骨を沈める心臓マッサージにより、胸の動きに伴い肺に空気が入っていきますので、それだけでも救命効果はあがるといわれています。
個体死とは脳の不可逆的な機能停止と定義されており、脳は身体の中で酸素欠乏に一番弱い臓器であり、生命維持に欠かせない臓器であります(図8)。
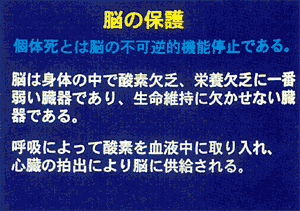
図8
心肺蘇生というのは、酸素欠乏という脳にとって一番弱い状態を助ける、脳機能の損失を最小限にくい止めるという意味合いで、一番大事な処置、ケアと言えます。
次に脳の損傷に関してお話します、一次的損傷と二次的損傷にわけられています(図9)。
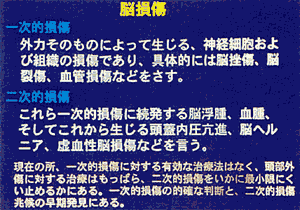
図9
前ページ 目次へ 次ページ