講演
第32回九州船員災害防止北九州大会より
怪我と病気の応急処置
(社)日本海員掖済会 門司病院
医師 安部利彦

掖済会門司病院、外科の安部と申します。本日はこの場においてお話を出来る機会をいただきまして光栄に存じます。
さっそくですが、本題に移らせていただきます。
一般市民の行う救急蘇生法には、心肺蘇生法と止血法が含まれ、救命手当と言われております(図1)。
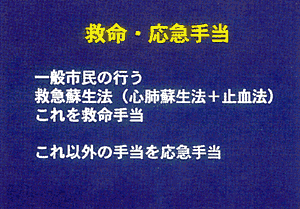
図1
これら以外の手当は応急手当となります。まず、生命に関わる一次救急手当として一般の方が行える救命手当、心肺蘇生法を知っていただき、また実際にこれを行っていただきたいと思っています。
救急蘇生法には、心肺蘇生法と止血法が含まれています(図2)。
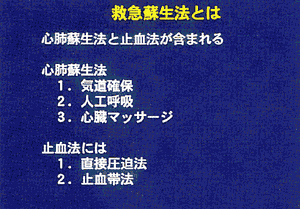
図2
心肺蘇生法には気道確保、人工呼吸、心臓マッサージがあり、止血法には、直接圧迫法、止血帯法があります。
心肺蘇生法というのは、脳の機能の損失を抑えるお手伝いをすることです(図3)。
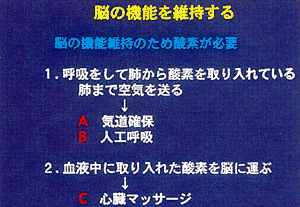
図3
心臓、呼吸が止まると脳に血液、酸素が運ばれなくなり脳の機能が損なわれます。脳の機能を維持するためには、酸素が必要です。酸素はどういうふうに脳に運ばれていくかと申しますと、呼吸をして肺から血液中に酸素を取り入れて、取り入れたものを心臓が拍動によって脳に運びます。この流れを止めないようにするというのが、心肺蘇生法の一番の目的だと考えています。という理由で、これらの流れを保つように気道確保、人工呼吸、心臓マッサージを行ないます。
心肺蘇生を行う前に、患者さんの状態をよく把握するということが大切であります(図4)。
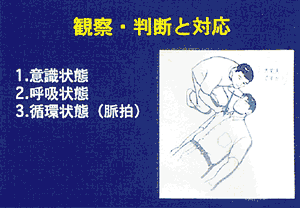
図4
その把握とはまず意識状態、呼んで返事があるか、刺激に対して反応するかということを見ていただく、その後、呼吸状態、脈拍をみるという順番になります。
呼吸状態ですが、息をしているかどうか胸の動きを見る、または鼻や口に耳を近づけることによって、息が流れ込むのを聞くという方法があります。
前ページ 目次へ 次ページ