この他に、改革についての特定の理念は、その認知された合法性と「所有権」(これについては、本章の、閣僚と官僚との関係の節ですでに指摘した)に影響を与えるかもしれない。下級公務員は、ある特定の政党、もしくは今をときめくシンクタンクの「天才少年」が発信源と思われる新機軸の理念には、より強く疑いの目を向けるだろう。ヒエラルヒーの下層における改革の「所有権」の達成も、「自家製」の要素が相当量あると思われれば、つまり、新機軸の理念もゼロックスやモトローラからの強制的な「輸入物」のように見えるものより、むしろ公務そのものに蓄積された経験にもとづいているように見えれば、困難の度合いはより少ない。むろん、これらの反動は、それ自体、行政文化によって影響を受ける。大企業発の理念は、フランスにしばらく存在した強力で誇り高い国家文化よりも、プロの商売における表面的な合法性、合衆国で優勢な反政府文化に一致する。
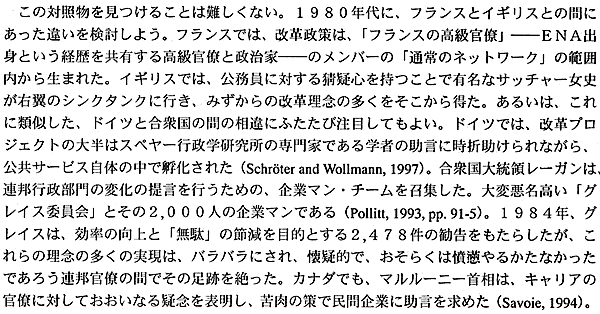
フィンランド、オランダ、およびスウェーデンは、またしても国によってそれぞれである。フィンランドの1987年からの10年間のパブリック・マネジメントの改革は、上級公務員の考えに帰せられる。実業界の人々やコンサルタントといった外部からの参加は、原則と言うより例外だった(1人か2人の公務員はもともと実業界での経験があったにせよ)。これとは対照的に、オランダの改革は、立て続けに開催された委員会や調査会の中から生まれたが、そうした委員会や調査会は公務員だけでなく、学者や会計検査官、実業界からの参加者を特徴とし、かなり開かれた助言や理念の市場が形成された。スウェーデンはさしづめフィンランドとオランダの中間といったところだ―「外部」との討論や「外部」からの参加はあったが、上級公務員は指導的地位をしっかり確保していたため、政府への助言役をつとめる実業界の人々や外部のシンクタンク、マネジメント・コンサルタントによって実質的に策定された改革計画をやむをえず実現したとき、イギリスや合衆国、カナダといった国々の公務員のような立場にはまったくなかった。