V パネルディスカッション
はじめに
司会
後 房雄(名古屋大学法学部教授)
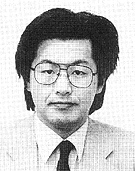
ただいまご紹介いだだきました、名古屋大学の後(うしろ)と申します。
これから第2部のパネルディスカッションを進めさせていただきます。
私、一応政治学、行政学を勉強しているのですが、この行政苦情救済制度については、恐らくこの会場の中では最も素人ではないかと思っております。勉強の良い機会ではあると思うのですが、同時にむしろこの会場には、経験を積まれてきた方々が非常に多いということですので、また、このシンポジウムも外部からの刺激があった方がいいのではという趣旨もあるようですので、素人の代表として、司会を務めさせていただきたいと思っております。御協力をよろしくお願い致します。
これから6名の方からご発言をいただきながら、パネルディスカッションを進めて行きたいと思います。その導入に当たりまして、これまで皆さんにお聞きいただいたオースティン先生のお話しを手掛かりに、少し私なりにイントロダクションということをさせていただきたいと思っております。素人にとっては、非常に分かりやすいオンブズマン制度の説明があったわけですけれども、特に研究者として関心をそそられたのは、オンブズマンの機能している国を四つの類型に分類されたということです。
つまり、1]経済が発展した確立された民主主義国、2]経済が発展した新興民主主義国、3]経済が発展途上にある新興民主主義国、4]経済が発展途上にある伝統的民主主義国の四つの類型を出されたわけです。
恐らく、日本の行政苦情救済制度を考える場合、どういう類型の国の中でその制度が機能しているのかということを考えることが、現在の問題点や今後の方向を考える上で非常に重要であろうと思います。その意味で、オースティン先生が出された四つのカテゴリーを、一つの枠組みとして日本を見た時、どういう問題点が浮かび上がるかという問題提起として、このパネルディスカッションにとっても非常に有益な枠組みを提出していただいたと思うわけです。
日本の行政相談制度は、一つ目の類型の国、つまり、経済が発展した確立された民主主義国におけるオンブズマン制度と最もよく似ているのではないかという、オースティン先生の日本についてのコメントがございました。日本の状況を考えますとき、これだけの経済の先進国になり、長い民主主義国家としての伝統を持っているわけですから、第1の類型に入るという、先生の説には基本的には異論のないところだと思います。