第16回TAFISAコングレス開催
新千年紀(ニュー・ミレニアム)のスポーツ・フォア・オール

世界のスポーツ・フォア・オール(以下SFA)推進機関を統括する国際組織であるTAFISA(国際トリム・フィットネス生涯スポーツ協議会)の第16回コングレスが11月21日から5日間、キプロス共和国のリマソルで開催された。
コングレスには世界40ヵ国から総勢133名が参加した(日本からの参加は6名)。初日にはTAFlSAと協力関係にあるIOC、WHO、UNESCO、GAISF(国際スポーツ団体総連合)などの代表者が招かれ、「ニュー・ミレニアムにおけるスポーツ・フォア・オールの可能性」というテーマでパネルディスカッションが行われた。
討議の中で、「SFAの新しい文化を作るためには、ネットワークと協力体制が不可欠であること」「トップスポーツとSFAを連携させるために、IOCは両者にバランス良く資金を配分すること」「行政の健康政策担当者をターゲットとしたSFA推進キャンペーンを実施すること」などが必要であるとの見解が示された。
このほかに、SFA政策の現状と成果に関する各国からの報告があった。なかでも、日本とシンガポールからはスポーツ参加に関するデータやスポーツクラブに関する事例が報告され、参加者の関心を集めた。
コングレスの期間中、アジア・オセアニア地域のSFA推進組織であるASFAA(アシアニア・スポーツ・フォア・オール協会)の総会が開かれ、任期満了に伴う役員の改選が行われた。新しい会長には韓国のシャンヒー・リー氏(スポーツ・フォア・オール・プサン協会会長)が就任、ASFAA会長を2期8年にわたって務め、組織の発展に貢献した坪内嘉雄会長(SSF顧問)は名誉会員に、笹川スポーツ財団の小野清子会長は顧問に推薦され、総会で承認された。
次回のTAFISAコングレスは2001年10月27日〜11月2日、南アフリカのステレンボシュで開催される。

「スポーツ実施調査」のグローバル・スタンダードに向けて
欧州のCOMPASSプロジェクト
ヨーロッパ評議会(CE)のスポーツ政策の一環として、イタリア・オリンピック委員会(CONI)とイギリス・スポーツカウンシル(UKSC)の主導のもと、スポーツ実施調査の国際標準化を図る「ヨーロッパにおけるスポーツ参加に関する比較調査(COMPASS:Co-Ordinated Monitoring Participation in Sports in Europe)」プロジェクトが推進されている。各国で行われてきたスポーツ実施に関する調査は、データの収集や分析の方法などが国ごとに異なるため、横並びの比較を行うことが困難であった。このブロジェクトには、調査手法を標準化することで、スポーツ実施状況に関する国際比較を可能にする狙いがある。
COMPASSでは試みとして、量的レベル、質的レベル、組織レベルの3項日からスポーツ参加を評価するモデル(COMPASSモデル)を作成、イタリア、イギリス、フィンランド、アイルランド、オランダ、スペイン、スウェーデンの7カ国の最新の調査を2次分析し、このモデルに当てはめて国際比較を行っている。
SSFでは、「スポーツライフ・データ1998」の中で、カナダ、オーストラリアなどのスポーツ先進国と我が国のスポーツ人口、実施種目について比較しているが、比較できる国も調査項目も限られているのが現状である。COMPASSの今後の動きを注意深く見守りたい。
M君のスポーツ突撃レポート
第4回─スパイダーマンにはほど遠い
屈辱の記録は8メートル
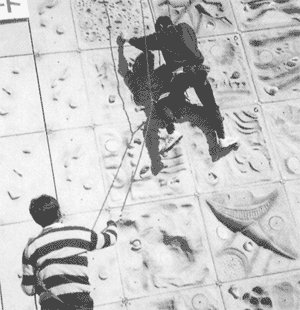
今回はフリークライミングに挑戦するため、神奈川県秦野市にある県立山岳スポーツセンターにやって来た。高さ15mのクリーム色の壁には、赤、青、黄、緑など原色の出っ張り(ホールド)が所々にくっついている。壁をスイスイとよじ登っていくベテランを見ると、いかにも簡単そう。
ビギナーなので、安全ロープを腰に縛り付けて登るトップロープ方式で登ることにした。ハーネスに繋がれた太さ11ミリのロープが命綱。上から吊ってもらいながら、下でロープを確保する人(ビレーヤー)とのチームプレーで、てっぺんの赤いホールドを目指す。
ハーネスを付けて、登り始める。高さ4mくらいまでは実に順調だったが、それからスピードがガクッと落ちた。フリークライミングは手足4本のうち、三点確保が基本。しかし壁面をはい登るほど足元が見にくくなる。
「右のホールド掴む!もっと右だ!」
「左足の上のホールドを使え!」
下からのアドバイスに素直に従おうにも体がついていかない。ホールドの出っ張りが小さすぎて手足が上手く引っかからないのだ。
とにかく腕が疲れる。「高さ」なんて、手と足に気を取られて、ほとんど気にはならない。というか、怖がってる余裕などないのだ。さっきから両手はずっと断続的な懸垂状態なので、ホールドを掴む手がぷるぷる震えはじめた。もう限界だ〜あ。
「テ、テンションかけてくださ〜い!」
下のビレーヤーにロープを張ってもらって小休止。
しかし、少し休んだくらいでは筋肉の笑いは止まらなかった。
「あの〜、下ろしてくださ〜い!」
「えっ!もうギブなの?だらしねーなぁ」
結果は8m弱。ビレーヤーの嘲笑を浴びながら、衆目の中、降ろされた。トホホホ。
フリークライミング。ちょっと見には簡単そうだが、これは腕力のいるスポーツだぞ。
クローズアップナウ
*このコーナーではスポーツ・フォア・オールの精神がキラリと光る自治体を紹介しています。
町のキャッチフレーズは「ボート王国」
岐阜県川辺町
川辺町教育委員会 井戸績
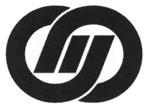
川辺町は岐阜県のほぼ中央に位置し、面積41.18km2、人口約1万1千人、町の中心部を北から南へと飛騨川が流れ、総面積の3分の2を山地が占める自然豊かな町です。
当町はその昔、飛騨への玄関口として、また、飛騨木材の集積場所(網場宿)として栄えました。川は交通の手段であると同時に仕事場であり、川と共に発展してきた町といえるでしょう。昭和に入って川辺ダムが建設され、このダム湖の有効利用の一つとして、昭和45年に岐阜県が艇庫を設置し、「岐阜県川辺漕艇場」が誕生しました。
全長4500mの練習水域の中に、社団法人日本ボート協会公認B級コースの認定を受けた、幅6レーン、直線距離1000mのボートコースを有し、川の流れや波風もほとんどなく、1年を通じて水量も安定している絶好の水面環境から、近年では日本代表クルーの強化合宿の場としても活用されるなど、全国でも有数のボートコースとなっています。
当町ではこの川辺ダム湖を町のシンボルと位置づけ、「ボート王国かわべ」をキャッチフレーズに町の活性化を図っています。平成元年から川辺ダム湖周辺整備事業を推進し、平成5年に湖岸線道路・遊歩道や広場を備えた右岸側の整備を終え、早朝から夕方にかけては美しいダム湖を眺めながらジョギングやウォーキング、あるいは魚釣りを楽しむ町民の姿を多数見ることができます。また、平成元年度から開催している「川辺町ボート大会」には、毎年80を超えるクルーチームが参加し、日頃の練習を含め湖面を賑わせてくれます。漕艇場に隣接する川辺中学校にもボート部があり、全国大会では常に上位を狙うなど、実力を発揮しています。同校の卒業生の中には日本を代表するクルーの一員として現在活躍している選手も少なくありません。また、平成10年からは一学年のすべての生徒が授業の一環としてボートを体験する実習も実施されており、町のボート愛好者の方々の指導のもと、ボートに関する技術のほか、川での事故防止、川辺ダム湖を取り巻く自然環境問題等、多くのことを実習で学ぶことができるようになっています。
ボートは、一人ひとりの力が、高い水準でかつ均等に発揮されて初めてバランスがとれ、スピードが出ます。一人でも呼吸を乱す者がいれば、たちまちバランスを崩し艇速は落ちてしまいます。自己のレベルアップを図るとともに、仲間との協調性を最も必要とするボートの精神は、将来の町の発展に重要な意味を持つはずです。
今後は、この川辺ダム湖を中心とした左岸側の整備も検討し、町民のふれあいの場にするとともに、ボートを通じた町民スポーツの振興をさらに図りたいと考えています。

前ページ 目次へ 次ページ