スポーツクラブ先進国
ドイツに学べ
by アクセル・ベッカー
最終回] 政府のスポーツ振興とクラブへの期待
『このコーナーは、福島大学の黒須充助教授にコーディネートしていただきました。』
社会政策としてのスポーツ振興
ドイツでは、国をはじめとしたすべての行政レベル(連邦、州、郡、市町村)においてスポーツの振興が行われています。もっとも地方分権が確立しているため、国民生活に直接関与するほとんどの権限が州もしくは自治体に任せられており、連邦政府が行う政策は国際的なレベルにある競技スポーツの振興やスポーツの普及・発展のためのガイドライン作成などに限られています。
では何故、国や州、自治体がスポーツの振興を行うのでしょうか。
これまでのスポーツ振興は、人々がスポーツ活動を行うための条件整備といった色あいが強く、特にスポーツ施設の整備・拡充とスポーツクラブの育成・援助に主眼が置かれてきました。しかし、社会が変化し、複雑になっていくなかで、他の行政部門や社会的機関との新たな共同作業が検討され始めています。たとえば、幼稚園、小学校とスポーツクラブが連携し、子供の運動能力の低下や肥満防止の施策を展開したり、病院や健康保険会社、スポーツクラブが協力し、心臓病の患者に対し個々の症状に合わせた適切な運動メニューを作成し、治療、再発防止に取り組むなど、スポーツの行政への発言力は一層強まっています。
このように、スポーツの振興は、単にスポーツを広く一般に普及させるというだけではなく、社会福祉的な政策とは切り離せない、重要な役割を担う存在となってきたといえるでしょう。
つまり、スポーツとは通常、健康を増進するのはもちろんのこと、教育的要素を有すると共に、多様な社会的・文化的政策の中に統合された形で、様々な社会問題の解決に寄与しているのです。
公益を担うパートナーとしてのスポーツクラブ
ドイツのスポーツの基盤は、あくまでも受益者負担の精神と住民のボランティアシップに基づいた地域スポーツクラブにあります。
つまり、弁護士は規約づくりを、建築業者はクラブハウスの建設を、税理士は捕助金の申請と財務を、そしてジャーナリストは広報を担当するといったように、会員それぞれがクラブ運営に役立つ技能や趣味を積極的に生かしていくという活動を通して、地域社会における住民活動の仕組みを作ってきたといっても過言ではありません。
しかし、これまで社会的に優遇されてきたドイツのスポーツクラブですが、社会情勢の変化に伴い、行政支援の在り方も少しづつ変化しています。
補助金の支給に関しては、「バラマキ予算」から、「プロジェクト助成」へと移行する傾向が見られます。たとえば、障害者や高齢者など社会的弱者を対象としたプロジェクトなどがこれに該当し、これまでスポーツをする機会に恵まれなかった人々に目を向けることによって、国民全体の健康および福祉のレベルを上げることができると考えられています。また、青少年の育成に力が注がれていることから、青少年の会員を抱えるクラブに対して、重点的に補助金を分配する仕組みになっていくでしょう。
これまでスポーツクラブは、様々な税制上の優遇措置を受けてきました。しかし、最近になって、税務当局がスポーツクラブに対する「監視の目」を強化しています。それは、スポーツクラブが実際にどれだけ地域社会の中で役立っているか、社会間題を解決していく機関としての役割をきちんと果たしているかなど、本当に税制上の優遇措置を受ける価値があるかどうかを見極め、これまで以上に高い公益性を求めているからです。
これらすべての措置は、スポーツが広範な文化生活の重要な部分を占めると共に、特に助成に値するものであるという認識に依拠しています。21世紀に向けて、新たなスポーツクラブの姿が模索されています。
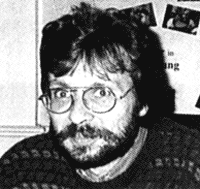
1955年ベルリン生まれ。ケルン体育大学卒業後、クライスノイス・スポーツ文化局に勤務。
こまつなおゆきの「元気の作り方」講座 ●第6回
フレッシュマンに贈る4つのCheck
この春、新しいスタートを切った皆さん、やる気いっぱい、夢と希望に胸を躍らせているとは思いますが、ちょぴり不安もあるかもしれません。
これまでとは違う世界で、年齢も仕事も趣味も好みも違うさまざまな人に会うことになるでしょう。でも臆病になったり、おびえてはイケマセンよ。
Check 1 こちらから先に挨拶する
まず、挨拶です。「挨拶はこちらからする」……これが元気づくりのコツなのです。挨拶は、「相手のためにしなくてはならないもの」と思っている人がいるかもしれませんが、実は自分の心理状態、あるいは潜在意識に働きかける作用の方が大きいのです。小さな声で、何を言ってるかわからないような曖昧な言い方で挨拶していると、相手にも暗いヤツだと思われてしまうばかりか、自分のエネルギーもますます失うことになります。挨拶は、はっきりとした言葉で、相手より先にします。これは、トレーニングで身につける一種の習慣ですから、はじめのうちは意識してやってみてください。
Check 2 握手はぎゅっと力を入れる
それから、初対面や仕事上の区切りの挨拶の際に握手をすることも多いかと思います。チャンスです。握手こそ、自分を元気にしてくれるチャンスなのです。握手の時には思い切って力強く相手の手を握りましょう。ふにゃっとした握手はダメです。相手に気後れしそうなときにはなおさらです。もし、相手が痛がったら「いや、ごめんなさい。私にとってあなたは重要人物なので、つい力が入ってしまいまして……」くらいのことを言ってもいいでしょう。力を入れるのは相手に対する親密感、信頼感の現れでもありますし、自分の存在を相手にアピールする積極的な行動として、自信にもつながります。力強い握手は自分の元気の素になるのです。
世の中の実体は「人」ですからね。あなたにとって「どうでもいい人」は一人もいませんよ。会う人には真剣に接してみることをすすめます。
Check 3 動作を大きくしてみよう
元気で明るく、はつらつと一日を過ごすことは、周りの人にも好ましい印象を与えますし、何より自分の幸せのためにそうありたいものです。しかし、実際にはイヤになってしまうことも多いし、ストレスもたまります。元気をなくして、憂鬱になってしまうこともあるかもしれませんが、そんなときは、わざと動作を大きく、速くしてみるのも方法です。たとえば、歩くとき、大股でピッチもあげて歩いてみてください。なぜか、少しだけ元気が出てくるはずです。
ふだん何気なくやっている動作には、そのときの心理状態や精神的なエネルギーが反映されます。たとえぱ、やらなければいけないことがあるのに、気分が乗ってこないようなとき、知らず知らずのうちに動作がゆっくりで、小さくなっています。そんなとき、やる気を出さなければと思っても、思うだけでは盛り上がってはきません。
そこで、元気を出すために、立ち居振る舞いや歩くときのからだの動きをわざと大きく、速くするのです。人と話をするときにも声を大きく、はっきりとしゃべるようにして、身ぶり手振りを大げさにするのも効果的です。
スポーツの世界では、試合前に一種の儀式のようにからだを大きく動かしたり、大声を出したりすることがありますよね。ニュージーランドのラグビーチーム・オールブラックスの「ウォー・クライ」は有名ですね。選手のやる気を盛り上ぽるための方法ですが、からだの動きはストレートに気持ちに作用するのです。
Check 4 20分間、無心で歩いてみる
憂鬱さが深刻だったり、大いにやる気をなくしているときには、20分くらい歩くことをおすすめします。歩き方は先ほどと同じ大股でピッチも早め。大きな動作をリズミカルに繰り返すことで、どこからか活力が沸いてくるはずです。もう一つは姿勢。やる気が出なかったり、自信がないときには、胸を引いた姿勢になりやすいのです。胸をかばうようにして、自分を守るような姿勢とでもいいますか。これを逆手にとって、元気が出ないときほど、胸を張って、背筋を伸ばして遠くを見るようにしてみてください。やせ我慢でもいいからタフな逞しい人物を演じてください。元気は自分でつくるもの。手に入れるには行動するしかありません。
小松直行
1960年横浜市長者町生まれ。筑波大学体育専門学群卒。東京大学大学院教育学研究科体育学専攻修士課程修了、同博士過程中退。資生堂研究員を経て95年より日本女子体育大学講師。著書に『身体教育の社会学(高文堂)』『暮らしのウエルネス事典(求龍堂)』『ウエルネス・ウォーキング(求龍堂)』など。
SSF・TOPICS
http://www.ssf.or.jp/
E-mail:info@ssf.or.jp
新刊紹介2冊
◎『スポーツの文化経済学』
(文化経済学ライブラリー第2巻)

SSFスポーツエイドの審査員でもある大鋸順氏(電気通信大学教授)の著作です。生活に密着している「スポーツ」を、行政・産業・スポーツ組織の面からとらえ、「行うスポーツ」から「見るスポーツ」まで、経済活動としてのスポーツの現状と将来を徹底分析したユニークな一冊です。
(芙蓉書房出版刊・本体1,500円+税)
◎『夢は箱根を駆けめぐる』
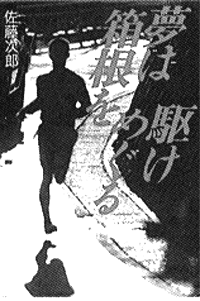
著者は、東京新聞運動部長佐藤次郎氏。神奈川大学駅伝チームの監督・大後栄治氏を通して、チームが箱根駅伝を制覇するまでに成長する過程をつぶさに取材した快作。読後の爽やかさ、この上なし。
(洋泉社刊・本体1,600円+税)
文部省人事紹介
体育局生涯スポーツ課(平成11年度の体制)
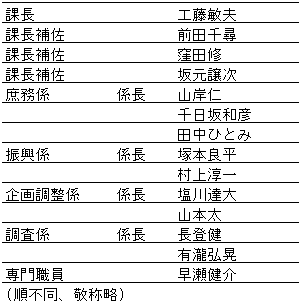
SSF人事異動報告
SSFの人事に異動がありました。新たな体制で今年度も様々な事業を実施して参りますので、今後ともよろしくお願いします。
常務理事
退任 城倉英人
新任 横山喬(前・総務部長)
お詫びと訂正
本紙前号(Vol. 29)第2面「ASFFAコングレス/ゲームズフェスティバル報告」の記事中にあった池田勝教授(大阪体育大学)による基調講演のタイトルは、「世界各国のスポーツ振興計画と日本のサッカーくじの実情」ではなく、「世界各国のスポーツ振興計画」でした。お詫びして訂正します。
前ページ 目次へ 次ページ