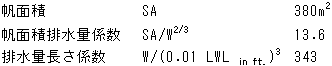菱垣廻船「浪華丸」帆走実験報告書
1999-10-15
大阪港振興協会
はじめに
菱垣廻船は江戸時代に大坂と江戸を結ぶ大動脈として活躍した商業帆船である。この船の構造、帆装や海運活動の実態などについてはすでに多くの研究があるが、その実船を復元建造し海上運転によってこの船の航海性能を明らかにする試みは今回の「浪華丸」実験をもって嚆矢とする。
菱垣廻船は船舶技術史上では弁才型と呼ばれる船の代表格であるが、この型式の船はわが国の伝統的船舶の中ではじめて人力推進に頼らず帆走だけで実用航海を行ない、それによって小人数の乗組員で大量の貨物輸送を可能にした画期的な船である。この大量輸送能力が年を追って発展する江戸期経済の物流を支えたことはよく知られている。
帆走のみに依存する航海を可能にした技術基盤は「開き走り」、すなわち横風や、さらに斜め前からの風まで利用して船を走らせることであった。弁才型の船はその船型や舵の構造、操帆のための綱取りなどに「開き走り」のための工夫が明らかに見て取られ、また文書記録や伝聞によっても「開き走り」をしたことが確かめられている。しかしどれくらいの速力で「開き走り」ができたか、またどれくらいの角度まで風に逆らって走ることができたか、などについて定量的な資料は明らかでなかった。
今回大阪市は海洋博物館「なにわの海の時空館」の中心展示として大阪の誇りでもある菱垣廻船の現尺復元を企画し、さらにこの機会に復元船を海上で実際に帆走させて映像記録に残し、また現在の機器を使って帆走性能の定量的資料を得ることはきわめて有意義であると判断した。当協会はこれを受けてこの海上帆走実験を行ない、所期の成果を得たのでここに報告するものである。
1. 「浪華丸」主要目、係数等
「浪華丸」の概略構造図、帆装図、概略船体線図をそれぞれ図1、2、3に示す。長さ、幅等の主要寸法も図中に記されている。
帆走実験時の状態は
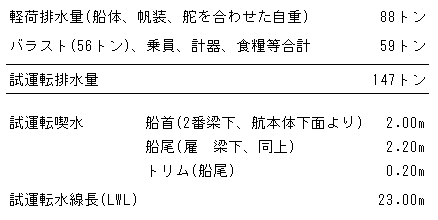
なお、この状態は本船の標準的積載量の75%程度積載に相当する。